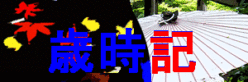糸瓜咲て痰のつまりし仏かな痰一斗糸瓜の水も間にあはずをととひのへちまの水も取らざりき
へちまさいて たんのつまりし ほとけかな
たんいっと へちまのみずも まにあわず
おとといの へちまのみずも とらざりき
 明治35年(1902年)9月21日の新聞「日本」に初出の正岡子規の句。一面に掲載された。この三句は子規の辞世と言えるもので、「絶筆三句」と呼ばれる。
明治35年(1902年)9月21日の新聞「日本」に初出の正岡子規の句。一面に掲載された。この三句は子規の辞世と言えるもので、「絶筆三句」と呼ばれる。
明治35年9月18日午前11時頃、妹の律と河東碧梧桐の手を借りて、まずまん中に「糸瓜咲て痰のつまりし佛かな」と大書。その左に「痰一斗糸瓜の水も間にあはず」と書いて、最後に右端に寝かせるように「をととひのへちまの水も取らざりき」と記す。その後昏睡状態となり、明くる19日の午前1時頃に永眠したのである。その時の様子は、碧梧桐版「子規言行録」の「絶筆」に詳しい。
十八日の朝の十時頃であったか、どうも様子が悪いという知らせに、胸を躍らせながら早速駆けつけた所、丁度枕辺には陸氏令閨と妹君が居られた。予は病人の左側近くへよって「どうかな」というと別に返辞もなく、左手を四五度動かした許りで静かにいつものまま仰向に寝て居る。余り騒々しくしてはわるいであろうと、予は口をつぐんで、そこに坐りながら妹君と、医者のこと薬のこと、今朝は痰が切れないでこまったこと、宮本へ痰の切れる薬をとりにやったこと、高浜を呼びにやったかどうかということなど話をして居た時に「高浜も呼びにおやりや」と病人が一言いうた。依って予は直ぐに陸氏の電話口へ往って、高浜に大急ぎで来いというて帰って見ると、妹君は病人の右側で墨を磨って居られる。やがて例の書板に唐紙の貼付けてあるのを妹君が取って病人に渡されるから、何かこの場合に書けるであろうと不審しながらも、予はいつも病人の使いなれた軸も穂も細長い筆に十分墨を含ませて右手へ渡すと、病人は左手で板の左下側を持ち添え、上は妹君に持たせて、いきなり中央へ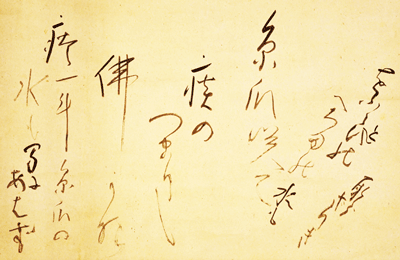
糸瓜咲て
とすらすらと書きつけた。併し「咲て」の二字はかすれて少し書きにくそうであったので、ここで墨をついでまた筆を渡すと、こんど糸瓜咲てより少し下げて
痰のつまりし
まで又た一息に書けた。字がかすれたのでまた墨をつぎながら、次は何と出るかと、暗に好奇心に駆られて板面を注視して居ると、同じ位の高さに
佛かな
と書かれたので、予は覚えず胸を刺されるように感じた。書き終わって投げるように筆を捨てながら、横を向いて咳を二三度つづけざまにして痰が切れんので如何にも苦しそうに見えた。妹君は板を横へ片付けながら側に坐って居られたが、病人は何とも言わないで無言である。また咳が出る。今度は切れたらしく反故でその痰を拭きとりながら妹君に渡す。痰はこれまでどんなに苦痛の劇しい時でも必ず設けてある痰壺を自分で取って吐き込む例であったのに、きょうはもうその痰壺をとる勇気も無いと見える。その間四五分たったと思うと、無言に前の書板を取り寄せる。予も無言で墨をつける。今度は左手を書板に持ち添える元気もなかったのか、妹君に持たせたまま前句「佛かな」と書いたその横へ
痰一斗糸瓜の水も
と「水も」を別行に認めた。ここで墨ををつぐ。すぐ次へ
間に合わず
と書いて、矢張投捨てるように筆を置いた。咳は二三度出る。如何にもせつなそうなので、予は以前にも増して動気が打って胸がわくわくして堪らぬ。また四五分も経てから、無言で板を持たせたので、予も無言で筆を渡す。今度は板の持ち方が少し具合が悪そうであったがそのまま少し筋違いに
を?ひのへちまの
と「へちまの」は行をかえて書く。予は墨をここでつぎながら、「?」の字の上の方が「ふ」のように、その下の方が「ら」の字を略したもののように見えるので「をふらひのへちまの」とは何の事であろうと聊か怪しみながら見て居ると、次を書く前に自分で「ひ」の上へ「と」と書いて、それが「ひ」の上へはいるもののようなしるしをした。それで始めて「をとヽひの」であると合点した。そのあとはすぐに「へちまの」の下へ
水の
と書いて
取らざりき
はその右側へ書き流して、例の通り筆を投げすてたが、丁度穂が先に落ちたので、白い寝床の上は少し許り墨の痕をつけた。余は筆を片付ける。妹君は板を障子にもたせかけられる。しばらくは病人自身もその字を見て居る様子であったが、予はこの場合その句に向かって何と言うべき考えも浮かばなかった。がもうこれでお仕舞いであるか、紙には書く場所はないようであるけれども、また書かれはすまいかと少し心待ちにして硯の側を去ることが出来なかったが、その後再び筆を持とうともしなかった。(明治丗五年九月)
「糸瓜の水」とは、痰をきる薬。仲秋の名月の晩に採ったのがよいといわれ、9月16日がその日であった。「糸瓜咲て」は、「糸瓜の花」と見なして、季節感を問題にすることがあるが、「咲」を「さける」などととらえる考え方がある。
「病牀六尺」には、闘病に伴う苦痛が至る所に記されてはいる。けれども、そんな苦しさを書き連ねる中で、死の6日前となる9月13日項に突然、「人間の苦痛はよほど極度へまで想像せられるが、しかしそんなに極度にまで想像したやうな苦痛が自分のこの身の上に来るとはちよつと想像せられぬ事である」と書き込んでいる。自身の写生論を病床にまで活用し、苦しみを達観する境地にまで辿り着いていたのだろう。これこそが、子規の実践してきた「俳句のかたち」なのかもしれない。
22歳で喀血してから13年。病床に伏して5年。その間に子規は、近代文学の方向性を定めた。そしてその最後、むかし「青瓢箪」とあだ名された子規は、糸瓜を見つめながら、悲壮感を纏わず逝ってしまった。
▶ 正岡子規の句





子規庵の句碑(東京都台東区)
 正岡子規が没した子規庵は、現在では子規の資料館として開放されており、当時の様子が再現されている。入場料を払えば誰でも、子規と同じ目線に立つことができ、縁側に立てば糸瓜棚、その左に「正岡子規絶筆三句碑」を見ることも出来る。
正岡子規が没した子規庵は、現在では子規の資料館として開放されており、当時の様子が再現されている。入場料を払えば誰でも、子規と同じ目線に立つことができ、縁側に立てば糸瓜棚、その左に「正岡子規絶筆三句碑」を見ることも出来る。
この「正岡子規絶筆三句碑」は、平成13年(2001年)9月19日に、子規没後百年を記念して財団法人子規庵保存会によって建立されたもの。国立国会図書館へ寄贈された唐紙の「絶筆三句」が原寸大で再現されている。
【撮影日:2019年9月16日】
▶ グーグルマップ