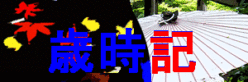毎日が辞世の句 [ 坂口昌弘 ]2200円(税込/送料込)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可【楽天ブックスならいつでも送料無料】 【楽天ブックス】
毎日が辞世の句 [ 坂口昌弘 ]2200円(税込/送料込)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可【楽天ブックスならいつでも送料無料】 【楽天ブックス】
辞世の句とは何か?
辞世とは生きた時間の集積である
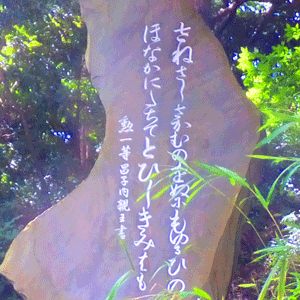 古事記における辞世のはじめは、倭建(ヤマトタケル)を助けようと走水の海に飛び込んだ弟橘比売(オトタチバナヒメ)の和歌「さねさし相摸の小野に燃ゆる火の 火中に立ちて問ひし君はも」である。則ち、「敵に仕掛けられた火中にあっても、問いかけて下さったあなたよ」と歌って、荒れ狂う海に身を躍らせると、波は鎮まり、七日後に姫の櫛が打ち上げられた。
古事記における辞世のはじめは、倭建(ヤマトタケル)を助けようと走水の海に飛び込んだ弟橘比売(オトタチバナヒメ)の和歌「さねさし相摸の小野に燃ゆる火の 火中に立ちて問ひし君はも」である。則ち、「敵に仕掛けられた火中にあっても、問いかけて下さったあなたよ」と歌って、荒れ狂う海に身を躍らせると、波は鎮まり、七日後に姫の櫛が打ち上げられた。
以降、武士や文人たちによって、多くの辞世が残された。江戸時代になって俳諧が盛んになると、五七五の辞世句も増え、最後に詠んだ句(絶吟)を辞世の句として、その人となりを伝えることも多くなった。
辞世は、人生の到達点である。時代の変遷の中で、その場所が失せようとしていることを残念に思う。今こそ、辞世の句を見つめなおす時だ。
(写真は、横須賀の走水神社にある弟橘媛命記念碑。東郷平八郎・乃木希典らが1910年に建立。揮毫は恒久王妃昌子内親王。)
辞世句一覧
◆江戸時代以前の辞世の句 一覧
| 飯尾宗祇(1502年) | ながむる月にたちぞうかるゝ |
|---|---|
| 荒木田守武(1549年) | 朝顔に今日は見ゆらんわが世かな |
◆江戸時代の辞世の句 一覧
| 斎藤徳元(1647年) | 今までは生たは事を月夜かな |
|---|---|
| 野々口立圃(1669年) | 月花の三句目を今しる世哉 |
| 神野忠知(1676年) | 霜月やあるはなき身の影法師 |
| 山本西武(1682年) | 夜の明けて花にひらくや浄土門 |
| 向井千子(1688年) | もえやすく又消えやすき螢哉 |
| 小杉一笑(1688年) | 心から雪うつくしや西の雲 |
| 岡村不卜(1691年) | あさがほのはじめて散るも哀也 |
| 図司呂丸(1693年) | 消安し都の土に春の雪 |
| 井原西鶴(1693年) | 浮世の月見過しにけり末二年 |
| 松尾芭蕉(1694年) | 旅に病んで夢は枯れ野をかけめぐる |
| 藤谷貞兼(1701年) | 月はみだぼさつや二十御来迎 |
| 萱野涓泉(1702年) | 晴れゆくや日頃心の花曇り |
| 大高子葉(1703年) | 梅で呑む茶屋もあるべし死出の山 |
| 大淀三千風(1707年) | 今日ぞはや見ぬ世の旅の衣がへ |
| 宝井其角(1707年) | 鶯の暁寒しきりぎりす |
| 服部嵐雪(1707年) | 一葉散る咄ひとはちる風の上 |
| 河合曾良(1710年) | 春に我乞食やめてもつくしかな |
| 北条団水(1711年) | おぼろおぼろ引つぺぐ胸の月清し |
| 岸本調和(1715年) | この一句衆議判なし木がらし野 |
| 山口素堂(1716年) | 初夢や通天のうきはし地主の花 |
| 志村無倫(1717年) | すはさらば水より水へゆきの道 |
| 岩田涼菟(1717年) | 合点じやそのあかつきの子規 |
| 秋の坊(1718年) | 正月四日よろづ此の世を去るによし |
| 立花北枝(1718年) | 書て見たりけしたり果はけしの花 |
| 池西言水(1722年) | 木枯の果はありけり海の音 |
| 菊后亭秋色(1725年) | 見し夢のさめても色の杜若 |
| 柳川琴風(1726年) | 一息にこの味はひぞ春の水 |
| 高野百里(1727年) | 死んで置いて涼しき月を見るぞかし |
| 杉山杉風(1732年) | 瘠顔に団扇をかざし絶し息 |
| 桑岡貞佐(1734年) | 中椀に白がゆ盈てり十三夜 |
| 上島鬼貫(1738年) | 夢返せ烏の覚ます霧の月 |
| 志太野坡(1740年) | 若水や冬は薬にむすびしを |
| 加藤原松(1742年) | 墓原や秋の蛍のふたつみつ |
| 早野巴人(1742年) | こしらへて有とはしらず西の奧 |
| 立羽不角(1753年) | 空蝉はもとのすがたに返しけり |
| 一世祇徳(1754年) | 空さえてもと来し道を帰るなり |
| 松木淡々(1761年) | 朝霜や杖で画きし富士の山 |
| 白井鳥酔(1769年) | 濃きうすき雲を待ち得てほとゝぎす |
| 加賀千代女(1775年) | 月も見て我はこの世をかしく哉 |
| 横井也有(1783年) | 短夜や我にはながき夢さめぬ |
| 与謝蕪村(1784年) | しら梅に明る夜ばかりとなりにけり |
| 越谷吾山(1788年) | 花と見し雪はきのうぞもとの水 |
| 横田柳几(1788年) | 老いらくの寝こころもよく春の雨 |
| 中村敲石(1788年) | 契りおく松やいくとせ若緑 |
| 柄井川柳(1790年) | 木枯らしや跡で芽をふけ川柳 |
| 松岡青蘿(1791年) | ふなばたや履ぬぎすつる水の月 |
| 加舎白雄(1791年) | たち出て芙蓉のしぼむ日に逢へり |
| 澤村訥子(1801年) | あぢきなや浮世の人に別れ霜 |
| 陶官鼠(1803年) | 果は我枕なるべし夏の富士 |
| 竹内玄々一(1804年) | 牽牛花やしぼめば又の朝ぼらけ |
| 府川志風(1805年) | 法の旅花野や杖の曳ちから |
| 市川團十郎(1806年) | ありがたや弥陀の浄土に冬籠り |
| 松村篁雨(1809年) | 道ばたに盆かわらけの破れけり |
| 竹塚東子(1815年) | 冬川や瀬ぶみもしらず南無阿弥陀仏 |
| 倉田葛三(1818年) | 六月や十日暮らせし一手柄 |
| 八木ほう水(1821年) | 比ときと華野に心はなちやる |
| 小林一茶(1828年) | 盥から盥に移るちんぷんかん |
| 大愚良寛(1831年) | うらをみせおもてを見せてちるもみじ |
| 遠藤曰人(1836年) | 土金や息はたえても月日あり |
| 麗々亭柳橋(1840年) | ほととぎす明かしかねたる此世かな |
| 柳亭種彦(1842年) | われも秋六十帖の名残かな |
| 辻嵐外(1845年) | 富士の山見ながらしたき頓死かな |
| 田川鳳朗(1845年) | からになる無常もありて蝸牛 |
| 鶴田卓池(1846年) | いざさらば迎え次第に月の宿 |
| 葛飾北斎(1849年) | 悲と魂でゆくきさんじや夏の原 |
| 桜井梅室(1852年) | ひとしづくけふのいのちぞ菊の露 |
| 市原多代女(1865年) | 終に行く道はいづくぞ花の雲 |
| 高杉晋作(1867年) | おもしろきこともなき世をおもしろく |
| 沖田総司(1868年) | 動かねば闇にへだつや花と水 |
◆明治時代の辞世の句 一覧
| 河井継之助(1868年) | 八十里腰抜け武士の越す峠 |
|---|---|
| 井上井月(1887年) | 闇き夜も花の明りや西の旅 |
| 大原其戎(1889年) | 寝姿の司や花をまくらもと |
| 藤野古白(1895年) | 花の頃西行もせぬ朝寝かな |
| 正岡子規(1902年) | 糸瓜咲て痰のつまりし佛かな |
| 尾崎紅葉(1903年) | 死なば秋露の干ぬ間ぞ面白き |
◆大正時代の辞世の句 一覧
| 夏目漱石(1916年) | 秋立つや一巻の書の読み残し |
|---|---|
| 野村朱鱗洞(1918年) | いち早く枯れる草なれば実を結ぶ |
| 大須賀乙字(1920年) | 干足袋の日南に氷る寒さかな |
| 内藤鳴雪(1926年) | 只たのむ湯婆一つの寒さかな |
◆昭和時代の辞世の句 一覧
| 芥川龍之介(1927年) | 水涕や鼻の先だけ暮れ残る |
|---|---|
| 芝不器男(1930年) | 一片のパセリ掃かるる暖炉かな |
| 長谷川春草(1934年) | すずしさや命を聴ける指の先 |
| 竹久夢二(1934年) | 死に隣る眠薬や蛙なく |
| 松瀬青々(1937年) | 月見して如来の月光三昧や |
| 河東碧梧桐(1937年) | 金爛帯かがやくをあやに解きつ巻き巻き解きつ |
| 泉鏡花(1939年) | 露草や赤のまんまもなつかしき |
| 種田山頭火(1940年) | もりもり盛りあがる雲へあゆむ |
| 川端茅舎(1941年) | 朴散華即ちしれぬ行方かな |
| 徳田秋声(1943年) | 生きのびてまた夏日の目にしみる |
| 杉田久女(1946年) | 鳥雲にわれは明日たつ筑紫かな |
| 山本安三郎(1947年) | 閼伽は是れ月澄む松の下雫 |
| 青木月斗(1949年) | 臨終の庭に鶯鳴きにけり |
| 原石鼎(1951年) | 松朽ち葉かゝらぬ五百木無かりけり |
| 日野草城(1956年) | 風立ちぬ深き睡りの息づかひ |
| 柳原極堂(1957年) | 吾生はへちまのつるの行き処 |
| 高浜虚子(1959年) | 春の山屍を埋めて空しかり |
| 西東三鬼(1962年) | 春を病み松の根つ子も見あきたり |
| 飯田蛇笏(1962年) | 誰彼もあらず一天自尊の秋 |
| 久保田万太郎(1963年) | 囀りや己のみ知る死への道 |
| 石田波郷(1969年) | 今生は病む生なりき烏頭 |
| 星野立子(1970年) | 春寒し赤鉛筆は六角形 |
| 橋本夢道(1974年) | 桃咲く藁家から七十年夢の秋 |
| 角川源義(1975年) | 後の月雨に終るや足まくら |
| 高野素十(1976年) | わが星のいづくにあるや天の川 |
| 秋元不死男(1977年) | 富士の根にわが眠る鳥わたりけり |
| 富安風生(1979年) | 九十五齢とは後生極楽春の風 |
| 水原秋桜子(1981年) | 紫陽花や水辺の夕餉早きかな |
| 大野林火(1982年) | 萩明り師のふところにゐるごとし |
| 中村草田男(1983年) | 勇気こそ地の塩なれや梅真白 |
| 山本健吉(1988年) | こぶし咲く昨日の今日となりしかな |
| 中村汀女(1988年) | 春暁や今はよはひをいとほしみ |
| 山口青邨(1988年) | 願ぎごとのあれもこれもと日は永し |
◆平成時代の辞世の句 一覧
| 加藤楸邨(1993年) | 梟となり天の川渡りけり |
|---|---|
| 山口誓子(1994年) | 一輪の花となりたる揚花火 |
| 江國滋酔郎(1997年) | おい癌め酌みかはさうぜ秋の酒 |
| 鈴木真砂女(2003年) | 来てみれば花野の果ては海なりし |
| 森澄雄(2010年) | 行く年や妻亡き月日重ねたる |
| 金子兜太(2018年) | 陽の柔わら歩ききれない遠い家 |
辞世のかたち
 辞世句には、来世への思いを詠んだものと、今生を評価したものがある。死に臨んでは、眼前を見つめることなどできぬだろうから、この2つに区分されることは理解できる。あとは人生終盤の句を辞世の句とするものがあるが、これも故人の人生を顧みて、このどちらかの特徴を持った句が選ばれるようだ。
辞世句には、来世への思いを詠んだものと、今生を評価したものがある。死に臨んでは、眼前を見つめることなどできぬだろうから、この2つに区分されることは理解できる。あとは人生終盤の句を辞世の句とするものがあるが、これも故人の人生を顧みて、このどちらかの特徴を持った句が選ばれるようだ。
ただ、明治の巨人・正岡子規だけはどうにも当てはまらない。死を覚悟して自ら筆を取った「絶筆三句」というものがあるが、そこには、自ら主張した写生の心が貫かれている。死の瞬間まで、一瞬一瞬を生き抜いて、その一瞬一瞬を描写し続けたと見える。まさに辞世とは「生きざま」である。