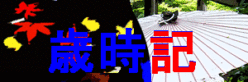けいとうの じゅうしごほんも ありぬべし
鶏頭論争を巻き起こした問題の俳句
 子規庵で明治32年(1900年)9月9日に行われた句会における、正岡子規の俳句。新聞「日本」1900年11月10日号に「庭前」の前書きで掲載された。季語は鶏頭で秋。
子規庵で明治32年(1900年)9月9日に行われた句会における、正岡子規の俳句。新聞「日本」1900年11月10日号に「庭前」の前書きで掲載された。季語は鶏頭で秋。
「俳句稿」には、下記の鶏頭の俳句もある。
(明治32年)
鶏頭の皆倒れたる野分哉
鶏頭の十本ばかり百姓家
鶏頭活けて地蔵を洗ふお願哉
駕吊りし医師か門や葉鶏頭
(明治33年)
鶏頭に秋の夕の迫りけり
鶏頭に霜見る秋の名残哉
萩刈て鶏頭の庭となりにけり
鶏頭の十四五本もありぬべし
朝貌の枯れし垣根や葉鶏頭
鶏頭や二度の野分に恙なし
鶏頭に車引き入るゝごみ屋哉
誰が植ゑしともなき路次の鶏頭や
鶏頭の錦を照す夕日哉
鶏頭の花にとまりしばつたかな
塀低き田舎の家や葉鶏頭
鶏頭の林に君を送る哉
鶏頭の四五本秋の日和哉
この「鶏頭の十四五本もありぬべし」が詠まれた時、寝たきり状態になって既に数年が経過している。二年後の9月19日に亡くなっているので、病状はかなり悪かったであろう。
「鶏頭が十四、五本もあるんだろうな」という意味で、病床から、見えない景色を詠んだものと考えることもできる。ただ、子規庵の庭に植えられた鶏頭は、寝転がっていても見えたとも言われている。上記「俳句稿」の俳句を見ると、鶏頭は、子規を取り巻く人々のようにも映る。
そう考えると、自らの死後のことをイメージして詠まれたものなのかもしれない。「十四五」の「四五」も、音調を整えるだけでなく、「死後」を導くために選択したものなのかもしれない。
当初、注目されることのなかった俳句であるが、子規門下の歌人である長塚節や斎藤茂吉によって注目され、斎藤茂吉はその著書「正岡子規」(1943年)で以下のように述べている。
子規は晩年芭蕉の句にもおもはせぶりを感じ厭味を感じたのであるが、芭蕉は新古今時代の幽玄を味つても万葉時代の純真素朴端的の趣が分からなかつた。そこで芭蕉には「鶏頭の十四五本もありぬべし」の味ひが分からない。従つて芭蕉を浅薄に理解して芭蕉を崇び子規を貶す人々もまたこの端的単心の趣が分からないのである。
以降、注目を浴びる俳句となり、1950年前後には「鶏頭論争」を巻き起こしている。論争の中心は、単なる事象の報告句ではないかというものであり、十四五本の意味を問うものでもあった。
俳句評論家の山本健吉は、これを即興詩ととらえ、ここに「鮮やかな心象風景」を見ている。
▶ 正岡子規の俳句