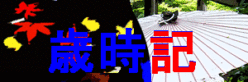とおやまに ひのあたりたる かれのかな
高浜虚子の俳句の代表作
 「五百句」(1937年)に「明治三十三年十一月二十五日 虚子庵例会」とある1900年、26歳の時の俳句。季語は枯野。「枯野に立つと、遠くに見える山に日が当たっている」というような意味で、自らの立つ枯野の陰鬱さと、遠山の明るさを対比させている。自らの境遇を嘆く情景とも、行くべき道を指し示すものとも捉えられてきた俳句。
「五百句」(1937年)に「明治三十三年十一月二十五日 虚子庵例会」とある1900年、26歳の時の俳句。季語は枯野。「枯野に立つと、遠くに見える山に日が当たっている」というような意味で、自らの立つ枯野の陰鬱さと、遠山の明るさを対比させている。自らの境遇を嘆く情景とも、行くべき道を指し示すものとも捉えられてきた俳句。
なおこの俳句は、開眼の一句とも言えるもので、虚子自らも好んで取り上げ、高浜虚子の俳句の代表作に挙げられている。
高浜年尾の「人生観めいたもの」との指摘には、「人生観と言う必要はない。目の前にある姿で作ったものが本当だ。松山の御宝町のうちを出て道後の方を眺めると、道後のうしろの温泉山にぽっかり冬の日が当たっているのが見えた。その日の当っているところに何か頼りになるものがあった。それがあの句だ」と答えた。
自評には下記のようにある。
遠山が向ふにあって、前が広漠たる枯野である。その枯野には日は当ってゐない。落莫とした景色である。唯、遠山に日が当ってをる。私はかういふ景色が好きである。わが人生は概ね日の当らぬ枯野の如きものであってもよい。寧ろそれを希望する。たゞ遠山の端に日の当ってをる事によって、心は平らかだ。烈日の輝きわたってをる如き人生も好ましくない事はない。が、煩はしい。遠山の端に日の当ってをる静かな景色、それは私の望む人生である。
▶ 高浜虚子の句
 【中古】 ホトトギス雑詠選集(夏の部) / 高浜 虚子 / 朝日新聞出版 [文庫]【メール便送料無料】【最短翌日配達対応】30394円(税込/送料別)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可【メール便送料無料、通常24時間以内出荷】 【もったいない本舗 楽天市場店】
【中古】 ホトトギス雑詠選集(夏の部) / 高浜 虚子 / 朝日新聞出版 [文庫]【メール便送料無料】【最短翌日配達対応】30394円(税込/送料別)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可【メール便送料無料、通常24時間以内出荷】 【もったいない本舗 楽天市場店】