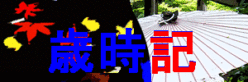はるかぜや とうしいだきて おかにたつ
本当に闘志を抱いていたか?|当時の虚子について
 「五百句」(高浜虚子1937年)所収の、高浜虚子の俳句。それまで小説に注力していた虚子が、かつての盟友河東碧梧桐の新傾向俳句に対抗して「守旧派」を宣言。俳壇復帰を果たした大正2年(1913年)、2月11日の三田俳句会(東京芝浦)で詠まれた俳句である。
「五百句」(高浜虚子1937年)所収の、高浜虚子の俳句。それまで小説に注力していた虚子が、かつての盟友河東碧梧桐の新傾向俳句に対抗して「守旧派」を宣言。俳壇復帰を果たした大正2年(1913年)、2月11日の三田俳句会(東京芝浦)で詠まれた俳句である。
虚子自身が「句意は多言を要さぬ」と言っているように、心情をありのままに描写した俳句である。
当時の虚子は、小説と俳句の間で揺れ動き、「ホトトギス」の方向性も定まらずノイローゼ状態で、俳壇では碧梧桐の方が優勢であった。この俳句が詠まれた大正2年には、俳壇復帰を宣言するものの、嶋田青峰に、うまくいかなくなったホトトギスの編集を一任しているのである。
よって、ここにある「闘志」というものの実情は、「空元気」のようなものだったとも考えられるのである。ただ、碧梧桐の打ち出した「新傾向」のために、行くべき道は定まった。
この年以降、虚子の運気は向上。反対に碧梧桐は下降線をたどっていく。
1937年に虚子は、碧梧桐の死を悼んで「たとふれば独楽のはぢける如くなり」と詠んでいる。俳壇の盟主となった虚子と、場外に弾き飛ばされた碧梧桐。その突端は、この俳句にあったのかもしれない。
大正2年春の虚子の俳句に、「一つ根に離れ浮く葉や春の水」がある。対抗心はあっても、根は同じという思いを、常に抱いていたのかもしれない。晩年までふたりの交流は続いていたという。
虚子が窮地に陥った時、その心に火を灯したのは碧梧桐であった…
▶ 高浜虚子の俳句