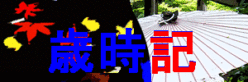俳句における季語とは何か
季語と歳時記
四季の属性が与えられた言葉を「季語」、それを季節ごとに分類したものを「歳時記」という。現代の歳時記は、主に俳句用に作られたもので、句作に便利なように、解説や例句が添えられている。
しかし、季語に関して絶対的な分類はなく、松尾芭蕉も「季節の一つもさがし出したらんは後世によき賜也」と述べている。つまり、新しい季語を発見することも、句作のひとつの目的だと言える。
このようなこともあり、歳時記における季語の分類は、その編集によって大きく異なる。ただ、季語にとって真に重要なのは、属性ではない。「本意」という、心に訴えかけるものがあり、それに目を向けなければ、句は死文に等しい。
季語の誕生と季題との違い
日本の詩歌の特色は季節感にあり、既に万葉集では季節ごとの部立てがなされている。
「季語」の言葉を生んだのは大須賀乙字で、明治41年12月号の俳誌「アカネ」の句評欄に初めて用いたとされている。それ以前、連歌や俳諧が盛んな折には、「四季の詞」とか「季の詞」と言っていた。
「季語」が生まれるのとほぼ時を同じくして生まれた言葉に「季題」があり、ホトトギス系の結社でよく用いられている。これは「季節の題目」という意味で、季節を詠み込む決まりの「俳諧の発句」の中から俳句が生まれたことを意識している。
ただ、「季語」の範疇は「季題」よりも広い。敢えて言うならば、季重なりのある句の場合、題目となった季語は「季題」、題目以外の四季の詞は「季語」となる。
俳句の中での季語の用い方
「俳諧の発句」の延長線上に俳句を置く考えから、伝統的な俳句では季語を必要とする。近代俳句の発展とともに様々な試みがなされ、季語を必要としない考えも生まれているが、現代俳句における主流ではない。
結社によって季語の扱いも大きく異なり正解はないが、概ね俳句は、五七五の中に季語を一つだけ盛り込む。入れる場所に指定はない。
季語を2つ以上用いるものを季重なりと言って嫌う傾向にあるが、古い句ほど季重なりに躊躇いはなく、音や意味のバランスに重きを置く。
高浜虚子は「俳句とはどんなものか」の中で、「季重なりはいけないと一概に排斥する月並宗匠輩の言葉はとるに足りませぬ」と喝破し、季節またぎの季重なりも容認している。ただし、重複感を取り除くことには腐心しなければならないとも述べている。
季語の役割とは何か
二条良基は「僻連抄」で、「時にしたがひて変はる姿を見れば、心も動き、詞もあらはるるなり」と述べている。つまり俳句に通じる和歌は、(至上に重きを置かず)移ろいの中に美を見出すことで生じる、嘆息にも似た詩である。その時「季の詞」は、変化の象徴として現れる。
また、座の文芸として発展してきた俳句における「季語」は、場の共感を得るツールでもある。そこに求められる要素は、蓄積されてきた悠久の記憶。その、歴史が育んだ不変性に目を向けた時、それを用いる者の主観は和らいでいく。
芭蕉の説く「不易流行」。変わりゆく景色の中に永遠を見つめる精神は、季節の中に身を置いて明らかになる。「変化」と「不変」を内包する季語を突き詰め、俳句を捻り出すことは、自らの立ち位置を定めるものでこそある。
季語検索に便利な歳時記
山本健吉基本季語五〇〇選
俳句研究で名高い山本健吉氏によって、1986年に刊行された基本季語五〇〇選。季語が氾濫する現代において、500という数値は少なすぎるようにも思われるが、関連季語も掲載してあるため、実数は数千に及ぶ。むしろ、基本季語が分かりやすく整理されており、関連する季語検索のための辞書としても使用できる。季語の背景に関する言及も鋭く、読み物としても面白い。現在では文庫版が流通しており、コンパクトに携行できて便利。
俳諧歳時記栞草
1803年(享和3年)に曲亭馬琴が上梓した「俳諧歳時記」を、1851年(嘉永4年)に藍亭青藍が「増補改正俳諧歳時記栞草」として刊行。俳諧歳時記には2629の季語、俳諧歳時記栞草には3467の季語を収録し、近世歳時記の最高峰とされた。
俳諧歳時記栞草では、季節ごとに、いろは順で季語の解説を載せ、最後に雑之部で俳諧の決まりごとなどに触れている。俳諧必携の書であるだけでなく、現代俳句における季語検索に耐え得る歳時記でもある。