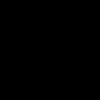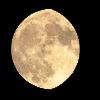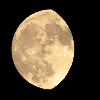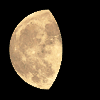仲秋の季語 名月
十五夜(じゅうごや)・三五の月(さんごのつき)・月見(つきみ)・今日の月(きょうのつき)・望月(もちづき)・十六夜(いざよい・じゅうろくや)・既望(きぼう)・立待月(たちまちづき)・十七夜(じゅうしちや)・居待月(いまちづき)・十八夜(じゅうはちや)・臥待月(ふしまちづき)・寝待月(ねまちづき)・更待月(ふけまちづき)・二十日月(はつかづき)・二十三夜(にじゅうさんや)・明月(めいげつ)・良夜(りょうや)・無月(むげつ)・雨月(うげつ)・初月(しょげつ)・初月夜(はつづきよ)・二日月(ふつかづき)・三日月(みかづき)・新月(しんげつ)・待宵(まつよい)・小望月(こもちづき)
 単に「月」といえば三秋の季語である。毎月十五夜はあるものの、単に「十五夜」と言った場合、通常は、仲秋の名月がのぼる旧暦8月15日の夜を指す。
単に「月」といえば三秋の季語である。毎月十五夜はあるものの、単に「十五夜」と言った場合、通常は、仲秋の名月がのぼる旧暦8月15日の夜を指す。
月見は、平安時代に日本に伝わった中国の「中秋節」に由来する風習で、「観月の宴」が開かれていた。中国ではこの日、月を祭り、幸せを祈りながら月餅を切り分けて食べる。
稲刈り前の農閑期と重なることや、気候の良さもあり、近世に入って庶民にも広まった。
別名「芋名月」とも呼ばれるが、芋の収穫祭の意味も込められ、かつては里芋を高く盛って月に供えられた。現在では里芋の代わりに団子を用いる。海外でも収穫祭に因んだ名が用いられており、秋分の日に最も近い満月のことを「ハーベストムーン」と呼ぶ。
月見行事には「栗名月」「豆名月」とも呼ぶ「十三夜」もあるが、こちらは仲秋の名月から約1カ月後の陰暦9月13日の名月をいう。仲秋の名月だけを愛でることを「片見月」として忌む。
▶ 関連季語 月(秋)
▶ 関連季語 後の月(秋)
【名月の俳句】
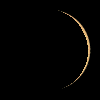 二日月
二日月
月の第二日目の夜に出る月のことを「二日月」というが、俳句の世界では、特に旧暦8月2日の月を指して仲秋の季語とする。
 十五夜・名月・明月・三五の月・望月・今日の月・良夜
十五夜・名月・明月・三五の月・望月・今日の月・良夜
旧暦8月15日の月。月の出た夜は「良夜」という。望月(もちづき)は、「みてりつき(満月)」から来ているという説がある。月の模様がウサギに見えることから、中国では不老不死の薬をウサギが搗いているいると言われているが、日本では「もちづき」から「餅つき」と結び付けられた。
 二十三夜
二十三夜
旧暦8月23日の月。この月はちょうど真夜中に出てくる。「二十三夜待」ともいう。