投稿者: uranari
季語|冬至(とうじ)
仲冬の季語 冬至
 冬至日とも言い、一年のうちで最も昼が短くなる日のことを指し、12月22日前後となる。また、二十四節気の第22で、大雪と小寒に挟まれた期間のことでもある。この期間の七十二候は、初候が夏枯草が芽を出すという「乃東生」、次候が鹿が角を落とす「麋角解」、末候が雪の下で麦が芽を出す「雪下出麦」。
冬至日とも言い、一年のうちで最も昼が短くなる日のことを指し、12月22日前後となる。また、二十四節気の第22で、大雪と小寒に挟まれた期間のことでもある。この期間の七十二候は、初候が夏枯草が芽を出すという「乃東生」、次候が鹿が角を落とす「麋角解」、末候が雪の下で麦が芽を出す「雪下出麦」。
太陽が最も南に到るこの日、陽の気が弱まり、陰の気が最も強くなる日であるとされる。俳諧歳時記栞草には、「冬至に三義あり、一は陰極るの至り、二は陽気はじめて至る、三は日南に行くの至り、故に冬至といふ」とある。
冬至のことを「一陽来復」とも言うが、陰が極まり陽に転ずることを指している。東京の穴八幡宮では、冬至祭が盛大に催され、「一陽来復」の御守を求めて多くの人が訪れる。
この日、小豆を使った冬至粥を食べ、冬至風呂と称して柚子湯に入る。冬至粥には邪気を祓う効用があるとされ、柚子は「融通」に掛けて、冬至に「湯治」の意味を込める。
また、冬至南瓜も知られるが、冬至に「ん」のつくものを食べると運気が上昇するとの縁起かつぎにより、「なんきん」を食べるのである。
19年に1度、冬至の日が朔になることがあり、これを朔旦冬至(さくたんとうじ)と言って、瑞祥とされる。直近の朔旦冬至は2014年であったが、次回は特殊事情で19年後にならず、2052年となる。
【冬至の俳句】
門前の小家もあそぶ冬至かな 野沢凡兆
季語|狼(おおかみ)
三冬の季語 狼
 ネコ目イヌ科イヌ属。タイリクオオカミの亜種であり、ハイイロオオカミと同種のニホンオオカミは、本州・四国九州に棲んでいた。1905年に奈良県東吉野村で捕獲されたのを最後に、絶滅したと考えられている。また、北海道には毛並が茶色のエゾオオカミが生息していたが、これも1900年ごろに絶滅した。
ネコ目イヌ科イヌ属。タイリクオオカミの亜種であり、ハイイロオオカミと同種のニホンオオカミは、本州・四国九州に棲んでいた。1905年に奈良県東吉野村で捕獲されたのを最後に、絶滅したと考えられている。また、北海道には毛並が茶色のエゾオオカミが生息していたが、これも1900年ごろに絶滅した。
イヌは、オオカミが飼い馴らされて家畜化したものと考えられている。西洋では牧畜が盛んだったこともあり、害獣との位置付けが強いが、農耕社会である日本では、害獣を駆逐する益獣としての位置付けから、神格化されることもあった。そのため、「おおかみ」の語源は「大神」であるとされる。
また、真神(まかみ)は狼を神格化した古語であり、万葉集には舎人娘子の和歌として、
大口の真神が原に降る雪は いたくな降りそ家もあらなくに
が載る。
日本神話における狼は、ヤマトタケルの項が印象的。景行天皇紀に、ヤマトタケルが信濃山中で迷った時に、白き狗が出てきて、美濃に導いたとある。この「白き狗」が狼のことで、ヤマトタケルにゆかりのある秩父の三峯神社は、狼を守護神としている。
欽明天皇紀には、秦大津父という臣を得た時の話が出て来る。秦大津父が伊勢からの帰りに、二匹の狼が取っ組み合いをしており、「貴き神にして、あらき行を楽む」とある。「もし猟士に逢はば、禽られむこと尤く速けむ」と言って、その取っ組み合いを押しとどめ、「ともに命全けてき」と解き放った。
西洋では、グリム童話の「赤ずきん」「狼と七匹の子山羊」、イソップ物語の「オオカミ少年」など、悪いイメージで語られる物語が多いが、古代ローマの建国神話には、建国者の育ての親だとも語られている。
【狼の俳句】
狼をのがれて淋し山の月 島田五空
季語|年の暮(としのくれ)
暮の季語 年の暮
年の瀬(としのせ)・年暮るる(としくるる)・歳晩(さいばん)
 一年の終わりの期間を年の暮というが、感覚的には、新年の準備を始める12月中旬ころから大晦日まで。
一年の終わりの期間を年の暮というが、感覚的には、新年の準備を始める12月中旬ころから大晦日まで。
徒然草第十九段では、次のように年末の慌ただしさを表現している。
さて、冬枯のけしきこそ、秋にはをさをさ劣るまじけれ。汀の草に紅葉の散り止まりて、霜いと白うおける朝、遣水より烟の立つこそをかしけれ。年の暮れ果てて、人ごとに急ぎあへるころぞ、またなくあはれなる。すさまじきものにして見る人もなき月の寒けく澄める、廿日余り空こそ、心ぼそきものなれ。御仏名、荷前の使立つなどぞ、あはれにやんごとなき。公事ども繋く、春の急ぎにとり重ねて催し行はるゝさまぞ、いみじきや。追儺より四方拝に続くこそ面白けれ。晦日の夜、いたう闇きに、松どもともして、夜半過ぐるまで、人の、門叩き、走りありきて、何事にかあらん、ことことしくのゝしりて、足を空に惑ふが、暁がたより、さすがに音なくなりぬるこそ、年の名残も心ぼそけれ。亡き人のくる夜とて魂祭るわざは、このごろ都にはなきを、東のかたには、なほする事にてありしこそ、あはれなりしか。
▶ 関連季語 年の内(暮)
【年の暮の俳句】
ともかくもあなたまかせの年の暮 小林一茶
分別の底たゝきけり年の暮 松尾芭蕉
季語|ずわい蟹(ずわいがに)
三冬の季語 ずわい蟹
 十脚目(エビ目)ケセンガニ科の蟹。同じく冬の季語となる鱈場蟹(たらばがに)は、十脚目異尾下目(ヤドカリ下目)タラバガニ科に属し、正確には蟹ではなく、ヤドカリである。
十脚目(エビ目)ケセンガニ科の蟹。同じく冬の季語となる鱈場蟹(たらばがに)は、十脚目異尾下目(ヤドカリ下目)タラバガニ科に属し、正確には蟹ではなく、ヤドカリである。
ずわい蟹は、メスよりもオスの方が大きい。山陰以東の日本海が主な漁場で、福井県で水揚げされるオスは「越前蟹」、山陰地方で水揚げされるオスは「松葉蟹」と呼ばれる。
語源は、細い木の枝を指す古語「楚(すわえ)」にあり、それがが訛って「ずわい」になったとされる。鍋や刺し身など、冬の味覚として人気が高く、蟹味噌や卵巣も食す。
地方によって、漁期が異なり、山陰地方の松葉蟹は11月6日から3月20日。ただし、メスは11月6日から12月31日までと決められている。
なお、ずわい蟹の種類には、ここで説明したオピリオと呼ばれるズワイガニのほか、ロシアやカナダから輸入されるオオズワイガニ、日本海特有種で水っぽいとも言われるが甘さはズワイガニを上回るベニズワイガニがある。
【ずわい蟹の俳句】
ずわい蟹大手広げて届きけり 根本ゆきを
季語|ポインセチア(ぽいんせちあ)
仲冬の季語 ポインセチア
 トウダイグサ科トウダイグサ属、和名はショウジョウボクで、クリスマスフラワーとも呼ばれる。原産地はメキシコで、アメリカの初代メキシコ公使J・R・ポインセットが母国に持ち帰り広めたことから、ポインセチアと呼ばれる。
トウダイグサ科トウダイグサ属、和名はショウジョウボクで、クリスマスフラワーとも呼ばれる。原産地はメキシコで、アメリカの初代メキシコ公使J・R・ポインセットが母国に持ち帰り広めたことから、ポインセチアと呼ばれる。
クリスマスフラワーと呼ばれるが、その鑑賞対象は、主に赤く染まる葉であり、それをキリストの血の色と見る。
日本には明治時代に渡来し、酒に浮かれ舞う猩々の赤顔に見立てて、猩々木(しょうじょうぼく)の名がついた。
クリスマスの時期に美しい赤色を楽しむには、約2カ月前から、人為的に光を遮断する短日処理を施す必要がある。
葉が赤色になるものの外、白色や桃色になるものもある。皮膚炎を発症する有毒成分を含むため、取り扱いには注意を要する。
【ポインセチアの俳句】
ポインセチアこころに人の棲まずなりぬ 草間時彦
季語|白菜(はくさい)
三冬の季語 白菜
 アブラナ科アブラナ属の二年生植物。原産地は地中海沿岸。中国に伝わり、カブととツケナの交雑から、11世紀頃には結球白菜が生まれていたと言われている。因みに、欧州に残ったものからキャベツが生まれている。白菜の英名は「Chinese cabbage」で、中国のキャベツの意。
アブラナ科アブラナ属の二年生植物。原産地は地中海沿岸。中国に伝わり、カブととツケナの交雑から、11世紀頃には結球白菜が生まれていたと言われている。因みに、欧州に残ったものからキャベツが生まれている。白菜の英名は「Chinese cabbage」で、中国のキャベツの意。
11月下旬から2月が旬で、鍋物には欠かせない食材であるが、普及したのは明治時代になってから。日清戦争・日露戦争で、中国野菜に触れたことが契機になったと言われている。
江戸時代には非結球種が渡来したが、交雑が起きて育種が難しく、定着しなかった。明治時代の終わりころから育種に成功するようになり、現在ではキャベツ・ダイコンに次ぐ生産量を誇る。
白菜から色々な加工食品も生まれているが、代表的なのは漬物とキムチ。ただ、朝鮮半島で白菜の栽培方法が確立されたのは、近代になってから。白菜キムチの歴史も、白菜の漬物同様、比較的新しい。
【白菜の俳句】
何のむなしさ白菜白く洗ひあげ 渡邊千枝子
季語|寒波(かんぱ)
三冬の季語 寒波
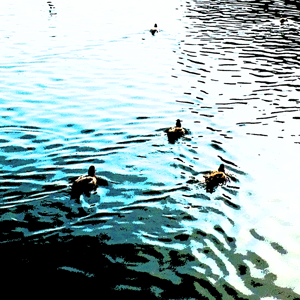 冬になると、シベリア大陸で発達した寒気団が、波のように押し寄せてくる。規模の大きいものは「大寒波」と言う。
冬になると、シベリア大陸で発達した寒気団が、波のように押し寄せてくる。規模の大きいものは「大寒波」と言う。
気象庁の「気温に関する用語」では、「主として冬期に、広い地域に2~3日、またはそれ以上にわたって顕著な気温の低下をもたらすような寒気が到来すること」と記されている。
冬期に偏西風の蛇行が大きくなると、シベリア高気圧とアリューシャン低気圧の発達により、西高東低の気圧配置が強まる。この時に、北西風を伴い、強い寒波がやってくる。日本海側では雪、太平洋側では乾燥する。
クリスマス時期の寒波は、「クリスマス寒波」という。
【寒波の俳句】
寒波来こゑを失くして息を吐く 岸田稚魚
季語|枯木(かれき)
三冬の季語 枯木
 俳句の世界では、立ち枯れした木のことではなく、冬になって葉を落とした木のことを言う。
俳句の世界では、立ち枯れした木のことではなく、冬になって葉を落とした木のことを言う。
「こぼく」と言えば、立ち枯れの木のことを指し、「無心」をも指す。また「枯木(こぼく)花開く」という言葉があり、衰えゆくものが再び脚光を浴びることをいう。
季語|都鳥(みやこどり)
三冬の季語 都鳥
 チドリ目ミヤコドリ科に分類される鳥類の一種にミヤコドリがあるが、古来、和歌などで詠まれる都鳥はチドリ目カモメ科カモメ属に分類されるユリカモメ(百合鷗)のことだと言われている。日本には冬鳥として、ユーラシア大陸北部からやってくる。
チドリ目ミヤコドリ科に分類される鳥類の一種にミヤコドリがあるが、古来、和歌などで詠まれる都鳥はチドリ目カモメ科カモメ属に分類されるユリカモメ(百合鷗)のことだと言われている。日本には冬鳥として、ユーラシア大陸北部からやってくる。
百合鷗のことを都鳥と称するようになったのは、伊勢物語の第九段「東下り」の件に因るとされる。
「なほ行き行きて、武蔵野の国と下つ総の国との中に、いと大きなる河あり。それをすみだ河といふ。その河のほとりにむれゐて思ひやれば、限りなく遠くも来にけるかなとわびあへるに、渡守、はや舟に乗れ、日も暮れぬ、といふに、乗りてわたらむとするに、皆人ものわびしくて、京に思ふ人なきにしもあらず。さる折しも、白き鳥の嘴と脚と赤き、鴫の大きさなる、水のうへに遊びつゝ魚をくふ。京には見えぬ鳥なれば、皆人見しらず。渡守に問ひければ、これなむ都鳥といふをきゝて、
名にし負はゞいざことゝはむ都鳥わが思ふ人はありやなしやと
とよめりければ、舟こぞりて泣きにけり。」
とある。
京都で百合鷗が見られるようになったのは最近のことであり、上記のような「白き鳥の嘴と脚と赤き、鴫の大きさなる、水のうへに遊びつゝ魚をくふ」という描写から、伊勢物語の都鳥は百合鷗で間違いないと考えられている。
なお、伊勢物語中の「名にし負はゞ~」の和歌は、在原業平の歌として古今和歌集に載るもの。在原業平が東下りしたかどうかは諸説あるが、浅草の「言問橋」の名は、この和歌が由来となっている。また、東京はこの物語をもとにして、1965年に都鳥(とちょう)を「ゆりかもめ」とした。
ただし、伊勢物語より100年ほど前の万葉集にも「都鳥」の和歌が一首あり、大伴家持は
舟競ふ堀江の川の水際に 来居つつ鳴くは都鳥かも
と歌っている。この鳥が何を指すかは分かっていない。
都鳥の語源は、その名の通り「都」に結びつけるものもあるが、伊勢物語の記述を引けば不自然となる。「ミャー」と鳴く鳥という説や、「雅なる」鳥との説もある。
【都鳥の俳句】
頭上過ぐ嘴脚紅き都鳥 松本たかし

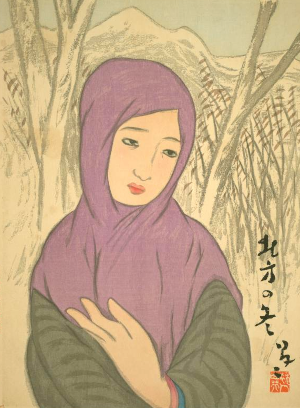 郭煕(1023年?~1085年?)の画論「臥遊録」に、「春山淡冶にして笑うが如く、夏山蒼翠にして滴るが如く、秋山明浄にして粧うが如く、冬山惨淡として眠るが如く」とある。これをもとに、
郭煕(1023年?~1085年?)の画論「臥遊録」に、「春山淡冶にして笑うが如く、夏山蒼翠にして滴るが如く、秋山明浄にして粧うが如く、冬山惨淡として眠るが如く」とある。これをもとに、