晩冬の季語 寒の雨
 寒の内(寒の入から立春の前日まで:1月5日頃から2月3日頃まで)に降る冷たい雨。寒々とした冬の雨を指す「寒雨(かんう)」とは異なる。
寒の内(寒の入から立春の前日まで:1月5日頃から2月3日頃まで)に降る冷たい雨。寒々とした冬の雨を指す「寒雨(かんう)」とは異なる。
「寒九の雨」とは、寒の入りから9日目(1月13日頃)に降る雨をいい、「寒九の雨は豊作のしるし」と言われた。寒九には、一番水が澄むとの言い伝えがある。
 寒の内(寒の入から立春の前日まで:1月5日頃から2月3日頃まで)に降る冷たい雨。寒々とした冬の雨を指す「寒雨(かんう)」とは異なる。
寒の内(寒の入から立春の前日まで:1月5日頃から2月3日頃まで)に降る冷たい雨。寒々とした冬の雨を指す「寒雨(かんう)」とは異なる。
「寒九の雨」とは、寒の入りから9日目(1月13日頃)に降る雨をいい、「寒九の雨は豊作のしるし」と言われた。寒九には、一番水が澄むとの言い伝えがある。
 「厄払い」とは、とりついた悪いものを取り除くという意味がある。本来は「厄祓」と書き、神仏に祈って穢れを払い落とすことである。
「厄払い」とは、とりついた悪いものを取り除くという意味がある。本来は「厄祓」と書き、神仏に祈って穢れを払い落とすことである。
「厄落し」とは、災厄を模擬化して、以降の災厄を取り除こうとするものである。江戸時代には褌を落として「厄落し」とし、これを「ふぐりおとし」と呼んだ。
厄払いは寺社に行けば年中受け付けてもらえるものではあるが、現在では元旦から節分までに行われることが多い。俳諧歳時記栞草(1851年)では「厄払、厄落」として、冬之部十二月に分類している。古くは旧暦大晦日に行われ、節分の行事であった。
現代でも、災厄に見舞われるとされる「厄年」は、広く認識されている。厄年とは、数え年の男25歳・42歳・61歳、女19歳・33歳・37歳になる1年のことである。
厄拂あとはくまなき月夜かな 大島蓼太
寒弾(かんびき)・寒稽古(かんげいこ)・寒復習(かんざらい)
 寒中の早朝や夜更けに、芸事などの稽古をすること。三味線の稽古をすることを「寒弾」という。武道においては「寒稽古」という。
寒中の早朝や夜更けに、芸事などの稽古をすること。三味線の稽古をすることを「寒弾」という。武道においては「寒稽古」という。
寒さの中で精神を鍛え、技術の向上を目指す。
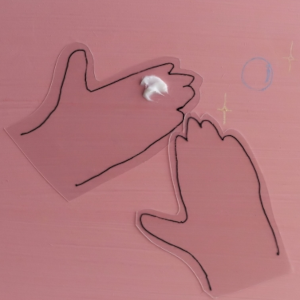 皮膚に亀裂が入って、炎症を伴って赤くなったり出血したりしたものをいう。皸の亀裂は、表皮の奥深くや真皮にまで届くことがあり、ひびよりも深い。
皮膚に亀裂が入って、炎症を伴って赤くなったり出血したりしたものをいう。皸の亀裂は、表皮の奥深くや真皮にまで届くことがあり、ひびよりも深い。
冬になると、乾燥した空気と、汗や皮脂の分泌量の低下に伴って、皮膚の水分が不足する。その状態で刺激を与えると、皮膚の弾性力が限界となって、亀裂が入る。水が蒸発する時、皮膚の水分も一緒に蒸発するため、水仕事をした後などに発生しやすい。血行不良が原因でできる「霜焼」とは発生メカニズムが違う。
皸をかくして母の夜伽かな 小林一茶
 メルフィーナ ひび・あかぎれクリーム 40g【第3類医薬品】[ネコポス配送1]1000円(税込/送料込)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可《日時指定・代金引換不可》【おくすり奉行28】
メルフィーナ ひび・あかぎれクリーム 40g【第3類医薬品】[ネコポス配送1]1000円(税込/送料込)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可《日時指定・代金引換不可》【おくすり奉行28】
 【第2類医薬品】新新薬品工業 マーカムHP水性クリーム 50g 乾皮症 ひじ・ひざ・かかと・�1000円(税込/送料込)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可有効成分ヘパリン類似物質配合【CosM@rt】
【第2類医薬品】新新薬品工業 マーカムHP水性クリーム 50g 乾皮症 ひじ・ひざ・かかと・�1000円(税込/送料込)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可有効成分ヘパリン類似物質配合【CosM@rt】
 【第3類医薬品】ニチバン あかぎればん 10g 手指のあかぎれ・ひび・さかむけを保護1000円(税込/送料込)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可切り傷、あかぎれに【ミライズリンク】
【第3類医薬品】ニチバン あかぎればん 10g 手指のあかぎれ・ひび・さかむけを保護1000円(税込/送料込)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可切り傷、あかぎれに【ミライズリンク】
 【第2類医薬品】へパロイド乳液α ヘパロイド 乳液 保湿 乾燥肌 肌荒れ 手指の荒れ ひび �1000円(税込/送料別)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可手指の荒れ ひじ ひざ かかと くるぶしの角化症 ヘパリン類似物質 乾燥 保湿 血行促進 抗【バンキョードラッグ 楽天市場店】
【第2類医薬品】へパロイド乳液α ヘパロイド 乳液 保湿 乾燥肌 肌荒れ 手指の荒れ ひび �1000円(税込/送料別)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可手指の荒れ ひじ ひざ かかと くるぶしの角化症 ヘパリン類似物質 乾燥 保湿 血行促進 抗【バンキョードラッグ 楽天市場店】
 【当日発送】【第2類医薬品】【送料無料】トフメルA15g 携帯用に便利な15g チューブタイ�1000円(税込/送料込)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可【2025年6月&11月 楽天 月間優良ショップ受賞!】すりきずやきりきず、やけどなどのケガ【安達太陽堂 楽天市場店】
【当日発送】【第2類医薬品】【送料無料】トフメルA15g 携帯用に便利な15g チューブタイ�1000円(税込/送料込)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可【2025年6月&11月 楽天 月間優良ショップ受賞!】すりきずやきりきず、やけどなどのケガ【安達太陽堂 楽天市場店】
 【第3類医薬品】コロスキン 11ml1000円(税込/送料込)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可第3類医薬品 コロスキン 11ml 小切傷 すりきず さかむけ あかぎれ ささくれ 水絆創膏 絆創�【ケーズストア 楽天市場店】
【第3類医薬品】コロスキン 11ml1000円(税込/送料込)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可第3類医薬品 コロスキン 11ml 小切傷 すりきず さかむけ あかぎれ ささくれ 水絆創膏 絆創�【ケーズストア 楽天市場店】
 【第2類医薬品】■ポスト投函■家庭の常備薬 キップパイロール-Hi 40g1000円(税込/送料込)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可【送料無料】/軟膏剤/塗り薬/軽度のやけど/切り傷・すり傷/ひび・あかぎれ/かみそりまけ【ドラッグストアザグザグ通販】
【第2類医薬品】■ポスト投函■家庭の常備薬 キップパイロール-Hi 40g1000円(税込/送料込)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可【送料無料】/軟膏剤/塗り薬/軽度のやけど/切り傷・すり傷/ひび・あかぎれ/かみそりまけ【ドラッグストアザグザグ通販】
 【第2類医薬品】リレイジュHPゲル「エルモディアHPの代替品」 20g しもやけ あかぎれ 傷 �1000円(税込/送料込)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可本品はゆうパケット発送で全国どこでも送料無料!(北海道・沖縄・離島含む)【福薬本舗 健康館】
【第2類医薬品】リレイジュHPゲル「エルモディアHPの代替品」 20g しもやけ あかぎれ 傷 �1000円(税込/送料込)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可本品はゆうパケット発送で全国どこでも送料無料!(北海道・沖縄・離島含む)【福薬本舗 健康館】
 【合算3150円で送料無料】【指定医薬部外品】ユースキン 80gチューブ1000円(税込/送料別)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可ひび、あかぎれ、しもやけを治す、黄色いビタミン系クリーム【サポートショップ】
【合算3150円で送料無料】【指定医薬部外品】ユースキン 80gチューブ1000円(税込/送料別)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可ひび、あかぎれ、しもやけを治す、黄色いビタミン系クリーム【サポートショップ】
 【第2類医薬品】健栄製薬 乾燥肌治療薬 ヒルマイルド ローション 30g【メール便発送/3個�1000円(税込/送料別)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可乾燥肌治療薬/ヒルマイルドローション/ヘパリン類似物質/健栄製薬 手指の荒れ、ひじ・�【朝の目覚めショップ】
【第2類医薬品】健栄製薬 乾燥肌治療薬 ヒルマイルド ローション 30g【メール便発送/3個�1000円(税込/送料別)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可乾燥肌治療薬/ヒルマイルドローション/ヘパリン類似物質/健栄製薬 手指の荒れ、ひじ・�【朝の目覚めショップ】
 【お買得クーポン対象】【送料無料】【第3類医薬品】サカムケア 10g 液体絆創膏 絆創�1000円(税込/送料別)カード利用可・海外配送可能・翌日配送不可痛い傷口をカバーして守る 速乾液体絆創膏【バラエティストアFukuko】
【お買得クーポン対象】【送料無料】【第3類医薬品】サカムケア 10g 液体絆創膏 絆創�1000円(税込/送料別)カード利用可・海外配送可能・翌日配送不可痛い傷口をカバーして守る 速乾液体絆創膏【バラエティストアFukuko】
 【指定医薬部外品】ユースキン 80gチューブ1000円(税込/送料別)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可★2999円以上で送料無料!北海道、沖縄は除く★ひび、あかぎれ、しもやけを治す、黄色�【湖畔の薬屋】
【指定医薬部外品】ユースキン 80gチューブ1000円(税込/送料別)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可★2999円以上で送料無料!北海道、沖縄は除く★ひび、あかぎれ、しもやけを治す、黄色�【湖畔の薬屋】
 【第3類医薬品】■ポスト投函■コロスキン 11ml1000円(税込/送料込)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可【送料無料】/液体絆創膏/水絆創膏/水ばんそうこう/あかぎれ/ささくれ/さかむけ/ひび【ドラッグストアザグザグ通販】
【第3類医薬品】■ポスト投函■コロスキン 11ml1000円(税込/送料込)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可【送料無料】/液体絆創膏/水絆創膏/水ばんそうこう/あかぎれ/ささくれ/さかむけ/ひび【ドラッグストアザグザグ通販】
 【第3類医薬品】【2個セット】ジャパンメディック メルフィーナひび・あかぎれクリーム1000円(税込/送料込)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可血行を促進するビタミンEなど6種類の有効成分が配合【花x花ドラッグ楽天市場店】
【第3類医薬品】【2個セット】ジャパンメディック メルフィーナひび・あかぎれクリーム1000円(税込/送料込)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可血行を促進するビタミンEなど6種類の有効成分が配合【花x花ドラッグ楽天市場店】
 【第2類医薬品】リレイジュHPゲル「エルモディアHPの代替品」 20g しもやけ あかぎれ 傷 �1000円(税込/送料込)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可本品はゆうパケット発送で全国どこでも送料無料!(北海道・沖縄・離島含む)【福薬本舗】
【第2類医薬品】リレイジュHPゲル「エルモディアHPの代替品」 20g しもやけ あかぎれ 傷 �1000円(税込/送料込)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可本品はゆうパケット発送で全国どこでも送料無料!(北海道・沖縄・離島含む)【福薬本舗】
1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 |53 |54 |55 |56 |57 |58 |59 |60 |61 |62 |63 |64 |65 |66 |67 |68 |69 |70 |71 |72 |73 |74 |75 |76 |77 |78 |79 |80 |81 |82 |83 |84 |85 |86 |87 |88 |89 |90 |91 |92 |93 |94 |95 |96 |97 |98 |99 |100 |
 雪が降っても通行できるように、町家の庇などを張り出して、下を通路にしたもの。その構造が、雁の編隊飛行の形に似ていることから「雁木」の名がついた。船着場の階段状の構造物や、雁が編隊飛行しているように見える階段も「雁木」というが、それとは異なる。
雪が降っても通行できるように、町家の庇などを張り出して、下を通路にしたもの。その構造が、雁の編隊飛行の形に似ていることから「雁木」の名がついた。船着場の階段状の構造物や、雁が編隊飛行しているように見える階段も「雁木」というが、それとは異なる。
青森県では小見世(こみせ)、山形県では小間屋(こまや)、鳥取県では仮屋(かりや)などと呼ばれ、雪が多い日本海側の町で見られたが、現在では新潟県と青森県黒石市に残るのみだという。新潟県東蒲原郡阿賀町津川には「雁木発祥の地」の碑がある。青森県黒石市は、まちづくりの一環として保存維持を進めている。