晩冬の季語 雪
吹雪(ふぶき)・雪しまき(ゆきしまき)・しまき・深雪(しんせつ・みゆき)・六花(ろっか・りっか・りくか)
 雪の結晶は、六角形を基本とすることから「六花」とも言い、様々な形状がある。温度が比較的高いと、平らな六角形の「角板」。温度が低くて湿度が低いと、柱状の六角形の「角柱」。温度が低くて湿度が高いと「針」となる。「初雪」は初冬の季語、「淡雪」「牡丹雪」は春の季語となる。
雪の結晶は、六角形を基本とすることから「六花」とも言い、様々な形状がある。温度が比較的高いと、平らな六角形の「角板」。温度が低くて湿度が低いと、柱状の六角形の「角柱」。温度が低くて湿度が高いと「針」となる。「初雪」は初冬の季語、「淡雪」「牡丹雪」は春の季語となる。
古くから、雪を見て豊穣を占い、大雪は豊作になると言われてきた。このことから、雪は神聖なものとしてとらえられ、物忌みを意味する「斎潔(ゆきよし)」に雪の語源があるといわれる。万葉集には、 山部赤人の有名な和歌
田子の浦ゆうち出でて見れば真白にぞ富士の高嶺に雪は降りける
など、155首の歌を載せる。
「しまき」は「風巻」と書き、風が激しく吹き荒れることをいうが、特に粉雪が強風にあおられる様子を指す。

 冬の空模様は、太平洋側と日本海側では大きく異なる。乾燥した日が続く太平洋側は晴天が多く、日本海側は雪になることが多い。
冬の空模様は、太平洋側と日本海側では大きく異なる。乾燥した日が続く太平洋側は晴天が多く、日本海側は雪になることが多い。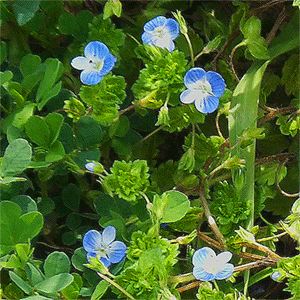 オオバコ科クワガタソウ属。3月から5月、淡いピンク色をした小花をつける。現在は、明治初年に入ってきたと見られる外来種のオオイヌノフグリが優勢で、イヌノフグリは絶滅危惧II類に指定されている。
オオバコ科クワガタソウ属。3月から5月、淡いピンク色をした小花をつける。現在は、明治初年に入ってきたと見られる外来種のオオイヌノフグリが優勢で、イヌノフグリは絶滅危惧II類に指定されている。 太陽暦では12月から2月まで、陰暦では10月から12月までを冬という。二十四節気では、立冬から立春の前日まで。語源は「冷ゆ(ひゆ)」にあるとする説が有力。
太陽暦では12月から2月まで、陰暦では10月から12月までを冬という。二十四節気では、立冬から立春の前日まで。語源は「冷ゆ(ひゆ)」にあるとする説が有力。
 花がすっかり散って、若葉となったころの桜。蕊が落ちて新緑に覆われるまでの桜の木を指す。
花がすっかり散って、若葉となったころの桜。蕊が落ちて新緑に覆われるまでの桜の木を指す。 イネ科ススキ属の植物。「茅(かや)」と呼ばれ、茅葺屋根の材料となる。万葉集には44首歌われていると言われ、「すすき」「をばな」「草(かや)」「み草」として出てくる。「すすき」として歌われる場合、しばしば「ハダススキ」として現れるが、この「ハダ」は「旗」のことだと言われ、「穂に出ず」の枕詞となる。
イネ科ススキ属の植物。「茅(かや)」と呼ばれ、茅葺屋根の材料となる。万葉集には44首歌われていると言われ、「すすき」「をばな」「草(かや)」「み草」として出てくる。「すすき」として歌われる場合、しばしば「ハダススキ」として現れるが、この「ハダ」は「旗」のことだと言われ、「穂に出ず」の枕詞となる。 エドヒガンの枝垂れ品種で、ソメイヨシノより1週間ほど早く咲く。京都府の府花。
エドヒガンの枝垂れ品種で、ソメイヨシノより1週間ほど早く咲く。京都府の府花。 その年に初めて咲いた桜、あるいは、咲いて間もない桜をいう。「初花」とも呼び、18歳くらいの女性のことをも指す。
その年に初めて咲いた桜、あるいは、咲いて間もない桜をいう。「初花」とも呼び、18歳くらいの女性のことをも指す。












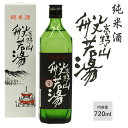

 ヤマザクラとマメザクラを交配したフユザクラは、11月から1月頃に花を咲かす。緋寒桜とも呼ばれるカンヒザクラは、これとは別種で、1月から3月頃に花を咲かせる。
ヤマザクラとマメザクラを交配したフユザクラは、11月から1月頃に花を咲かす。緋寒桜とも呼ばれるカンヒザクラは、これとは別種で、1月から3月頃に花を咲かせる。