三冬の季語 狸
 哺乳綱食肉目イヌ科タヌキ属タヌキ。極東にのみ生息していたが、毛皮目的で旧ソビエト連邦に持ち込まれ、それがヨーロッパなどに広がり、生態系を乱すとして問題になっている。
哺乳綱食肉目イヌ科タヌキ属タヌキ。極東にのみ生息していたが、毛皮目的で旧ソビエト連邦に持ち込まれ、それがヨーロッパなどに広がり、生態系を乱すとして問題になっている。
夜行性で、雑食。主に湿地や森林で生活するが、都市部で見られることもある。複数の個体が糞をする場所を「ため糞(ためふん)」と呼ぶ。個体同士の情報交換を行っていると考えられている。
積雪の多い地方を除き、狸に冬眠の習性はなく、冬場の個体は脂肪を蓄え、毛も長くなるため、丸々としている。冬場の狩猟対象となるために、冬の季語となっている。
狸は驚くと擬死状態になるため、「たぬき寝入り」という慣用句が生まれた。また、悪賢い者同士のたとえに「狐と狸」、当てにならないことを計算に組み込む「とらぬ狸の皮算用」などの言葉も生まれている。
ちなみに「たぬき」の語源は、「たぬき寝入り」を「魂抜き(たまぬき)」と見たことによるものとの説がある。

 哺乳綱食肉目クマ科に属する動物の総称がクマであるが、これにはジャイアントパンダも含め、8種が属する。その内、日本に生息するのはツキノワグマとヒグマ(エゾヒグマ)であり、ツキノワグマは本州と四国に、ヒグマは北海道に生息する。最大のものは白熊と呼ばれるホッキョクグマで、日本では動物園で観察される。
哺乳綱食肉目クマ科に属する動物の総称がクマであるが、これにはジャイアントパンダも含め、8種が属する。その内、日本に生息するのはツキノワグマとヒグマ(エゾヒグマ)であり、ツキノワグマは本州と四国に、ヒグマは北海道に生息する。最大のものは白熊と呼ばれるホッキョクグマで、日本では動物園で観察される。 漢字では「海鼠腸」と書くとおり、
漢字では「海鼠腸」と書くとおり、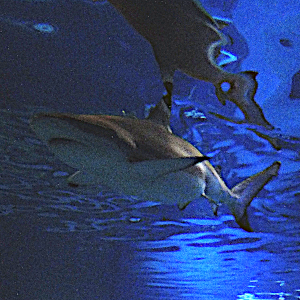 軟骨魚綱板鰓亜綱に属する魚類のうち、鰓裂が体の側面にあるもの。鰓裂が下面にあるものはエイである。世界では553種、日本近海では約130種が確認されている。アオザメ(青鮫)・シュモクザメ(撞木鮫)などの、人喰鮫と呼ばれる獰猛な種類もある。また、大きなものは鱶(ふか)とも呼ばれ、古代には鰐(わに)とも呼ばれていた。
軟骨魚綱板鰓亜綱に属する魚類のうち、鰓裂が体の側面にあるもの。鰓裂が下面にあるものはエイである。世界では553種、日本近海では約130種が確認されている。アオザメ(青鮫)・シュモクザメ(撞木鮫)などの、人喰鮫と呼ばれる獰猛な種類もある。また、大きなものは鱶(ふか)とも呼ばれ、古代には鰐(わに)とも呼ばれていた。 北海道や東北地方で作られる、
北海道や東北地方で作られる、
 「鱩」「燭魚」とも書く。スズキ目ハタハタ科の魚で、約20センチメートル。主に日本海側の深海で生活し、産卵に寄ってくる冬場に漁獲量が多くなる。この頃は、雷がよく鳴るので、雷魚の別名もある。
「鱩」「燭魚」とも書く。スズキ目ハタハタ科の魚で、約20センチメートル。主に日本海側の深海で生活し、産卵に寄ってくる冬場に漁獲量が多くなる。この頃は、雷がよく鳴るので、雷魚の別名もある。 つむじ風に乗って現われて人を切りつけるという妖怪。雪国を中心に、全国に伝承があり、鎌のような爪を持ったイタチの姿で描かれることが多い。つむじ風自体を「鎌鼬」と呼ぶこともある。
つむじ風に乗って現われて人を切りつけるという妖怪。雪国を中心に、全国に伝承があり、鎌のような爪を持ったイタチの姿で描かれることが多い。つむじ風自体を「鎌鼬」と呼ぶこともある。 鯨突とは、鯨を銛で突いて捕えることである。江戸時代には「鯨組」が組織されて、全国で年間数百頭もの鯨が捕獲されていた。
鯨突とは、鯨を銛で突いて捕えることである。江戸時代には「鯨組」が組織されて、全国で年間数百頭もの鯨が捕獲されていた。 哺乳類クジラ目は、歯を持つハクジラと、歯を持たずヒゲを持つヒゲクジラに大別される。ハクジラ類には、マッコウクジラやイルカが含まれ、ヒゲクジラ類にはセミクジラやナガスクジラ、ザトウクジラが含まれる。日本周辺には、上記4種を含む約40種類が生息しており、太平洋側のホエールウォッチングでは主にマッコウクジラやザトウクジラが観察できる。
哺乳類クジラ目は、歯を持つハクジラと、歯を持たずヒゲを持つヒゲクジラに大別される。ハクジラ類には、マッコウクジラやイルカが含まれ、ヒゲクジラ類にはセミクジラやナガスクジラ、ザトウクジラが含まれる。日本周辺には、上記4種を含む約40種類が生息しており、太平洋側のホエールウォッチングでは主にマッコウクジラやザトウクジラが観察できる。