三冬の季語 梟
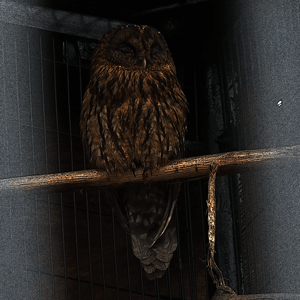 「森の物知り博士」「森の哲学者」の呼称でも知られる猛禽類の一種で、フクロウ目フクロウ科フクロウ属に分類される。夜行性で、待ち伏せて狩りをする。
「森の物知り博士」「森の哲学者」の呼称でも知られる猛禽類の一種で、フクロウ目フクロウ科フクロウ属に分類される。夜行性で、待ち伏せて狩りをする。
日本に生息するフクロウ科の鳥には、フクロウの他に、シマフクロウ、シロフクロウ、ワシミミズク、トラフズク、コノハズク、コミミズク、アオバズクなどがある。フクロウは留鳥であるが、コノハズク(木葉木菟)・アオバズク(青葉木菟)は渡り鳥であり、夏の季語となる。
飛翔時には羽音を立てることがないため、「森の忍者」と呼ばれることも。その風切羽の構造は、新幹線のパンタグラフなどに応用され、消音に役立てられている。
鳴き声は、「五郎助奉公」「ボロ着て奉公」と聞きなされる。
現在では「不苦労」「福老」の当字で、幸せを呼ぶ鳥と見なされているが、古代中国や西欧文化が伝わる近代までの日本では、母を食う鳥として「不孝鳥(不幸鳥)」とされた。
日本書紀(景行紀)には、敵対するものとして川上梟帥(かわかみのたける)などに「梟」の文字が当てられる。川上梟帥を討った日本童男は、日本武(やまとたける)の名が譲られた。ここに見るに、古代日本では、「梟」に、強くて悪いもののイメージがあったと考えられる。因みに古事記では、「タケル」に「建」の字が充てられる。
梟を詠んだ和歌として、夫木和歌抄に西行上人の
山ふかみけぢかき鳥の音はせで 物おそろしきふくろふのこゑ
が載る。
西欧でフクロウに対するイメージが良いのは、ギリシャ神話で、女神アテナの従者として描かれているためか。
長野には、「梟の染め物屋」という昔話があり、カラスを黒く染めたところ激怒され、カラスに追いかけまわされるようになったという。それ以降、森の奥で「糊付けほっほ」と鳴きながら営業をしているという。
フクロウの語源は、毛が膨れた鳥にあるとも、鳴き声からきたとも言われる。「梟」の文字が「木」の上に「鳥」を置いた形なのは、むかし、木の上に梟の死骸を置いて鳥除けにしたからとの説がある。「梟首」とはさらし首のことである。
【梟の俳句】
梟に奪はれさうな灯が一つ 藤本和子

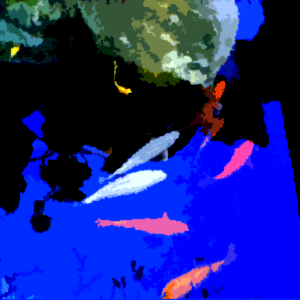 澄み渡った秋空を映し込む水面は、美しい。実際には、台風などで秋の水辺は濁ることが多いが、嵐は、夏場に腐敗した有機物を拡散し、流し去る役目も果たす。
澄み渡った秋空を映し込む水面は、美しい。実際には、台風などで秋の水辺は濁ることが多いが、嵐は、夏場に腐敗した有機物を拡散し、流し去る役目も果たす。 亀には声帯がないため、鳴くことはない。ただし、擦過音と呼ばれる呼吸音に近いものが、「クー」などと聞こえることがある。また、「シュー」と威嚇音を立てることも知られている。
亀には声帯がないため、鳴くことはない。ただし、擦過音と呼ばれる呼吸音に近いものが、「クー」などと聞こえることがある。また、「シュー」と威嚇音を立てることも知られている。 ヒガンバナ科。南ヨーロッパ原産。江戸末期に渡来。
ヒガンバナ科。南ヨーロッパ原産。江戸末期に渡来。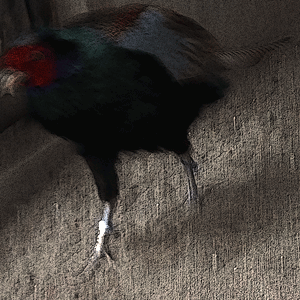 キジ目キジ科キジ属に分類される鳥。日本固有の留鳥で、性質は勇敢、「焼け野のきぎす」の諺もあるように母性愛が強いため、戦後すぐに日本の国鳥に指定された。
キジ目キジ科キジ属に分類される鳥。日本固有の留鳥で、性質は勇敢、「焼け野のきぎす」の諺もあるように母性愛が強いため、戦後すぐに日本の国鳥に指定された。 燕は、スズメ目ツバメ科ツバメ属に分類される。3月頃から南方より飛来し、4月頃に巣作りを始める。
燕は、スズメ目ツバメ科ツバメ属に分類される。3月頃から南方より飛来し、4月頃に巣作りを始める。 維管束のない植物・蘚苔類(蘚類・苔類)のことを一般にコケと呼ぶが、鑑賞用に用いられるのは苔類。その苔類にもいろいろな種類があり、苔寺などでよく見られるのは、スギゴケ、ヒノキゴケ、シラガゴケ。
維管束のない植物・蘚苔類(蘚類・苔類)のことを一般にコケと呼ぶが、鑑賞用に用いられるのは苔類。その苔類にもいろいろな種類があり、苔寺などでよく見られるのは、スギゴケ、ヒノキゴケ、シラガゴケ。 昆虫綱ハチ目(膜翅目)に分類される昆虫の内、アリ以外のものをハチという。秋の蜂、
昆虫綱ハチ目(膜翅目)に分類される昆虫の内、アリ以外のものをハチという。秋の蜂、 シダ植物門トクサ綱トクサ目トクサ科トクサ属の植物にスギナがあり、その胞子茎をツクシという。地下茎で繁茂し、根が深いことから「地獄草」の別名もある。ツクシは胞子を放出すると枯れ、緑色のスギナが繁茂する。スギナの名は、その栄養茎が杉に似ていることに因る。
シダ植物門トクサ綱トクサ目トクサ科トクサ属の植物にスギナがあり、その胞子茎をツクシという。地下茎で繁茂し、根が深いことから「地獄草」の別名もある。ツクシは胞子を放出すると枯れ、緑色のスギナが繁茂する。スギナの名は、その栄養茎が杉に似ていることに因る。 モクレン目モクレン科モクレン属の落葉高木で、「田打ち桜」とも呼ばれる。日本原産。3月から5月に白い花をつける。果実の形状が握りこぶしのように凸凹していることが、コブシの名前の由来である。
モクレン目モクレン科モクレン属の落葉高木で、「田打ち桜」とも呼ばれる。日本原産。3月から5月に白い花をつける。果実の形状が握りこぶしのように凸凹していることが、コブシの名前の由来である。