晩冬の季語 節分
豆撒き(まめまき)・鬼の豆(おにのまめ)・柊挿す(ひいらぎさす)
 雑節の一つで、各季節の始まりの日の前日のことであったが、江戸時代以降は立春の前日を指すことが普通になった。この日まで大寒であり、一年で一番寒い日の最後の日となる。
雑節の一つで、各季節の始まりの日の前日のことであったが、江戸時代以降は立春の前日を指すことが普通になった。この日まで大寒であり、一年で一番寒い日の最後の日となる。
2月3日が節分に定められていると認識している者も多いが、常にそうなるとは限らない。
季節の変わり目には邪気(鬼)が生じると考えられており、この日、魔除けのために「鬼は外、福は内」と唱えながら豆をまき、年の数だけ豆を食べる。豆を用いるのは、「魔滅」に通じるからでもある。
文献からは、室町時代に豆撒きの風習があったことは確実であるが、宇多天皇の代(平安時代)に始まったとの説も「壒嚢鈔」に載る。それによると、鞍馬山の奥深くに棲む「藍婆(らんば)」と「揔主(そうず)」という二頭の鬼神の企みを毘沙門天のお告げで暴き、三斛三斗の大豆を鬼の目に投げつけて退散させたとある。
また、節分には柊の枝に鰯の頭を刺した柊鰯を戸口に立てる風習もあるが、これは、聞鼻(かぐはな)という名の鬼を払うための魔除けである。
近年では、恵方を向いて無言で食すると縁起が良いと言われる恵方巻が、節分の名物になっているが、2000年以降に急速に広まったもの。大阪が発祥とも言われているが、起源は明らかではない。
【節分の俳句】
半天は鳩に覆はれ節分会 鷹羽狩行

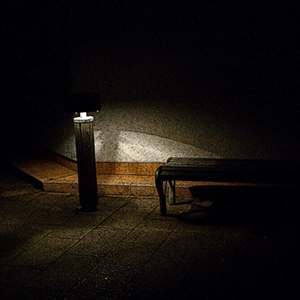 冬の夜の寒さは厳しい。現代でこそ暖房設備が整い、室内では快適に過ごすことができるようになったが、かつては、それを如何に遣り過ごすかは生きていく上での課題であった。古い句に、時代の変遷を見るのも面白い。
冬の夜の寒さは厳しい。現代でこそ暖房設備が整い、室内では快適に過ごすことができるようになったが、かつては、それを如何に遣り過ごすかは生きていく上での課題であった。古い句に、時代の変遷を見るのも面白い。 中国では、草が腐って蛍になると言われており、腐草(くちくさ)とはホタルのことである。晋の政治家・車胤は、生家が貧しく、灯火の油が買えなかったので、蛍の光で書物を読んだ。このことは、雪明りで勉強した孫康とともに「蛍雪の功」の故事となり、日本では「蛍の光」の唱歌になった。
中国では、草が腐って蛍になると言われており、腐草(くちくさ)とはホタルのことである。晋の政治家・車胤は、生家が貧しく、灯火の油が買えなかったので、蛍の光で書物を読んだ。このことは、雪明りで勉強した孫康とともに「蛍雪の功」の故事となり、日本では「蛍の光」の唱歌になった。 寒さには強い鴉であるが、冬場には集団で森などにねぐらを作る習性があるために、群れで見かけることが多くなる。鴉が集団で帰る夕景が見られるのも、秋から冬にかけてである。
寒さには強い鴉であるが、冬場には集団で森などにねぐらを作る習性があるために、群れで見かけることが多くなる。鴉が集団で帰る夕景が見られるのも、秋から冬にかけてである。















 秋の冷気は寂しさを増長し、身に深くしみてくる。後拾遺和歌集に、よみ人しらずの歌が載る。
秋の冷気は寂しさを増長し、身に深くしみてくる。後拾遺和歌集に、よみ人しらずの歌が載る。 冬の日の夕方は日没も早いが、冬至が一番日没時間が早いのではない。12月上旬から中旬にかけて、東京では16時30分頃に日が沈む。大阪ではそれより約20分遅く、福岡では東京より約40分遅い。
冬の日の夕方は日没も早いが、冬至が一番日没時間が早いのではない。12月上旬から中旬にかけて、東京では16時30分頃に日が沈む。大阪ではそれより約20分遅く、福岡では東京より約40分遅い。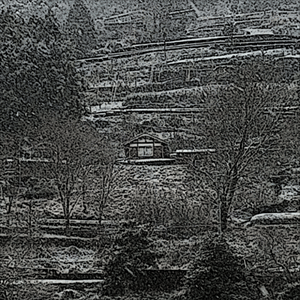 主に、どっしりとした感じの洋風家屋について言う。
主に、どっしりとした感じの洋風家屋について言う。 スズメ目スズメ科スズメ属のスズメは、ヒトの生活に隣接するように生息しており、「ちゅんちゅん」という鳴き声は、都会から農村まで聞くことが出来る。「舌切り雀」などの童話にも登場し、稲の害鳥として認識されるが、雑食性であり稲の害虫をも食す。
スズメ目スズメ科スズメ属のスズメは、ヒトの生活に隣接するように生息しており、「ちゅんちゅん」という鳴き声は、都会から農村まで聞くことが出来る。「舌切り雀」などの童話にも登場し、稲の害鳥として認識されるが、雑食性であり稲の害虫をも食す。 散り落ちた椿の花。
散り落ちた椿の花。 ツバキ科ツバキ属の常緑樹で、冬から春に花をつける。普通に見られるヤブツバキは、日本原産。同じツバキ属の山茶花は花びらがひとつひとつ散っていくのに対し、椿は花ごと落花するため、病床では厭われる。首が落ちるような落花の様を武士が嫌っていたというのは俗説で、武士は、その潔さを愛でた。江戸時代には特に二代将軍徳川秀忠が好んだことから、ユキツバキなどと掛け合わせる品種改良が盛んに行われ、花だけでなく葉や枝も観賞対象とした。
ツバキ科ツバキ属の常緑樹で、冬から春に花をつける。普通に見られるヤブツバキは、日本原産。同じツバキ属の山茶花は花びらがひとつひとつ散っていくのに対し、椿は花ごと落花するため、病床では厭われる。首が落ちるような落花の様を武士が嫌っていたというのは俗説で、武士は、その潔さを愛でた。江戸時代には特に二代将軍徳川秀忠が好んだことから、ユキツバキなどと掛け合わせる品種改良が盛んに行われ、花だけでなく葉や枝も観賞対象とした。