初夏の季語 初鰹
 フィリピン沖から三陸海岸沖辺りを周遊する鰹は、5月頃に黒潮に乗って房総沖に達する。75日寿命が延びるとし、「初物七十五日」と言って初物を食べる習慣があった江戸時代においても、初鰹は特に珍重された。
フィリピン沖から三陸海岸沖辺りを周遊する鰹は、5月頃に黒潮に乗って房総沖に達する。75日寿命が延びるとし、「初物七十五日」と言って初物を食べる習慣があった江戸時代においても、初鰹は特に珍重された。
「女房子供を質に出してでも食え」とも言われ、高値を厭わない姿勢が「粋」とされた。「恥ずかしさ医者に鰹の値が知れる」という川柳もあるが、これは、安い鰹を食べて食中毒になることを揶揄するもの。
現在では鰹と言えば土佐だが、かつては鎌倉沖のものが珍重され、有名な「目には青葉~」の句にも、「かまくらにて」の前書がある。産地が西にずれたことで、初鰹の季節もひと月ほど早くなり、現在では4月頃には食卓に並んでいる。
徒然草119段に鰹についての言及があり、鎌倉の年寄に「この魚は自分たちが若かった頃は下等な魚だったのに、世も末になったので上流階級までがもてはやしている」と言わしめている。
▶ 関連季語 鰹(夏)
【初鰹の俳句】
目には青葉山ほととぎす初がつお 山口素堂

 二十四節気の第7で5月5日頃。この日から立秋の前日までが夏。立夏の期間の七十二候は、蛙が鳴き始めるとされる「蛙始鳴」、ミミズが地上に這出るとされる「蚯蚓出」、筍が生えて来るとされる「竹笋生」。
二十四節気の第7で5月5日頃。この日から立秋の前日までが夏。立夏の期間の七十二候は、蛙が鳴き始めるとされる「蛙始鳴」、ミミズが地上に這出るとされる「蚯蚓出」、筍が生えて来るとされる「竹笋生」。 スズメ目ヒヨドリ科ヒヨドリ属に分類される漂鳥であるが、留鳥として年中観測されるものもある。特に東京では、近年の温暖化の影響か、一年中生息している。雑食ではあるが、果実や花の蜜を啜っている様子がよく観察される。
スズメ目ヒヨドリ科ヒヨドリ属に分類される漂鳥であるが、留鳥として年中観測されるものもある。特に東京では、近年の温暖化の影響か、一年中生息している。雑食ではあるが、果実や花の蜜を啜っている様子がよく観察される。 春は、異動などで慌ただしい季節ではあるがまた、冬の厳しさも去り、穏やかでのんびりとした気持ちにもなる。「
春は、異動などで慌ただしい季節ではあるがまた、冬の厳しさも去り、穏やかでのんびりとした気持ちにもなる。「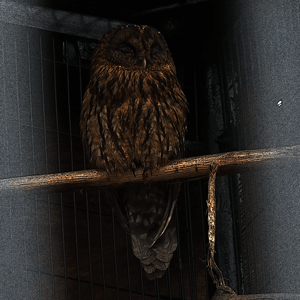 「森の物知り博士」「森の哲学者」の呼称でも知られる猛禽類の一種で、フクロウ目フクロウ科フクロウ属に分類される。夜行性で、待ち伏せて狩りをする。
「森の物知り博士」「森の哲学者」の呼称でも知られる猛禽類の一種で、フクロウ目フクロウ科フクロウ属に分類される。夜行性で、待ち伏せて狩りをする。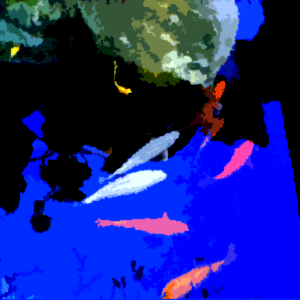 澄み渡った秋空を映し込む水面は、美しい。実際には、台風などで秋の水辺は濁ることが多いが、嵐は、夏場に腐敗した有機物を拡散し、流し去る役目も果たす。
澄み渡った秋空を映し込む水面は、美しい。実際には、台風などで秋の水辺は濁ることが多いが、嵐は、夏場に腐敗した有機物を拡散し、流し去る役目も果たす。 亀には声帯がないため、鳴くことはない。ただし、擦過音と呼ばれる呼吸音に近いものが、「クー」などと聞こえることがある。また、「シュー」と威嚇音を立てることも知られている。
亀には声帯がないため、鳴くことはない。ただし、擦過音と呼ばれる呼吸音に近いものが、「クー」などと聞こえることがある。また、「シュー」と威嚇音を立てることも知られている。 ヒガンバナ科。南ヨーロッパ原産。江戸末期に渡来。
ヒガンバナ科。南ヨーロッパ原産。江戸末期に渡来。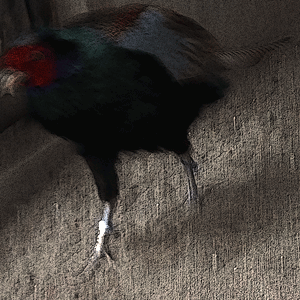 キジ目キジ科キジ属に分類される鳥。日本固有の留鳥で、性質は勇敢、「焼け野のきぎす」の諺もあるように母性愛が強いため、戦後すぐに日本の国鳥に指定された。
キジ目キジ科キジ属に分類される鳥。日本固有の留鳥で、性質は勇敢、「焼け野のきぎす」の諺もあるように母性愛が強いため、戦後すぐに日本の国鳥に指定された。 燕は、スズメ目ツバメ科ツバメ属に分類される。3月頃から南方より飛来し、4月頃に巣作りを始める。
燕は、スズメ目ツバメ科ツバメ属に分類される。3月頃から南方より飛来し、4月頃に巣作りを始める。