晩秋の季語 新酒
 かつては収穫された新米を使って造った酒を新酒とし、酒造は10月1日を起点としていたため、10月1日は「日本酒の日」となっている。ただ、江戸時代より寒造りが中心となり、新酒は主に冬場のものとなった。現在でも秋の日本酒は人気であるが、そのほとんどは、春にできた日本酒を貯蔵して出す「ひやおろし」である。
かつては収穫された新米を使って造った酒を新酒とし、酒造は10月1日を起点としていたため、10月1日は「日本酒の日」となっている。ただ、江戸時代より寒造りが中心となり、新酒は主に冬場のものとなった。現在でも秋の日本酒は人気であるが、そのほとんどは、春にできた日本酒を貯蔵して出す「ひやおろし」である。
なお芋焼酎は、現在でも収穫してすぐに製造にとりかかるため、秋が新酒のシーズンであり、11月1日は「本格焼酎の日」となっている。同じくワインも、秋が新酒のシーズンであり、地方により解禁日が異なる。日本で最も有名なボジョレー・ヌーヴォーの解禁日は、11月の第3木曜日となっている。
造り酒屋の軒先には、新酒が出来上がったことを知らせるために杉球を吊るすことがあるが、その色合いで酒の熟成具合を知らせるという役割もある。一休和尚は、
極楽は何処の里と思ひしに 杉葉立てたる又六が門
と、一休和尚のいた大徳寺の門前の杉玉を吊るした酒屋にも極楽があると歌っている。
日本人は太古から酒に親しんでいたと見られ、古事記には「ヤマタノオロチ」の項に初出。スサノオが、ヤマタノオロチを退治するために八塩折酒(やしおりのさけ)を用いる。
酒の語源は、神の召物を指す「清けし(さやけし)食(け)」にあると言われる。

 季語の「木の葉」は、散ったり散り残ったりしている樹木の葉のことで、冬の季語となる。取るに足らないことも「木の葉」になぞらえて表現する。つれづれ草百五十五段に、「木の葉の落つるも、先づ落ちて芽ぐむにはあらず。下より萌しつわるに耐えずして落つるなり」と、木の葉散ることは春の兆しとの見方がある。
季語の「木の葉」は、散ったり散り残ったりしている樹木の葉のことで、冬の季語となる。取るに足らないことも「木の葉」になぞらえて表現する。つれづれ草百五十五段に、「木の葉の落つるも、先づ落ちて芽ぐむにはあらず。下より萌しつわるに耐えずして落つるなり」と、木の葉散ることは春の兆しとの見方がある。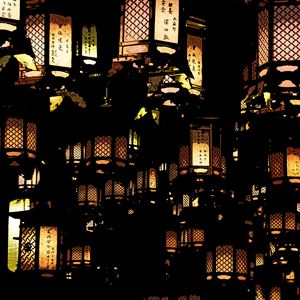 除夜とは除日(古いものを除き去る一年の一番最後の日)の夜のこと。主な寺院では、大晦日の深夜に107回、新年明けてすぐに1回、合わせて108回梵鐘を撞く。その数は、煩悩の数と言われている。
除夜とは除日(古いものを除き去る一年の一番最後の日)の夜のこと。主な寺院では、大晦日の深夜に107回、新年明けてすぐに1回、合わせて108回梵鐘を撞く。その数は、煩悩の数と言われている。 本来は旧暦1月の別名。現在では、「三が日」または「松の内」という意味で使用することが多い。松の内は小正月の15日や20日までとすることもあるが、通常は7日まで。
本来は旧暦1月の別名。現在では、「三が日」または「松の内」という意味で使用することが多い。松の内は小正月の15日や20日までとすることもあるが、通常は7日まで。 新年になって去年を思うこと。同じ銘の「抹茶」がある。
新年になって去年を思うこと。同じ銘の「抹茶」がある。 木綿や麻を使った生地が多い夏衣。
木綿や麻を使った生地が多い夏衣。 元旦の朝に、初めて酌んだ若水で心身を洗い清める。手水を「ちょうず」と読むのは「てみず」の転訛。手水は、禊の簡略作法であり、本来は河川に入り身を清める。イザナギノミコトが黄泉の国から帰還した折、日向の橘の小門の阿波岐原で身禊をしたという神話に基づく。
元旦の朝に、初めて酌んだ若水で心身を洗い清める。手水を「ちょうず」と読むのは「てみず」の転訛。手水は、禊の簡略作法であり、本来は河川に入り身を清める。イザナギノミコトが黄泉の国から帰還した折、日向の橘の小門の阿波岐原で身禊をしたという神話に基づく。 柚子を砂糖で煮て、熱湯で薄めた飲み物も「柚子湯」と言うが、俳句では主に、冬至に柚子を浮かべた風呂のことを言う。
柚子を砂糖で煮て、熱湯で薄めた飲み物も「柚子湯」と言うが、俳句では主に、冬至に柚子を浮かべた風呂のことを言う。 マメ科ハギ属。秋の七草のひとつで、7月から10月に紫や白などの花をつける。痩せた土地でも良く育つため、緑化資材としても用いられる。中秋の名月に、ススキ・月見団子と共に供える。
マメ科ハギ属。秋の七草のひとつで、7月から10月に紫や白などの花をつける。痩せた土地でも良く育つため、緑化資材としても用いられる。中秋の名月に、ススキ・月見団子と共に供える。 樹木の枝が雪の付着で折れないように、縄で枝を支える。リンゴの実の重さから枝を守るために行ったことを起源とし、明治の終わりに導入された柱の先から放射状に縄を張る「りんご吊り(芯立て)」が一般的。ほかに、幹から縄を張り枝を支える「幹吊り」などがある。金沢市の兼六園が有名で、11月1日から作業を始め、3月まで見られる。東京でも、甘泉園公園や六義園などで見られる。
樹木の枝が雪の付着で折れないように、縄で枝を支える。リンゴの実の重さから枝を守るために行ったことを起源とし、明治の終わりに導入された柱の先から放射状に縄を張る「りんご吊り(芯立て)」が一般的。ほかに、幹から縄を張り枝を支える「幹吊り」などがある。金沢市の兼六園が有名で、11月1日から作業を始め、3月まで見られる。東京でも、甘泉園公園や六義園などで見られる。