三夏の季語 日傘
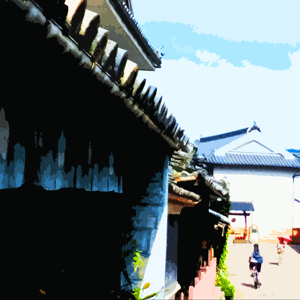 さしかけるタイプの傘は、西暦552年に百済から初めて渡来した(日本書紀)。雨傘としての用途ではなく、他人がさしかけるタイプの日傘であり、権力の象徴として用いられたと考えられている。
さしかけるタイプの傘は、西暦552年に百済から初めて渡来した(日本書紀)。雨傘としての用途ではなく、他人がさしかけるタイプの日傘であり、権力の象徴として用いられたと考えられている。
現代では、日傘を用いる習慣があるのは、ほぼ日本に限られている。パラソル(=日傘)の言葉があるフランスでは、19世紀ころに流行はあったが、現在では廃れた。古代には、権力の象徴として、世界各地で使用されている。
日傘の効用は、紫外線を遮ることと、暑さを和らげること。ビーチパラソルも日傘の一種で、晩夏の季語となるが、こちらは大型で地面に突き刺して用いる。
傘と笠は、語源が同じで、風雨などを遮るものの意とされている。「かざす(髪挿す)」の転訛か。

 おでんは御田と表記する。元々は、豆腐料理である「田楽」を意味する女房言葉で、田楽は室町時代にはじまる料理である。江戸時代に入って、こんにゃくの田楽が登場し、オデンの略称で呼ばれるようになったとも言われる。
おでんは御田と表記する。元々は、豆腐料理である「田楽」を意味する女房言葉で、田楽は室町時代にはじまる料理である。江戸時代に入って、こんにゃくの田楽が登場し、オデンの略称で呼ばれるようになったとも言われる。 秋の一日のことであり、秋の太陽のことでもある。秋も深まるにつれ、暮れやすく、慌ただしく感じる。
秋の一日のことであり、秋の太陽のことでもある。秋も深まるにつれ、暮れやすく、慌ただしく感じる。 冬に見られる鳥全般。鷹、鴨、都鳥、鶴、鴛鴦、千鳥、鳰、白鳥などは、そのまま冬の季語となる。寒雀、浮寝鳥、寒鴉、水鳥なども冬の季語。
冬に見られる鳥全般。鷹、鴨、都鳥、鶴、鴛鴦、千鳥、鳰、白鳥などは、そのまま冬の季語となる。寒雀、浮寝鳥、寒鴉、水鳥なども冬の季語。 「
「 鯉は、中央アジア原産。日本の鯉は、史前帰化動物として古くから定着していたと考えられているが、琵琶湖などに棲むノゴイなどは日本列島在来種であるとも言われている。日本書紀景行天皇四年の美濃への御幸の条に、「鯉魚」を使って恋心を成就しようとした話があるが、このことから「鯉」を「コイ」と言うようになったという説もある。同時期に編集された万葉集に「鯉」は出てこない。
鯉は、中央アジア原産。日本の鯉は、史前帰化動物として古くから定着していたと考えられているが、琵琶湖などに棲むノゴイなどは日本列島在来種であるとも言われている。日本書紀景行天皇四年の美濃への御幸の条に、「鯉魚」を使って恋心を成就しようとした話があるが、このことから「鯉」を「コイ」と言うようになったという説もある。同時期に編集された万葉集に「鯉」は出てこない。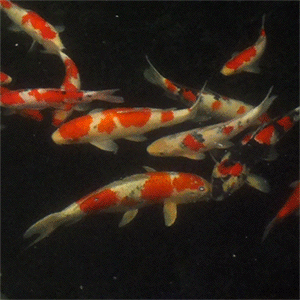 陰暦十月。冬のはじめ。
陰暦十月。冬のはじめ。 中国南部原産のタデ科ソバ属の一年草で、イネ科以外の穀類である。乾燥した冷涼な土地でも栽培が容易で、3カ月ほどで収穫できることから、救荒作物ともなる。播種の時期にもよるが、初秋に小さな白い花をつける。ただし、悪臭を放つ。
中国南部原産のタデ科ソバ属の一年草で、イネ科以外の穀類である。乾燥した冷涼な土地でも栽培が容易で、3カ月ほどで収穫できることから、救荒作物ともなる。播種の時期にもよるが、初秋に小さな白い花をつける。ただし、悪臭を放つ。 夏木立は、暑い夏の日ざしを遮る役目も果たす。「
夏木立は、暑い夏の日ざしを遮る役目も果たす。「 ヒルガオ科サツマイモ属の一年性植物。ヒマラヤ原産とも言われるがよく分かっていない。日本へは、奈良時代の遣唐使が、薬として持ち帰ったと言われており、その名が万葉集にも5首出てくる。ただし、万葉集におけるアサガオは、よみびと知らずで知られる
ヒルガオ科サツマイモ属の一年性植物。ヒマラヤ原産とも言われるがよく分かっていない。日本へは、奈良時代の遣唐使が、薬として持ち帰ったと言われており、その名が万葉集にも5首出てくる。ただし、万葉集におけるアサガオは、よみびと知らずで知られる