三冬の季語 凍る
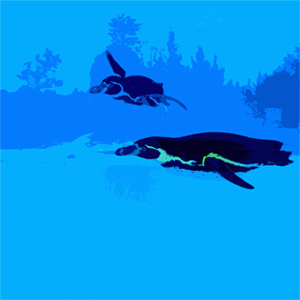 「こおる」が表面的であるのに対して、「しむ(凍む)」は奥まで深くこおってゆく語感をもつ。新古今集に載る藤原家隆の和歌
「こおる」が表面的であるのに対して、「しむ(凍む)」は奥まで深くこおってゆく語感をもつ。新古今集に載る藤原家隆の和歌
志賀の浦や遠ざかりゆく波間より凍りて出づる有り明けの月
は、後拾遺和歌集に載る快覚法師の
小夜ふくるままに汀や凍るらむ遠ざかりゆく志賀の浦波
の本歌取り。
語源に関して「こおる」は、「凝ふ(こふ)」と「和る(おる)」の合成により成立。「こほる」とすれば「毀る」ともなり、壊れることを表す。
ぼうたん・白牡丹(はくぼたん)・緋牡丹(ひぼたん)・牡丹園(ぼたんえん)・深見草(ふかみぐさ)・鎧草(よろいぐさ)
 花王とも呼ばれ、中国では古代よりもっとも親しまれてきた花である。隋の煬帝や、唐の則天武后が愛でたという伝説もある。根の樹皮は、「牡丹皮」として薬になる。日本には、天平時代に中国から入ってきたと見られている。李白は、楊貴妃を「花」として牡丹にたとえている。日本文学では「枕草子」に初出。古くは「ふかみ草」と言い、千載和歌集には賀茂重保の歌が載る。
花王とも呼ばれ、中国では古代よりもっとも親しまれてきた花である。隋の煬帝や、唐の則天武后が愛でたという伝説もある。根の樹皮は、「牡丹皮」として薬になる。日本には、天平時代に中国から入ってきたと見られている。李白は、楊貴妃を「花」として牡丹にたとえている。日本文学では「枕草子」に初出。古くは「ふかみ草」と言い、千載和歌集には賀茂重保の歌が載る。
人しれず思ふこころはふかみぐさ花咲きてこそ色に出でけれ
裏切りから身を滅ぼすことを指す「獅子身中の虫」という仏教用語があるが、牡丹の花の夜露はその薬となると言われ、獅子は牡丹の花から離れられない。それを基に、獅子に牡丹をあしらった芸術作品が数多く存在する。
「ボタン」は、漢語「牡丹」から来ている。接ぎ木で増やされたため「牡(オス)」の植物とみなされ、それに赤を表す「丹」をつけて表現された。つまり「赤い男」である。5月頃に見頃となるため、夏の季語となる。
吹雪(ふぶき)・雪しまき(ゆきしまき)・しまき・深雪(しんせつ・みゆき)・六花(ろっか・りっか・りくか)
 雪の結晶は、六角形を基本とすることから「六花」とも言い、様々な形状がある。温度が比較的高いと、平らな六角形の「角板」。温度が低くて湿度が低いと、柱状の六角形の「角柱」。温度が低くて湿度が高いと「針」となる。「初雪」は初冬の季語、「淡雪」「牡丹雪」は春の季語となる。
雪の結晶は、六角形を基本とすることから「六花」とも言い、様々な形状がある。温度が比較的高いと、平らな六角形の「角板」。温度が低くて湿度が低いと、柱状の六角形の「角柱」。温度が低くて湿度が高いと「針」となる。「初雪」は初冬の季語、「淡雪」「牡丹雪」は春の季語となる。
古くから、雪を見て豊穣を占い、大雪は豊作になると言われてきた。このことから、雪は神聖なものとしてとらえられ、物忌みを意味する「斎潔(ゆきよし)」に雪の語源があるといわれる。万葉集には、 山部赤人の有名な和歌
田子の浦ゆうち出でて見れば真白にぞ富士の高嶺に雪は降りける
など、155首の歌を載せる。
「しまき」は「風巻」と書き、風が激しく吹き荒れることをいうが、特に粉雪が強風にあおられる様子を指す。
いぬのふぐり・ひょうたんぐさ・おおいぬのふぐり
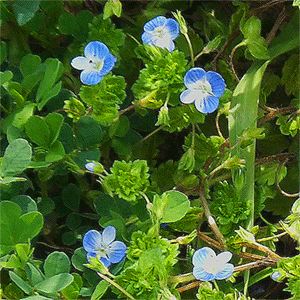 オオバコ科クワガタソウ属。3月から5月、淡いピンク色をした小花をつける。現在は、明治初年に入ってきたと見られる外来種のオオイヌノフグリが優勢で、イヌノフグリは絶滅危惧II類に指定されている。
オオバコ科クワガタソウ属。3月から5月、淡いピンク色をした小花をつける。現在は、明治初年に入ってきたと見られる外来種のオオイヌノフグリが優勢で、イヌノフグリは絶滅危惧II類に指定されている。
イヌノフグリの名前は、果実の形状が雄犬の陰嚢に似ていることに由来するが、オオイヌノフグリの果実は形状を異にする。
冬の日(ふゆのひ)・冬うらら(ふゆうらら)・冬眠(とうみん)・冬籠り(ふゆごもり)・冬籠(ふゆごもり)・冬ざれ(ふゆざれ)・冬ざるる(ふゆざるる)・底冷え(そこびえ)・冷たし(つめたし)・寒し(さむし)・寒さ(さむさ)
 太陽暦では12月から2月まで、陰暦では10月から12月までを冬という。二十四節気では、立冬から立春の前日まで。語源は「冷ゆ(ひゆ)」にあるとする説が有力。
太陽暦では12月から2月まで、陰暦では10月から12月までを冬という。二十四節気では、立冬から立春の前日まで。語源は「冷ゆ(ひゆ)」にあるとする説が有力。
「芭蕉開眼の書」とも呼ばれる「冬の日」は、貞享元年(1684年)刊。「野ざらし紀行」の旅の折、名古屋で成る。
薺咲く(なずなさく)・三味線草(しゃみせんぐさ)・ぺんぺん草(ぺんぺんぐさ)・薺の花(なずなのはな)
 春の七草のひとつ薺は、「薺」だけだと新春の季語。麦栽培の伝来と共に渡来した史前帰化植物と考えられている。平安時代後期、源俊頼の歌に現れたのが初出か。
春の七草のひとつ薺は、「薺」だけだと新春の季語。麦栽培の伝来と共に渡来した史前帰化植物と考えられている。平安時代後期、源俊頼の歌に現れたのが初出か。
君がため夜ごしにつめる七草のなづなの花を見てしのびませ
語源には諸説あるが、夏になると枯れてなくなることから、夏無(なつな)から来たとする説が有力である。生命力の強い植物であることから、「ぺんぺん草が生える」「ぺんぺん草も生えない」は、慣用句として使われる。