晩秋の季語 雁
かりがね・初雁(はつかり)・雁渡る(かりわたる)・雁行(がんこう)
 カモ目カモ科ガン亜科の水鳥の中でも、カモより大きくハクチョウよりも小さい一群をいう。マガン、カリガネ、コクガン、ハクガン、ヒシクイなどがこれに当たり、首が長く、雌雄同色の特徴を持つ。冬鳥として日本に渡ってくるが、渡りの季節に目立つため、秋の季語となる。
カモ目カモ科ガン亜科の水鳥の中でも、カモより大きくハクチョウよりも小さい一群をいう。マガン、カリガネ、コクガン、ハクガン、ヒシクイなどがこれに当たり、首が長く、雌雄同色の特徴を持つ。冬鳥として日本に渡ってくるが、渡りの季節に目立つため、秋の季語となる。
V字になったりなどの編隊飛行で10月頃に北方から渡って来て、沿岸部の湖沼などで生活し、3月頃まで留まる。千葉県の印旛沼などが飛来地として知られていたが、現在では温暖化や開発の影響で、太平洋側では宮城県がマガンの飛来の南限となっている。その宮城県には、国内の8割に当たる10万羽が飛来するという、ラムサール条約にも登録されている伊豆沼・内沼がある。
現在では漢語を元にした「がん」が正式名だが、室町時代以前は「かり」と呼ばれており、現代俳句でも「かり」として詠むのが一般的。なお「かり」の名は、その鳴き声を元にしていると言われる。
古くから狩猟の対象として生活に溶け込んでいた雁は、文学上にも多く登場する。漢書の蘇武伝には、捕らえられた蘇武が、手紙を雁の足に結びつけて放ったという故事があり、そこから「雁の使い」「雁の玉章」という言葉が生まれた。60首あまりの雁の歌が載る万葉集にも、遣新羅使の和歌
天飛ぶや雁を使に得てしかも 奈良の都に言告げ遣らむ
のように「雁の使い」が詠み込まれている。
また「かりがね」という種類の雁が存在するが、もとは「雁が音」で、雁の鳴き声を言い表す言葉だったことが知られており、それが次第に「雁」全般を指す言葉に変化していき、現在では特定種を指す言葉になった。万葉集にも
我が宿に鳴きし雁がね雲の上に 今夜鳴くなり国へかも行く
という詠み人知らずの和歌をはじめ、多数が歌いこまれている。
紛らわしい季語に雁渡しがあるが、これは、雁が渡ってくる9月から10月頃に吹く北風のことである。
雁は遠くから渡ってくるため、「遠つ人」が枕詞となる。万葉集に大伴家持の和歌で、
今朝の朝明秋風寒し遠つ人 雁が来鳴かむ時近みかも
がある。
「雁字」は、雁が飛ぶ様子をいう言葉であり、「雁の使い」にも通じ「手紙」のことも指す。
【雁の俳句】
風の香の身につきそめし雁のころ 岸田稚魚
雲とへだつ友かや雁のいきわかれ 松尾芭蕉

 中国では、重陽の日(陰暦9月9日・菊の節句)に酒を温めて飲むと病気にかからないと言われていた。日本にも、平安時代以前にそれが伝わっていたと見られ、酒を温める習慣がある。
中国では、重陽の日(陰暦9月9日・菊の節句)に酒を温めて飲むと病気にかからないと言われていた。日本にも、平安時代以前にそれが伝わっていたと見られ、酒を温める習慣がある。 スズメ目ヒヨドリ科ヒヨドリ属に分類される漂鳥であるが、留鳥として年中観測されるものもある。特に東京では、近年の温暖化の影響か、一年中生息している。雑食ではあるが、果実や花の蜜を啜っている様子がよく観察される。
スズメ目ヒヨドリ科ヒヨドリ属に分類される漂鳥であるが、留鳥として年中観測されるものもある。特に東京では、近年の温暖化の影響か、一年中生息している。雑食ではあるが、果実や花の蜜を啜っている様子がよく観察される。 かつては収穫された新米を使って造った酒を新酒とし、酒造は10月1日を起点としていたため、10月1日は「日本酒の日」となっている。ただ、江戸時代より寒造りが中心となり、新酒は主に冬場のものとなった。現在でも秋の日本酒は人気であるが、そのほとんどは、春にできた日本酒を貯蔵して出す「ひやおろし」である。
かつては収穫された新米を使って造った酒を新酒とし、酒造は10月1日を起点としていたため、10月1日は「日本酒の日」となっている。ただ、江戸時代より寒造りが中心となり、新酒は主に冬場のものとなった。現在でも秋の日本酒は人気であるが、そのほとんどは、春にできた日本酒を貯蔵して出す「ひやおろし」である。 春と秋にはそれぞれに「行く~」という季語があり、季節を惜しむ。新古今和歌集に権中納言兼宗の
春と秋にはそれぞれに「行く~」という季語があり、季節を惜しむ。新古今和歌集に権中納言兼宗の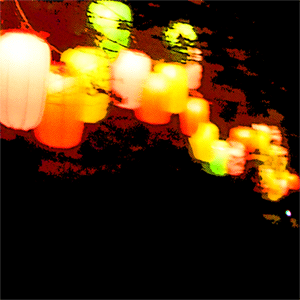 秋の深まりとともに、火の気が恋しくなってくる。
秋の深まりとともに、火の気が恋しくなってくる。 仲秋の名月から約1カ月後の陰暦9月13日夜の名月。満月の二日前に欠けた月を愛で、仲秋の名月だけを愛でることを「片見月」として忌む。仲秋の名月を芋名月というのに対し、豆名月・栗名月と呼び、豆や栗を供える。平安時代にはすでに行われていた、日本独自の風習。「十三夜に曇りなし」と言われ、晴天になることが多い。「芭蕉庵十三夜」(貞亨5年9月13日)に、「木曽の痩せもまだなほらぬに後の月」の句とともに、
仲秋の名月から約1カ月後の陰暦9月13日夜の名月。満月の二日前に欠けた月を愛で、仲秋の名月だけを愛でることを「片見月」として忌む。仲秋の名月を芋名月というのに対し、豆名月・栗名月と呼び、豆や栗を供える。平安時代にはすでに行われていた、日本独自の風習。「十三夜に曇りなし」と言われ、晴天になることが多い。「芭蕉庵十三夜」(貞亨5年9月13日)に、「木曽の痩せもまだなほらぬに後の月」の句とともに、 冬への移行も、秋の暮れ時をも指す秋の暮。新古今和歌集の「三夕の歌」は有名だけれども、それに先立つ後拾遺集に載る良暹法師の歌は、小倉百人一首70番。
冬への移行も、秋の暮れ時をも指す秋の暮。新古今和歌集の「三夕の歌」は有名だけれども、それに先立つ後拾遺集に載る良暹法師の歌は、小倉百人一首70番。 ブドウ科ツタ属の蔦は「夏蔦」とも呼ばれ、9月から11月頃にかけて紅葉する。ウコギ科の「キヅタ」などは「冬蔦」とも呼ばれ、紅葉しない。
ブドウ科ツタ属の蔦は「夏蔦」とも呼ばれ、9月から11月頃にかけて紅葉する。ウコギ科の「キヅタ」などは「冬蔦」とも呼ばれ、紅葉しない。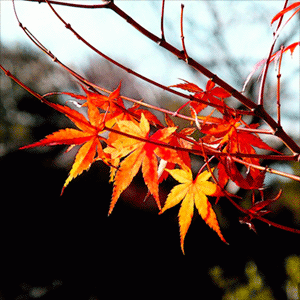 春の花・夏の時鳥・冬の雪とともに、四季を代表する景物。連俳では、花・時鳥・月・雪とともに、「五個の景物」になる。いずれにしても、秋の季語の代表のようなものである。
春の花・夏の時鳥・冬の雪とともに、四季を代表する景物。連俳では、花・時鳥・月・雪とともに、「五個の景物」になる。いずれにしても、秋の季語の代表のようなものである。