三冬の季語 千鳥
浜千鳥(はまちどり)・千鳥足(ちどりあし)・夕千鳥(ゆうちどり)・小夜千鳥(さよちどり)・夕波千鳥(ゆうなみちどり)
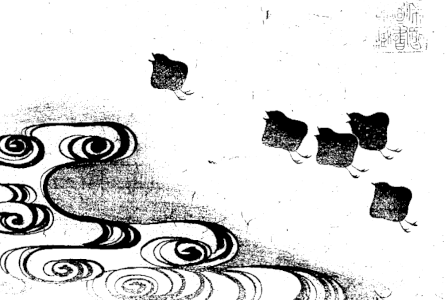 チドリ目チドリ科の鳥には、旅鳥として日本に春秋に立ち寄り少数が越冬するメダイチドリ・ダイゼン、冬鳥としてやってくるタゲリ、夏鳥としてやってくるコチドリ・シロチドリ、留鳥のケリなどが知られる。
チドリ目チドリ科の鳥には、旅鳥として日本に春秋に立ち寄り少数が越冬するメダイチドリ・ダイゼン、冬鳥としてやってくるタゲリ、夏鳥としてやってくるコチドリ・シロチドリ、留鳥のケリなどが知られる。
本来は、野山や水辺に群れる小鳥たちの総称で、「チ」は数の多さを表す「千」の意味と言われる。歴史とともに海辺などで見かける小さな鳥を指す言葉となり、その鳥の群れた様を表す「百千鳥」という言葉も生まれ、この言葉もまたチドリの別名になるに至った。ただし百千鳥は春の季語となる。
古事記に、倭建(やまとたける)が死して後、白鳥になって飛び去るのを追いかけて詠まれた歌に、
浜つ千鳥 浜よ行かず 磯伝ふ
がある。これは、白鳥を追いかける自らの姿を千鳥に擬し、海を越えていく白鳥と、浜から離れられずに磯伝いをする千鳥とを対比している。
万葉集にも26首が載り、柿本人麻呂の
近江の海夕波千鳥汝が鳴けば 心もしのにいにしへ思ほゆ
は有名。その他にも、金葉和歌集の源兼昌の
淡路島かよふ千鳥の鳴く声に いく夜寝覚めぬ須磨の関守
は、小倉百人一首78番。
上記のように、年中見られる千鳥ではあるが、俳句の世界では冬の季語。源氏物語の頃より、冬の景物との地位が定着している。その代表的な姿は、水上を鳴きながら飛んで、誰かを呼ぶというもの。
古くから親しまれてきただけに、千鳥は日本文化の中に溶け込んでいる。吉沢検校の「千鳥の曲」は、古今和歌集の詠み人知らずの和歌
しほの山のさしでの磯にすむ千鳥 君がみよをばやちよとぞなく
と、上記源兼昌の和歌を採り歌としている。
「波に千鳥」は、調和の良いものの譬であり、奈良時代から用いられてきた紋様でもある。かき氷の幟にも、その図柄を確認することができる。
「千鳥足」は、酔っ払いなどの定まらぬ足取りを言うものである。俳諧歳時記栞草では、「千鳥」の項に次いで「兼三冬物」に分類される。「大和本草」の引用で「雀より大也。前三指、後指なし。歩むに、足を左右にちがへてはしる。人の歩むこと、これに似たるを千鳥足と云」とある。
【千鳥の俳句】
星崎の闇を見よとや啼千鳥 松尾芭蕉

 その冬、はじめて降る雪。本格的な寒さのはじまりを告げるものではあるが、心躍るものもある。
その冬、はじめて降る雪。本格的な寒さのはじまりを告げるものではあるが、心躍るものもある。 ウグイスガイ目イタボガキ科とベッコウガキ科に属する二枚貝。英語では「oyster(オイスター)」。食用には、冬に旬を迎えるマガキや、夏に旬を迎えるイワガキ(ともにイタボガキ科マガキ属)が用いられ、身が乳白色で高栄養であることから、海のミルクとも呼ばれる(ゆえに、季語で用いる牡蠣はマガキが主)。
ウグイスガイ目イタボガキ科とベッコウガキ科に属する二枚貝。英語では「oyster(オイスター)」。食用には、冬に旬を迎えるマガキや、夏に旬を迎えるイワガキ(ともにイタボガキ科マガキ属)が用いられ、身が乳白色で高栄養であることから、海のミルクとも呼ばれる(ゆえに、季語で用いる牡蠣はマガキが主)。 水辺に棲息する鳥の種類は豊富で、季節を問わず観察できるが、「水鳥」は冬の季語となる。水鳥の代表的なものが、日本では冬鳥としてやってくるからである。主なものは、
水辺に棲息する鳥の種類は豊富で、季節を問わず観察できるが、「水鳥」は冬の季語となる。水鳥の代表的なものが、日本では冬鳥としてやってくるからである。主なものは、 中国西部原産で、ヒガンバナ科ネギ亜科ネギ属。塩害に強いため、海岸近くの砂地で栽培されることが多い。同属には、タマネギ、ニンニク、ラツキョウ、ニラ、ワケギなどがある。
中国西部原産で、ヒガンバナ科ネギ亜科ネギ属。塩害に強いため、海岸近くの砂地で栽培されることが多い。同属には、タマネギ、ニンニク、ラツキョウ、ニラ、ワケギなどがある。 初冬に、春を思わせる穏やかな晴天が広がることがあり、小春日和とも言う。小春の穏やかな晴天を「小春空」、凪いだ海のことを「小春凪」と言う。
初冬に、春を思わせる穏やかな晴天が広がることがあり、小春日和とも言う。小春の穏やかな晴天を「小春空」、凪いだ海のことを「小春凪」と言う。 気温が下がっても、全ての蜂が死んでしまうわけではなく、冬の日向に蜂を見かけることがある。
気温が下がっても、全ての蜂が死んでしまうわけではなく、冬の日向に蜂を見かけることがある。 その冬、初めて張った氷のこと。東京では12月20日頃となる。因みに終氷は3月10日頃。初雪は1月5日頃、初霜は初氷と同じく12月20日頃である。
その冬、初めて張った氷のこと。東京では12月20日頃となる。因みに終氷は3月10日頃。初雪は1月5日頃、初霜は初氷と同じく12月20日頃である。 二十四節気の第19で、この日から立春の前日までが冬となる。立冬日は、11月7日頃となる。
二十四節気の第19で、この日から立春の前日までが冬となる。立冬日は、11月7日頃となる。 ツバキ科ツバキ属の常緑広葉樹。晩秋から初冬に、赤や白やピンクの、
ツバキ科ツバキ属の常緑広葉樹。晩秋から初冬に、赤や白やピンクの、