仲夏の季語 苔の花
 維管束のない植物・蘚苔類(蘚類・苔類)のことを一般にコケと呼ぶが、鑑賞用に用いられるのは苔類。その苔類にもいろいろな種類があり、苔寺などでよく見られるのは、スギゴケ、ヒノキゴケ、シラガゴケ。
維管束のない植物・蘚苔類(蘚類・苔類)のことを一般にコケと呼ぶが、鑑賞用に用いられるのは苔類。その苔類にもいろいろな種類があり、苔寺などでよく見られるのは、スギゴケ、ヒノキゴケ、シラガゴケ。
コケは、はじめて地上に上陸した植物。約5億年前に上陸したコケは、空中の酸素量の増加に寄与した。
コケは、薄暗い湿気の多い環境を好むと考えられているが、苔類は乾燥にも意外と強い。また、光合成を行うため、光を必要とする存在でもある。「苔の花」と呼ばれるものは、苔類の胞子嚢である蒴のこと。春か秋に蒴が見られる種類が多いが、苔類が雨季に映えるために、夏の季語となる。
このところの苔ブームで、特に人気が高いのは「タマゴケ」の蒴で、その目玉おやじのような姿は、「たまちゃん」の名で親しまれている(画像参照)。
日本において苔は、古くから悠久の時を刻むものとして親しまれており、万葉の時代から「苔生す」の表現がよく使われている。特に有名なのは、「君が代」のもととなった古今和歌集の詠み人知らずの歌
我君は千世に八千世にさゝれ石の 巌となりて苔のむすまで
であろう。
【苔の花の俳句】
苔咲くや親にわかれて二十年 村上鬼城

 昆虫綱ハチ目(膜翅目)に分類される昆虫の内、アリ以外のものをハチという。秋の蜂、
昆虫綱ハチ目(膜翅目)に分類される昆虫の内、アリ以外のものをハチという。秋の蜂、 シダ植物門トクサ綱トクサ目トクサ科トクサ属の植物にスギナがあり、その胞子茎をツクシという。地下茎で繁茂し、根が深いことから「地獄草」の別名もある。ツクシは胞子を放出すると枯れ、緑色のスギナが繁茂する。スギナの名は、その栄養茎が杉に似ていることに因る。
シダ植物門トクサ綱トクサ目トクサ科トクサ属の植物にスギナがあり、その胞子茎をツクシという。地下茎で繁茂し、根が深いことから「地獄草」の別名もある。ツクシは胞子を放出すると枯れ、緑色のスギナが繁茂する。スギナの名は、その栄養茎が杉に似ていることに因る。 モクレン目モクレン科モクレン属の落葉高木で、「田打ち桜」とも呼ばれる。日本原産。3月から5月に白い花をつける。果実の形状が握りこぶしのように凸凹していることが、コブシの名前の由来である。
モクレン目モクレン科モクレン属の落葉高木で、「田打ち桜」とも呼ばれる。日本原産。3月から5月に白い花をつける。果実の形状が握りこぶしのように凸凹していることが、コブシの名前の由来である。 モクレン目モクレン科モクレン属の落葉低木で、紫色の花をつけるため「シモクレン」とも。花がランに似ていることから、木蘭と呼ばれていたとも言われるが、現在では、蓮に似ているとして「木蓮」と呼ぶ。1億年前から既に存在していたことが判明しており、「最古の花木」の異名を持つ。
モクレン目モクレン科モクレン属の落葉低木で、紫色の花をつけるため「シモクレン」とも。花がランに似ていることから、木蘭と呼ばれていたとも言われるが、現在では、蓮に似ているとして「木蓮」と呼ぶ。1億年前から既に存在していたことが判明しており、「最古の花木」の異名を持つ。 雑節の一つで、春分を中日とし、前後各3日を合わせた各7日間を彼岸と言う。秋分を中日とする秋彼岸もあるが、単に「彼岸」ならば、春の彼岸を指す。最初の日を「彼岸の入り」、最後の日を「彼岸明け」と言う。
雑節の一つで、春分を中日とし、前後各3日を合わせた各7日間を彼岸と言う。秋分を中日とする秋彼岸もあるが、単に「彼岸」ならば、春の彼岸を指す。最初の日を「彼岸の入り」、最後の日を「彼岸明け」と言う。 二十四節気の第4。太陽暦では3月20日頃が「春分の日」として祝日になり、彼岸の中日でもある。
二十四節気の第4。太陽暦では3月20日頃が「春分の日」として祝日になり、彼岸の中日でもある。 ヤブコウジ科ヤブコウジ属の常緑小低木で、7月頃に白い花を咲かせ、冬に赤い実をつける。もとは南方系の植物で、関東以南の林間に自生するものであるが、江戸時代から栽培も盛んに行われている。白い実をつけるシロミノマンリョウ、黄色い実をつけるキミノマンリョウなども知られている。
ヤブコウジ科ヤブコウジ属の常緑小低木で、7月頃に白い花を咲かせ、冬に赤い実をつける。もとは南方系の植物で、関東以南の林間に自生するものであるが、江戸時代から栽培も盛んに行われている。白い実をつけるシロミノマンリョウ、黄色い実をつけるキミノマンリョウなども知られている。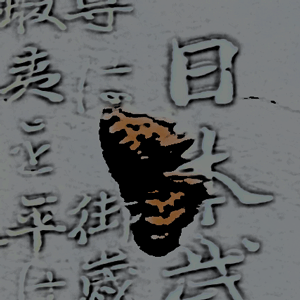 アゲハチョウやモンシロチョウなど、大多数の蝶は、蛹となって越冬するが、中には、卵や幼虫、成虫の形態で越冬するものもある。
アゲハチョウやモンシロチョウなど、大多数の蝶は、蛹となって越冬するが、中には、卵や幼虫、成虫の形態で越冬するものもある。 「時雨」は冬を告げる雨であるが、春のにわか雨には明るさもある。
「時雨」は冬を告げる雨であるが、春のにわか雨には明るさもある。