投稿者: uranari
季語|たんぽぽ
季語|凩(こがらし)
初冬の季語 凩
 初冬の寒風は、木々をも枯らすと言われる。元禄3年(1690年)「新撰都曲」に載った「木枯の果はありけり海の音」は評判を呼び、池西言水は「木枯の言水」と呼ばれている。なお、この句の「海」は琵琶湖、「木枯」は比叡颪である。この句から派生したと見られる、山口誓子の「海に出て木枯らし帰るところなし」も秀句として知られる。
初冬の寒風は、木々をも枯らすと言われる。元禄3年(1690年)「新撰都曲」に載った「木枯の果はありけり海の音」は評判を呼び、池西言水は「木枯の言水」と呼ばれている。なお、この句の「海」は琵琶湖、「木枯」は比叡颪である。この句から派生したと見られる、山口誓子の「海に出て木枯らし帰るところなし」も秀句として知られる。
季語|秋の暮(あきのくれ)
季語|菫(すみれ)
三春の季語 菫
すみれ草(すみれぐさ)・一夜草(ひとよぐさ)
 在来種である菫は、日本各地に自生。花言葉は、「謙虚」「誠実」。万葉集にも「すみれ」あるいは「つほすみれ」として現れ、古くからすみれ摘みの習慣があったことが伺われる。山部赤人には次の歌があり、菫の別名「一夜草」の語源になった。
在来種である菫は、日本各地に自生。花言葉は、「謙虚」「誠実」。万葉集にも「すみれ」あるいは「つほすみれ」として現れ、古くからすみれ摘みの習慣があったことが伺われる。山部赤人には次の歌があり、菫の別名「一夜草」の語源になった。
春の野にすみれ摘みにと来しわれそ野を懐かしみ一夜寝にける
スミレの語源は、植物学者牧野富太郎による、大工道具の「墨入れ」に似ていることから「すみれ」となったという説が有名。
季語|春の雨(はるのあめ)
三春の季語 春の雨
 万葉集にはすでに春雨が歌われている。よみ人しらずではあるが、
万葉集にはすでに春雨が歌われている。よみ人しらずではあるが、
春雨のやまず降る降る我が恋ふる
人の目すらを相見せなくに
などがある。また、嘉永年間 (1848年~1855年) に流行した端唄に「春雨」がある。
春雨にしっぽり濡るる鶯の
羽風に匂う梅が香や
花にたわむれしおらしや
小鳥でさえもひと筋に
ねぐら定めぬ気はひとつ
わたしゃ鶯 主は梅
やがて身まま気ままになるならば
さあ鶯宿梅ぢゃないかいな
さあ何でもよいわいな

 松の梢に吹く風や、その音を松籟という。
松の梢に吹く風や、その音を松籟という。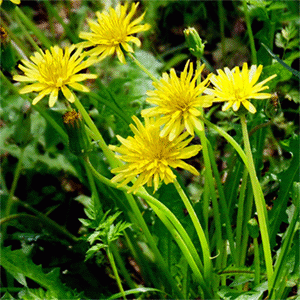 キク科タンポポ属。在来種は外来種(セイヨウタンポポ)に比べ、背が低く、種の数が少ない。セイヨウタンポポは開花期間が長く、夏場でも見られる。
キク科タンポポ属。在来種は外来種(セイヨウタンポポ)に比べ、背が低く、種の数が少ない。セイヨウタンポポは開花期間が長く、夏場でも見られる。 冬への移行も、秋の暮れ時をも指す秋の暮。新古今和歌集の「三夕の歌」は有名だけれども、それに先立つ後拾遺集に載る良暹法師の歌は、小倉百人一首70番。
冬への移行も、秋の暮れ時をも指す秋の暮。新古今和歌集の「三夕の歌」は有名だけれども、それに先立つ後拾遺集に載る良暹法師の歌は、小倉百人一首70番。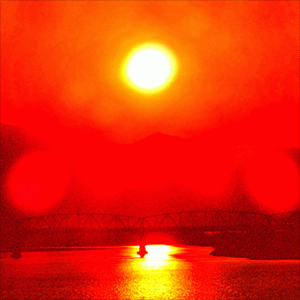 西に傾いた太陽。その日ざし。夏の強い西日は室温を上昇させるために印象深く、夏の季語となる。
西に傾いた太陽。その日ざし。夏の強い西日は室温を上昇させるために印象深く、夏の季語となる。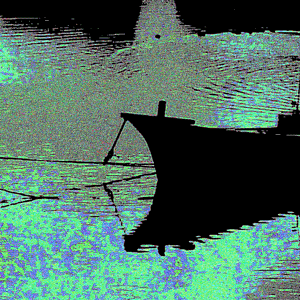 楽しみ目的で船に乗る習慣は古くからあったと見られ、京都嵐山で5月に行われる「三船祭」は、平安時代の面影を残す。当時は主に、和歌や奏楽を楽しんだか。また、万葉集にも原型は確認され、額田王の
楽しみ目的で船に乗る習慣は古くからあったと見られ、京都嵐山で5月に行われる「三船祭」は、平安時代の面影を残す。当時は主に、和歌や奏楽を楽しんだか。また、万葉集にも原型は確認され、額田王の 秋の長雨は、秋雨前線によってもたらされる。秋はまた台風の季節であり、雨の降りやすい時期である。
秋の長雨は、秋雨前線によってもたらされる。秋はまた台風の季節であり、雨の降りやすい時期である。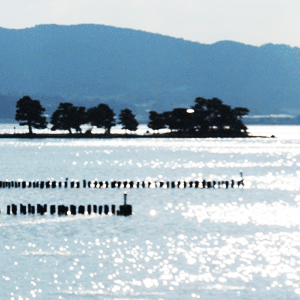 大きいことを表す「う」と水の「み」が結びつき、「うみ」。名前の由来は淡水湖にあるが、塩湖や、淡水中に海水が入った汽水湖もある。
大きいことを表す「う」と水の「み」が結びつき、「うみ」。名前の由来は淡水湖にあるが、塩湖や、淡水中に海水が入った汽水湖もある。