三春の季語 春夕焼
春茜(はるあかね)
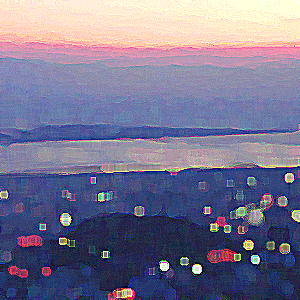 単に「夕焼」といった場合は夏。夕焼の翌日は晴れるという。
単に「夕焼」といった場合は夏。夕焼の翌日は晴れるという。
夕焼の言葉が成立したのは比較的新しく、江戸時代後半に「夕焼」を詠んだ句が散見される。季語となったのは明治以降である。なお、中世には「ほてり」と呼んでいたらしい。中国では夕焼に「霞」の字を当てる。「やけ」も夕焼けを指す言葉として使われているが、朝焼けにも使用されていることから、「やけ」とは「明け」あるいは「朱」の転訛かもしれない。
寒夕焼(かんゆうやけ)・冬茜(ふゆあかね)・寒茜(かんあかね)
 単に「夕焼」といった場合は夏。夕焼の翌日は晴れるという。
単に「夕焼」といった場合は夏。夕焼の翌日は晴れるという。
夕焼の言葉が成立したのは比較的新しく、江戸時代後半に「夕焼」を詠んだ句が散見される。季語となったのは明治以降である。なお、中世には「ほてり」と呼んでいたらしい。中国では夕焼に「霞」の字を当てる。「やけ」も夕焼けを指す言葉として使われているが、朝焼けにも使用されていることから、「やけ」とは「明け」あるいは「朱」の転訛かもしれない。
春水(しゅんすい)・水温む(みずぬるむ)・春の川(はるのかわ)・水の春(みずのはる)
 川や池や水田の水。雪どけや春雨で水かさは増し、次第に温み、命を育む。海水に対して「春の水」を用いることはない。
川や池や水田の水。雪どけや春雨で水かさは増し、次第に温み、命を育む。海水に対して「春の水」を用いることはない。
「水」は、「満つ」からきているという説がある。古事記における水の神・弥都波能売(ミツハノメ)は、火神・迦具土(カグツチ)を生んで陰部を火傷した伊耶那美(イザナミ)の、尿が化成したとある。
 雑節の一つで、春分・秋分を中日とし、前後各3日を合わせた各7日間を彼岸と言い、秋分を中日とするものを秋彼岸、あるいは後の彼岸と呼ぶ。単に「彼岸」ならば、春の彼岸を指す。最初の日を「彼岸の入り」、最後の日を「彼岸明け」と言う。お彼岸にはお墓参りをし、おはぎを先祖に供え感謝し、極楽往生を願う。
雑節の一つで、春分・秋分を中日とし、前後各3日を合わせた各7日間を彼岸と言い、秋分を中日とするものを秋彼岸、あるいは後の彼岸と呼ぶ。単に「彼岸」ならば、春の彼岸を指す。最初の日を「彼岸の入り」、最後の日を「彼岸明け」と言う。お彼岸にはお墓参りをし、おはぎを先祖に供え感謝し、極楽往生を願う。
真西に太陽が沈む春分・秋分に、遙か西方の極楽浄土に思いをはせたのが彼岸の始まり。大同元年(806年)、日本で初めて彼岸会が行われた。なお彼岸の行事は、インドや中国の仏教にはなく、日本独自のものだとされる。
語源は、サンスクリット語の Pāramitā つまり「波羅蜜」にあるとされ、これを意訳した「至彼岸」が元となっている。迷いや煩悩を川にたとえ、その向こうの涅槃を目指すもの。
秋空(あきぞら)・天高し(てんたかし)・秋天(しゅうてん)・秋晴(あきばれ)・秋澄む(あきすむ)・澄む(すむ)・月白(つきしろ)・秋高し(あきたかし)
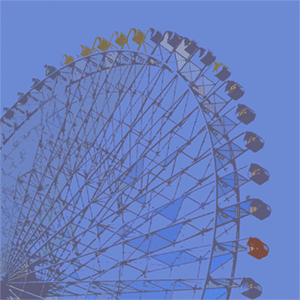 「女心と秋の空」あるいは「男心と秋の空」と言うように、意外にも秋の空は変わりやすく、雨や曇天になることが多い。そして、梅雨時よりも日照時間は短いというデータもある。しかし、晴れると爽やかな空が広がり、その澄みきった空を秋晴という。
「女心と秋の空」あるいは「男心と秋の空」と言うように、意外にも秋の空は変わりやすく、雨や曇天になることが多い。そして、梅雨時よりも日照時間は短いというデータもある。しかし、晴れると爽やかな空が広がり、その澄みきった空を秋晴という。
空は、見上げる時に身体を反らすから「そら」とよばれるようになったとの説がある。なお、山幸彦で知られる天孫・日子穂穂出見を虚空津日高(そらつひこ)と呼ぶが、古くは、天と地上の間にある場所を虚空(そら)と呼んでいたと思われる。
冬満月(ふゆまんげつ)・寒月(かんげつ)・月冴ゆ
 単に「月」といえば秋。
単に「月」といえば秋。
月の語源は、太陽の次に明るいことから次(つく)が変化したものだと言われている。なお、古事記で月の神は三貴神に数え上げられ、イザナギの左目から生まれた太陽神アマテラスの次に、右目からツクヨミとして生まれている。
神有月(かみありづき)・神在月(かみありづき)・神の留守(かみのるす)・神の旅(かみのたび)・神迎(かみむかえ)・神還(かみかえる)
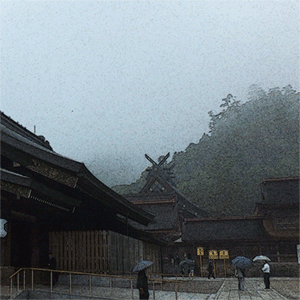 旧暦十月は、全国の神様が大国主が祀られる出雲大社に集結するとされ、神様が留守になることから神無月という。反対に出雲では神有月、神在月という。出雲大社では、縁結びの相談が行われているという。平安時代には既に定着していた説であるが、本来は「神の月」という意味の「神な月」から来ていると言われている。俳諧歳時記栞草には、荷田東麻呂翁の「雷無月」が語源という説も載せる。
旧暦十月は、全国の神様が大国主が祀られる出雲大社に集結するとされ、神様が留守になることから神無月という。反対に出雲では神有月、神在月という。出雲大社では、縁結びの相談が行われているという。平安時代には既に定着していた説であるが、本来は「神の月」という意味の「神な月」から来ていると言われている。俳諧歳時記栞草には、荷田東麻呂翁の「雷無月」が語源という説も載せる。