晩春の季語 チューリップ
 ユリ科チューリップ属の植物で、牡丹百合の名もある。和名は鬱金香(うこんこう)で、花の香りがウコンのように泥臭いことに由来する。チューリップの名は、オスマン帝国からヨーロッパに伝わった時に、誤って、ターバンのことである tülbend と伝わったことから来ている。
ユリ科チューリップ属の植物で、牡丹百合の名もある。和名は鬱金香(うこんこう)で、花の香りがウコンのように泥臭いことに由来する。チューリップの名は、オスマン帝国からヨーロッパに伝わった時に、誤って、ターバンのことである tülbend と伝わったことから来ている。
原産地はトルコのアナトリア地方で、チューリップで有名なオランダには16世紀頃伝わる。オランダは、チューリップ取引で栄え、17世紀にはじまった商品取引の元になったとされる。
オランダには、3人の騎士から求婚された少女が、悩んだ挙句、花になった話が伝わる。それぞれの騎士からの結納であった王冠・剣・財宝が、花・葉・球根になり、少女の名からチューリップと名付けられたとされる。
日本には、江戸時代後期に伝来したが普及せず、大正時代に入って富山や新潟で本格的な球根栽培が始まった。このことから、富山県と新潟県では県花に指定されている。
イラン・アフガニスタン・オランダ・トルコ・ハンガリーでは国花である。
【チューリップの俳句】
チューリップ喜びだけを持つてゐる 細見綾子

 マメ目マメ科シャジクソウ属の多年草。原産地はヨーロッパで、4月から12月にかけて白い花を咲かせる。明治時代以降、牧草として導入されたものが野生化した帰化植物。窒素固定作用があり、緑化資材にも適している。
マメ目マメ科シャジクソウ属の多年草。原産地はヨーロッパで、4月から12月にかけて白い花を咲かせる。明治時代以降、牧草として導入されたものが野生化した帰化植物。窒素固定作用があり、緑化資材にも適している。 マメ科フジ属のつる性落葉木本。つるが右巻きの藤を「フジ(ノダフジ)」、左巻きの藤を「ヤマフジ(ノフジ)」といい、共に日本固有種。4月から5月に花を咲かせる。
マメ科フジ属のつる性落葉木本。つるが右巻きの藤を「フジ(ノダフジ)」、左巻きの藤を「ヤマフジ(ノフジ)」といい、共に日本固有種。4月から5月に花を咲かせる。 キク科アザミ属で、日本では100種類ほどが知られており、春から秋にかけて花が咲く。「薊」だけでは春の季語であるが、夏の季語となる「夏薊」、秋の季語である「富士薊」などがある。
キク科アザミ属で、日本では100種類ほどが知られており、春から秋にかけて花が咲く。「薊」だけでは春の季語であるが、夏の季語となる「夏薊」、秋の季語である「富士薊」などがある。 猫の繁殖は1月から8月頃まで続き、妊娠期間は約65日。よって、冬場を除いて子猫は生まれるが、子猫が最も多くみられるのは春である。
猫の繁殖は1月から8月頃まで続き、妊娠期間は約65日。よって、冬場を除いて子猫は生まれるが、子猫が最も多くみられるのは春である。
 1656年の伊勢暦に記され、1685年からはじまる貞享暦に正式に採用された、日本独自の雑節のひとつ。
1656年の伊勢暦に記され、1685年からはじまる貞享暦に正式に採用された、日本独自の雑節のひとつ。


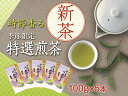









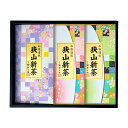

 二十四節気のひとつで、太陽の黄経が30度に達した時を言い、太陽暦では4月20日頃。この日から、立夏前日までが「穀雨」と呼ばれる期間。
二十四節気のひとつで、太陽の黄経が30度に達した時を言い、太陽暦では4月20日頃。この日から、立夏前日までが「穀雨」と呼ばれる期間。 日本で柳と言えば、主にシダレヤナギを指す。これは中国原産で、奈良時代に渡来した。雌雄の区分があり、日本で見られるもののほとんどは雄株。落葉性で、秋の終わりに一気に葉が散る。春には、葉をつけて、雌株は
日本で柳と言えば、主にシダレヤナギを指す。これは中国原産で、奈良時代に渡来した。雌雄の区分があり、日本で見られるもののほとんどは雄株。落葉性で、秋の終わりに一気に葉が散る。春には、葉をつけて、雌株は バラ科ボケ属の落葉低木。朱紅色の緋木瓜、純白の白木瓜、紅と白とが混じる更紗木瓜などがある。原産地は中国で、日本には平安時代に入ってきたと見られている。木瓜は、「ぼっか」「もっか」とも読む。果実が瓜に似ているところから、木になる瓜の意で「木瓜」となった。花は3月から4月に見られるが、11月頃から花を咲かせる寒木瓜もあり、こちらは冬の季語になる。
バラ科ボケ属の落葉低木。朱紅色の緋木瓜、純白の白木瓜、紅と白とが混じる更紗木瓜などがある。原産地は中国で、日本には平安時代に入ってきたと見られている。木瓜は、「ぼっか」「もっか」とも読む。果実が瓜に似ているところから、木になる瓜の意で「木瓜」となった。花は3月から4月に見られるが、11月頃から花を咲かせる寒木瓜もあり、こちらは冬の季語になる。