カテゴリー: 季語
季語|鳥帰る(とりかえる)
仲春の季語 鳥帰る
帰る鳥(かえるとり)・鳥雲に入る(とりくもにいる)・鳥雲に(とりくもに)・鳥曇(とりぐもり)
 鴨や白鳥など、日本で越冬した鳥が北方へ帰ること。秋の「鳥渡る(渡り鳥)」に対応する。
鴨や白鳥など、日本で越冬した鳥が北方へ帰ること。秋の「鳥渡る(渡り鳥)」に対応する。
その鳥が、彼方の雲に見えなくなる様を「鳥雲に入る」「鳥雲に」という。また、その雲を指す「鳥雲」や、天候を指す「鳥曇」という季語も有る。
鳥を特定する季語としては「引鶴」「引鴨」「帰雁」「白鳥帰る」「戻り鴫」などがある。
▶ 関連季語 鳥渡る(秋)
季語|師走(しわす)
仲冬の季語 師走
 陰暦の師走は晩冬。現在では、新暦の12月も師走と呼ぶ。古くは、暮れの数日のみを「しはす」と言っていたらしい。
陰暦の師走は晩冬。現在では、新暦の12月も師走と呼ぶ。古くは、暮れの数日のみを「しはす」と言っていたらしい。
語源は、僧が読経に走り回るために「師馳す」にあるとされ、平安時代から支持されてきたが、一年の終わりを指す「年果つ(としはつ)」にあると見る方が正しいか。一年の行事を為し終えたことを「為果つ(しはつ)」と表現したとの説もある。万葉集には、一首だけ「師走」の歌が載るが、これは「十二月」を「しはす」と読む。
十二月には沫雪降ると知らぬかも梅の花咲く含めらずして 紀小鹿郎女
季語|寒梅(かんばい)
季語|蝶(ちょう・てふ)
三春の季語 蝶
紋白蝶(もんしろちょう)・蝶々(てふてふ・ちょうちょう)・胡蝶(こちょう)・黄蝶(きちょう)
 同じ蝶でも、「揚羽蝶」は夏の季語となる。蝶のことを新撰字鏡では「加波比良古(かわひらこ)」とし、亡くなった人の魂をも表した。川の近くでひらひら飛んでいたからこの名前がついたと言われ、蝶の古名とされるが、カワトンボとの混同ではないかとも疑われる。
同じ蝶でも、「揚羽蝶」は夏の季語となる。蝶のことを新撰字鏡では「加波比良古(かわひらこ)」とし、亡くなった人の魂をも表した。川の近くでひらひら飛んでいたからこの名前がついたと言われ、蝶の古名とされるが、カワトンボとの混同ではないかとも疑われる。
因みに蝶は、奈良時代に唐から入ってきた言葉で、「てふ」と読んだ。万葉集に蝶の歌は載らないが、巻五の梅の歌の序文に1箇所だけ「新蝶」として出てくる。古今和歌集には、僧正遍照の和歌として
散りぬればのちはあくたになる花を思ひ知らずも惑ふてふかな
がある。
季語|秋風(あきかぜ・しゅうふう)
三秋の季語 秋風
秋の風(あきのかぜ)・あきの風(あきのかぜ)・金風(きんぷう)・色なき風(いろなきかぜ)・爽籟(そうらい)
 秋が五行説の金行にあたるので「金風」ともいう。その爽やかな響きを爽籟という。「飽き」に掛けて、男女間の愛情が冷めることにもたとえられる。万葉集には「秋風」を詠んだ歌が60首あまりあり、大伴家持は夫人を亡くしてひと月経って、
秋が五行説の金行にあたるので「金風」ともいう。その爽やかな響きを爽籟という。「飽き」に掛けて、男女間の愛情が冷めることにもたとえられる。万葉集には「秋風」を詠んだ歌が60首あまりあり、大伴家持は夫人を亡くしてひと月経って、
うつせみの世は常なしと知るものを秋風寒み偲ひつるかも
と歌った。芭蕉の句「物いへば~」は、半ば慣用句。
季語|凍る(こおる)
季語|若葉(わかば)
季語|河童忌(かっぱき)
季語|牡丹(ぼたん)
初夏の季語 牡丹
ぼうたん・白牡丹(はくぼたん)・緋牡丹(ひぼたん)・牡丹園(ぼたんえん)・深見草(ふかみぐさ)・鎧草(よろいぐさ)
 花王とも呼ばれ、中国では古代よりもっとも親しまれてきた花である。隋の煬帝や、唐の則天武后が愛でたという伝説もある。根の樹皮は、「牡丹皮」として薬になる。日本には、天平時代に中国から入ってきたと見られている。李白は、楊貴妃を「花」として牡丹にたとえている。日本文学では「枕草子」に初出。古くは「ふかみ草」と言い、千載和歌集には賀茂重保の歌が載る。
花王とも呼ばれ、中国では古代よりもっとも親しまれてきた花である。隋の煬帝や、唐の則天武后が愛でたという伝説もある。根の樹皮は、「牡丹皮」として薬になる。日本には、天平時代に中国から入ってきたと見られている。李白は、楊貴妃を「花」として牡丹にたとえている。日本文学では「枕草子」に初出。古くは「ふかみ草」と言い、千載和歌集には賀茂重保の歌が載る。
人しれず思ふこころはふかみぐさ花咲きてこそ色に出でけれ
裏切りから身を滅ぼすことを指す「獅子身中の虫」という仏教用語があるが、牡丹の花の夜露はその薬となると言われ、獅子は牡丹の花から離れられない。それを基に、獅子に牡丹をあしらった芸術作品が数多く存在する。
「ボタン」は、漢語「牡丹」から来ている。接ぎ木で増やされたため「牡(オス)」の植物とみなされ、それに赤を表す「丹」をつけて表現された。つまり「赤い男」である。5月頃に見頃となるため、夏の季語となる。
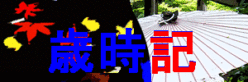
 吐く息が白く見えること。
吐く息が白く見えること。 梅の花は春、実は夏の季語になる。万葉の昔から親しまれてきた花である。
梅の花は春、実は夏の季語になる。万葉の昔から親しまれてきた花である。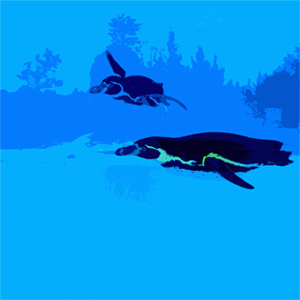 「こおる」が表面的であるのに対して、「しむ(凍む)」は奥まで深くこおってゆく語感をもつ。新古今集に載る藤原家隆の和歌
「こおる」が表面的であるのに対して、「しむ(凍む)」は奥まで深くこおってゆく語感をもつ。新古今集に載る藤原家隆の和歌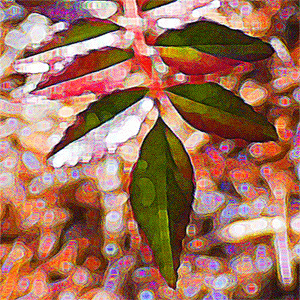 生えたばかりの葉を言うが、若さ・新しさ・青さの象徴に用いられることもある季語。万葉集には見られず、一説には源氏物語での造語とも。源氏物語では玉鬘の歌として、
生えたばかりの葉を言うが、若さ・新しさ・青さの象徴に用いられることもある季語。万葉集には見られず、一説には源氏物語での造語とも。源氏物語では玉鬘の歌として、 7月24日。
7月24日。