初秋の季語 芙蓉
 アオイ科フヨウ属の落葉低木。中国では蓮のことを芙蓉と呼んでおり、日本では、区別するために「木芙蓉(もくふよう)」と呼ぶ。蓮のことは「水芙蓉(すいふよう)」とも呼ぶ。ただし、俳諧歳時記栞草では、「木芙蓉」と書いて「ふよう」と読ませ、蓮のことを「草芙蓉」と呼んでいる。
アオイ科フヨウ属の落葉低木。中国では蓮のことを芙蓉と呼んでおり、日本では、区別するために「木芙蓉(もくふよう)」と呼ぶ。蓮のことは「水芙蓉(すいふよう)」とも呼ぶ。ただし、俳諧歳時記栞草では、「木芙蓉」と書いて「ふよう」と読ませ、蓮のことを「草芙蓉」と呼んでいる。
槿(むくげ)と似ているが、槿は雌しべの先が真っすぐなのに対し、芙蓉は上に向いて曲がる。ハイビスカスも近縁種である。
中国原産で、沖縄、九州・四国の海岸近くに自生する。7月から10月頃に花をつける。朝咲いて夕方には萎む1日花で、次々に花を咲かせる。「酔芙蓉」は、朝は白く、時間が経つにつれて赤みがかってくるため、酔った姿に擬して名がついた。
富士山には、「芙蓉峰」あるいは「芙蓉」の名がついている。
【芙蓉の俳句】
日を帯びて芙蓉かたぶく恨みかな 与謝蕪村
たちいでて芙蓉のしぼむ日に逢へり 加舎白雄

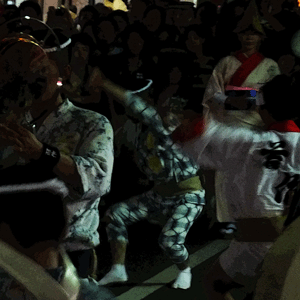 俳句で「踊」と言えば、盆踊りのことで秋の季語となる。盆に帰ってきた先祖の霊を慰めるための行事である。
俳句で「踊」と言えば、盆踊りのことで秋の季語となる。盆に帰ってきた先祖の霊を慰めるための行事である。 ウリ科の西瓜の原産地は、アフリカの砂漠地帯。日本への伝来は室町時代と考えられているが、鳥獣戯画に西瓜と見られる貢物が描かれており、平安時代に伝来していた可能性もある。
ウリ科の西瓜の原産地は、アフリカの砂漠地帯。日本への伝来は室町時代と考えられているが、鳥獣戯画に西瓜と見られる貢物が描かれており、平安時代に伝来していた可能性もある。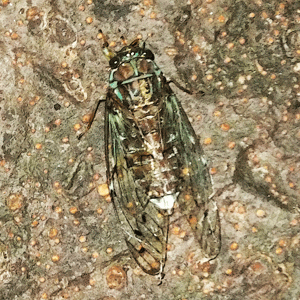 カメムシ目セミ科に属する
カメムシ目セミ科に属する 立秋を過ぎても残る暑さを言い秋の季語となる。立秋は8月7日前後なので、それ以降の暑さは残暑となる。概ね8月いっぱいの暑さを残暑と言う。
立秋を過ぎても残る暑さを言い秋の季語となる。立秋は8月7日前後なので、それ以降の暑さは残暑となる。概ね8月いっぱいの暑さを残暑と言う。 二十四節気の第13。夏至と秋分の中間で、太陽暦では8月7日頃。暦上は、この日から秋になる。
二十四節気の第13。夏至と秋分の中間で、太陽暦では8月7日頃。暦上は、この日から秋になる。 盆の鎮魂や秋祭りの奉納として打ち上げられ、秋の季語として扱う場合もあるが、両国の花火が川開きとともに行われたことが全国に広がり、夏の風物詩として定着し、夏の季語となっている。
盆の鎮魂や秋祭りの奉納として打ち上げられ、秋の季語として扱う場合もあるが、両国の花火が川開きとともに行われたことが全国に広がり、夏の風物詩として定着し、夏の季語となっている。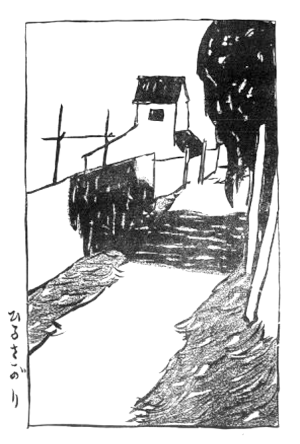 晩夏の昼は、日射しも強く気だるさを伴うイメージ。灼けつくような夏の午後の暑さを、炎昼と表現した。「炎」は「炎帝」の「炎」であり、「炎帝」は夏を司る神。
晩夏の昼は、日射しも強く気だるさを伴うイメージ。灼けつくような夏の午後の暑さを、炎昼と表現した。「炎」は「炎帝」の「炎」であり、「炎帝」は夏を司る神。 中国原産の、ノウゼンカズラ科の落葉性のつる性木本。
中国原産の、ノウゼンカズラ科の落葉性のつる性木本。 7月下旬から8月にかけての長期休暇を夏休みと言う。社会人にとっては盆休みが夏休みとなることが多いが、「
7月下旬から8月にかけての長期休暇を夏休みと言う。社会人にとっては盆休みが夏休みとなることが多いが、「