ن¸‰ه¤ڈمپ®ه£èھم€€ç€§
و»ï¼ˆمپںمپچ)مƒ»ç€‘ه¸ƒï¼ˆمپ°مپڈمپµï¼‰
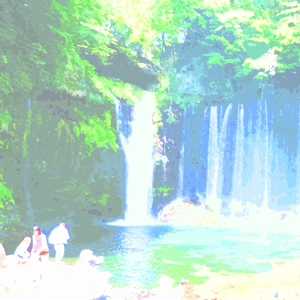 ه›½هœںهœ°çگ†é™¢مپ®ه®ڑ義مپ«م‚ˆم‚‹مپ¨م€پ瀧مپ¨مپ¯م€پم€Œوµپو°´مپŒو€¥و؟€مپ«èگ½ن¸‹مپ™م‚‹ه ´و‰€مپ§èگ½ه·®مپŒï¼•مƒ،مƒ¼مƒˆمƒ«ن»¥ن¸ٹم€په¸¸و™‚و°´مپŒوµپم‚Œمپ¦مپ„م‚‹م‚‚مپ®م€چم€‚ه½¢çٹ¶مپ«م‚ˆمپ£مپ¦هˆ†é،مپŒمپھمپ•م‚Œمپ¦مپٹم‚ٹم€پ直瀑م‚„هˆ†ه²گ瀑م€پو®µç€‘م€پوµ·ه²¸ç€‘مپھمپ©مپŒمپ‚م‚‹م€‚و—¥وœ¬ن¸‰ه¤§هگچ瀑مپ¨مپ—مپ¦وœ‰هگچمپھ瀧م‚‚مپ‚م‚‹مپŒم€پé‚£و™؛و»مƒ»èڈ¯هژ³و»مپ®2瀑ن»¥ه¤–مپ¯م€پ袋田مپ®و»م‚„白糸مپ®و»مپŒوŒ™مپ’م‚‰م‚Œم‚‹مپھمپ©م€په®ڑمپ¾مپ£مپ¦مپ„مپھمپ„م€‚
ه›½هœںهœ°çگ†é™¢مپ®ه®ڑ義مپ«م‚ˆم‚‹مپ¨م€پ瀧مپ¨مپ¯م€پم€Œوµپو°´مپŒو€¥و؟€مپ«èگ½ن¸‹مپ™م‚‹ه ´و‰€مپ§èگ½ه·®مپŒï¼•مƒ،مƒ¼مƒˆمƒ«ن»¥ن¸ٹم€په¸¸و™‚و°´مپŒوµپم‚Œمپ¦مپ„م‚‹م‚‚مپ®م€چم€‚ه½¢çٹ¶مپ«م‚ˆمپ£مپ¦هˆ†é،مپŒمپھمپ•م‚Œمپ¦مپٹم‚ٹم€پ直瀑م‚„هˆ†ه²گ瀑م€پو®µç€‘م€پوµ·ه²¸ç€‘مپھمپ©مپŒمپ‚م‚‹م€‚و—¥وœ¬ن¸‰ه¤§هگچ瀑مپ¨مپ—مپ¦وœ‰هگچمپھ瀧م‚‚مپ‚م‚‹مپŒم€پé‚£و™؛و»مƒ»èڈ¯هژ³و»مپ®2瀑ن»¥ه¤–مپ¯م€پ袋田مپ®و»م‚„白糸مپ®و»مپŒوŒ™مپ’م‚‰م‚Œم‚‹مپھمپ©م€په®ڑمپ¾مپ£مپ¦مپ„مپھمپ„م€‚
瀧مپŒه¤ڈمپ®ه£èھمپ¨مپھمپ£مپںمپ®مپ¯م€پè؟‘ن¸–مپ«مپھمپ£مپ¦مپ‹م‚‰مپ مپ¨è¨€م‚ڈم‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚èٹ蕉مپ«م€Œمپ—مپ°م‚‰مپڈمپ¯ç€§مپ«ç± م‚‹م‚„ه¤ڈمپ®هˆم‚پم€چمپŒمپ‚م‚ٹم€پ瀧مپ‹م‚‰و¶¼م‚’連وƒ³مپ•مپ›م‚‹مپ“مپ¨مپ¯مپ‚م‚ٹم€پم€Œه¤ڈم€چمپ¨م‚†م‚‹مپڈçµگمپ³مپ¤مپ„مپ¦مپ„مپںم€‚ن؟³è«§و³و™‚è¨کو èچ‰مپ§مپ¯م€پ瀧مپ®مپمپ°مپ«é€ م‚‹و®؟èˆژم‚’م€Œو»و®؟م€چمپ¨مپ—مپ¦ه¤ڈن¹‹éƒ¨ه…وœˆمپ«هˆ†é،مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚ه®ںéڑ›مپ«م€پو¢…雨م‚„هڈ°é¢¨مپ®ه½±éں؟مپ§وœ€م‚‚و°´é‡ڈمپŒه¤ڑمپڈمپھم‚ٹم€پ瀧مپ®هٹ›مپŒوœ€ه¤§مپ«مپھم‚‹مپ®مپ¯ه¤ڈه£مپ§مپ‚م‚ٹم€په¤ڈمپ®ه£èھمپ¨مپھم‚‹مپ®مپ«ن¸چه‚™مپ¯مپھمپ„م€‚
ه› مپ؟مپ«م€پو°´é‡ڈمپŒوœ€ه°ڈمپ«مپھم‚‹ه†¬مپ«مپ¯م€Œو¶¸و»م€چمپ®ه£èھمپŒمپ‚م‚‹م€‚
ن¸‡è‘‰é›†مپ«م‚‚ه¤ڑمپڈمپ®م€Œç€§م€چمپŒè© مپ¾م‚Œمپ¦مپ„م‚‹مپŒم€پمپ“مپ®é ƒمپ«مپ¯م€پو€¥وµپم‚’م€Œç€§م€چمپ¨è،¨çڈ¾مپ—مپںه½¢è·،مپŒمپ‚م‚‹م€‚ه¤§çں³è“‘é؛»ه‘‚مپ¯م€په®‰èٹ¸ه›½مپ®é•·é–€ه³¶مپ§
çں³èµ°م‚‹ç€§م‚‚مپ¨مپ©م‚چمپ«é³´مپڈè‰مپ®م€€ه£°م‚’مپ—èپمپ‘مپ°éƒ½مپ—و€مپ»م‚†
مپ¨وŒمپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚م€Œمپںمپچم€چمپ®èھو؛گم‚‚م€پو€¥وµپم‚’وŒ‡مپ™م€Œمپںمپژمپ¤مپ›م€چم€پمپ¤مپ¾م‚ٹم€Œو»¾م‚‹م€چمپ§مپ‚م‚‹مپ¨è¨€م‚ڈم‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚
مپ¾مپںم€پن¸‡è‘‰é›†مپ«مپ¯ç€§م‚’ه‚و°´ï¼ˆمپںم‚‹مپ؟)مپ¨ه‘¼م‚“مپ وŒم‚‚وژ²è¼‰مپ•م‚Œمپ¦مپٹم‚ٹم€پمپ“مپ،م‚‰مپ®و–¹مپŒم€پçڈ¾هœ¨مپ®م€Œç€§م€چم‚’وŒ‡مپ™مپ®مپ§مپ¯مپھمپ„مپ‹مپ¨è¨€م‚ڈم‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚مپ„مپڑم‚Œم‚‚م€Œçں³èµ°م‚‹م€چمپ®و•è©م‚’ن¼´مپ†م€‚
مپمپ®ه†…مپ®ن¸€é¦–م€پè© مپ؟ن؛؛çں¥م‚‰مپڑمپ®مپ“مپ®وŒم€پ
ه‘½م‚’مپ—ه¹¸مپڈم‚ˆمپ‘م‚€مپ¨çں³èµ°م‚‹م€€ه‚و°´مپ®و°´م‚’م‚€مپ™مپ³مپ¦é£²مپ؟مپ¤
مپ®م‚ˆمپ†مپ«م€پ瀧مپ®و°´مپ«مپ¯éœٹهٹ›مپŒمپ‚م‚‹مپ¨ن؟،مپکم‚‰م‚Œمپ¦مپٹم‚ٹم€پ瀧مپ®و°´م‚’飲م‚“مپ§è‹¥è؟”مپ£مپںمپ¨مپ„مپ†ن¼èھ¬م‚‚هگ„هœ°مپ«و®‹م‚‹م€‚
م€Œه¾Œو¼¢و›¸م€چه…ڑ錮ن¼مپ«م€پ黄و²³ن¸ٹوµپمپ«مپ‚م‚‹ç«œé–€م‚’ç™»م‚ٹمپچمپ£مپں鯉مپ¯ç«œمپ«مپھم‚‹مپ¨مپ„مپ†م€‚م€Œé¯‰مپ®ç€§ç™»م‚ٹم€چمپ®èھو؛گمپ§مپ‚م‚‹م€‚
م€گ瀧مپ®ن؟³هڈ¥م€‘
瀧èگ½مپ،مپ¦ç¾¤é’ن¸–ç•Œمپ¨مپ©م‚چمپ‘م‚ٹم€€م€€و°´هژں秋و،œهگ
é…’مپ®مپ؟مپ«èھم‚‰م‚“مپ‹م‚م‚‹ç€§مپ®èٹ±م€€م€€و¾ه°¾èٹ蕉

 é›ھمپ®ه¦–و€ھمپ§م€پم€Œمƒ¦م‚مƒ م‚¹مƒ،م€چم€Œمƒ¦م‚م‚ھمƒ³مƒگم€چم€Œمƒ¦م‚م‚ھمƒٹم‚´م€چمپھمپ©مپ¨ه‘¼مپ°م‚Œم‚‹مپ“مپ¨م‚‚م€‚م€Œه®—祇諸ه›½ç‰©èھم€چ(è¥؟و‘ه¸‚éƒژهڈ³è،›é–€ï¼ڑ1685ه¹´ï¼‰مپ«مپ¯م€پ
é›ھمپ®ه¦–و€ھمپ§م€پم€Œمƒ¦م‚مƒ م‚¹مƒ،م€چم€Œمƒ¦م‚م‚ھمƒ³مƒگم€چم€Œمƒ¦م‚م‚ھمƒٹم‚´م€چمپھمپ©مپ¨ه‘¼مپ°م‚Œم‚‹مپ“مپ¨م‚‚م€‚م€Œه®—祇諸ه›½ç‰©èھم€چ(è¥؟و‘ه¸‚éƒژهڈ³è،›é–€ï¼ڑ1685ه¹´ï¼‰مپ«مپ¯م€پ














 وœ¨ç“œمپ®èٹ±مپ¯وک¥مپ®ه£èھمپ«مپھم‚‹مپŒم€پ11وœˆé ƒمپ‹م‚‰èٹ±م‚’ه’²مپ‹مپ›م‚‹ه“پ種م‚‚مپ‚م‚ٹم€په¯’وœ¨ç“œمپ¨ه‘¼مپ¶م€‚ه“پ種مپ«مپ¯م€Œمپ‹م‚“مپ،مپ©م‚ٹم€چم€Œمپ‹م‚“مپ•م‚‰مپ•م€چم€Œمپ—مپ®مپ®م‚پم€چم€Œمپ¹مپ«مپ¼مپںم‚“م€چمپھمپ©مپŒمپ‚م‚‹م€‚
وœ¨ç“œمپ®èٹ±مپ¯وک¥مپ®ه£èھمپ«مپھم‚‹مپŒم€پ11وœˆé ƒمپ‹م‚‰èٹ±م‚’ه’²مپ‹مپ›م‚‹ه“پ種م‚‚مپ‚م‚ٹم€په¯’وœ¨ç“œمپ¨ه‘¼مپ¶م€‚ه“پ種مپ«مپ¯م€Œمپ‹م‚“مپ،مپ©م‚ٹم€چم€Œمپ‹م‚“مپ•م‚‰مپ•م€چم€Œمپ—مپ®مپ®م‚پم€چم€Œمپ¹مپ«مپ¼مپںم‚“م€چمپھمپ©مپŒمپ‚م‚‹م€‚ ن؛Œهچپه››ç¯€و°—مپ®ç¬¬1م€‚2وœˆ4و—¥مپ“م‚چمپ‹م‚‰2وœˆ20و—¥مپ“م‚چمپ®é›¨و°´مپ®ه‰چو—¥مپ¾مپ§مپ§مپ‚م‚‹مپŒم€پن¸€èˆ¬çڑ„مپ«مپ¯مپمپ®هˆو—¥م‚’مپ„مپ†م€‚ه†¬è‡³مپ¨وک¥هˆ†مپ®ن¸é–“مپ§مپ‚م‚ٹم€په£ç¯€مپ®و±؛مپ¾م‚ٹمپ”مپ¨مپ¯م€پمپ“مپ®و—¥مپŒèµ·ç‚¹مپ¨مپھم‚‹م€‚ç«‹وک¥مپ¨مپ¯è¨€مپˆم€پمپ“مپ®é ƒمپŒن¸€ه¹´مپ§وœ€م‚‚ه¯’مپ•مپŒهژ³مپ—مپ„م€‚ç«‹وک¥م‚’ه¢ƒمپ«م€پم€Œه¯’ن¸è¦‹èˆمپ„م€چمپ¯م€Œن½™ه¯’見èˆمپ„م€چمپ«هˆ‡م‚ٹو›؟م‚ڈم‚‹م€‚
ن؛Œهچپه››ç¯€و°—مپ®ç¬¬1م€‚2وœˆ4و—¥مپ“م‚چمپ‹م‚‰2وœˆ20و—¥مپ“م‚چمپ®é›¨و°´مپ®ه‰چو—¥مپ¾مپ§مپ§مپ‚م‚‹مپŒم€پن¸€èˆ¬çڑ„مپ«مپ¯مپمپ®هˆو—¥م‚’مپ„مپ†م€‚ه†¬è‡³مپ¨وک¥هˆ†مپ®ن¸é–“مپ§مپ‚م‚ٹم€په£ç¯€مپ®و±؛مپ¾م‚ٹمپ”مپ¨مپ¯م€پمپ“مپ®و—¥مپŒèµ·ç‚¹مپ¨مپھم‚‹م€‚ç«‹وک¥مپ¨مپ¯è¨€مپˆم€پمپ“مپ®é ƒمپŒن¸€ه¹´مپ§وœ€م‚‚ه¯’مپ•مپŒهژ³مپ—مپ„م€‚ç«‹وک¥م‚’ه¢ƒمپ«م€پم€Œه¯’ن¸è¦‹èˆمپ„م€چمپ¯م€Œن½™ه¯’見èˆمپ„م€چمپ«هˆ‡م‚ٹو›؟م‚ڈم‚‹م€‚ 雑節مپ®ن¸€مپ¤مپ§م€پهگ„ه£ç¯€مپ®ه§‹مپ¾م‚ٹمپ®و—¥مپ®ه‰چو—¥مپ®مپ“مپ¨مپ§مپ‚مپ£مپںمپŒم€پو±ںوˆ¸و™‚ن»£ن»¥é™چمپ¯ç«‹وک¥مپ®ه‰چو—¥م‚’وŒ‡مپ™مپ“مپ¨مپŒو™®é€ڑمپ«مپھمپ£مپںم€‚مپ“مپ®و—¥مپ¾مپ§ه¤§ه¯’مپ§مپ‚م‚ٹم€پن¸€ه¹´مپ§ن¸€ç•ھه¯’مپ„و—¥مپ®وœ€ه¾Œمپ®و—¥مپ¨مپھم‚‹م€‚
雑節مپ®ن¸€مپ¤مپ§م€پهگ„ه£ç¯€مپ®ه§‹مپ¾م‚ٹمپ®و—¥مپ®ه‰چو—¥مپ®مپ“مپ¨مپ§مپ‚مپ£مپںمپŒم€پو±ںوˆ¸و™‚ن»£ن»¥é™چمپ¯ç«‹وک¥مپ®ه‰چو—¥م‚’وŒ‡مپ™مپ“مپ¨مپŒو™®é€ڑمپ«مپھمپ£مپںم€‚مپ“مپ®و—¥مپ¾مپ§ه¤§ه¯’مپ§مپ‚م‚ٹم€پن¸€ه¹´مپ§ن¸€ç•ھه¯’مپ„و—¥مپ®وœ€ه¾Œمپ®و—¥مپ¨مپھم‚‹م€‚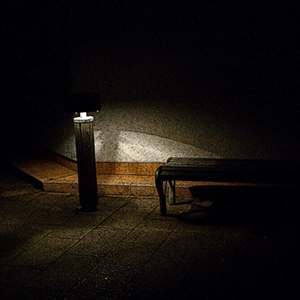 ه†¬مپ®ه¤œمپ®ه¯’مپ•مپ¯هژ³مپ—مپ„م€‚çڈ¾ن»£مپ§مپ“مپوڑ–وˆ؟è¨ه‚™مپŒو•´مپ„م€په®¤ه†…مپ§مپ¯ه؟«éپ©مپ«éپژمپ”مپ™مپ“مپ¨مپŒمپ§مپچم‚‹م‚ˆمپ†مپ«مپھمپ£مپںمپŒم€پمپ‹مپ¤مپ¦مپ¯م€پمپم‚Œم‚’ه¦‚ن½•مپ«éپ£م‚ٹéپژمپ”مپ™مپ‹مپ¯ç”ںمپچمپ¦مپ„مپڈن¸ٹمپ§مپ®èھ²é،Œمپ§مپ‚مپ£مپںم€‚هڈ¤مپ„هڈ¥مپ«م€پو™‚ن»£مپ®ه¤‰éپ·م‚’見م‚‹مپ®م‚‚é¢ç™½مپ„م€‚
ه†¬مپ®ه¤œمپ®ه¯’مپ•مپ¯هژ³مپ—مپ„م€‚çڈ¾ن»£مپ§مپ“مپوڑ–وˆ؟è¨ه‚™مپŒو•´مپ„م€په®¤ه†…مپ§مپ¯ه؟«éپ©مپ«éپژمپ”مپ™مپ“مپ¨مپŒمپ§مپچم‚‹م‚ˆمپ†مپ«مپھمپ£مپںمپŒم€پمپ‹مپ¤مپ¦مپ¯م€پمپم‚Œم‚’ه¦‚ن½•مپ«éپ£م‚ٹéپژمپ”مپ™مپ‹مپ¯ç”ںمپچمپ¦مپ„مپڈن¸ٹمپ§مپ®èھ²é،Œمپ§مپ‚مپ£مپںم€‚هڈ¤مپ„هڈ¥مپ«م€پو™‚ن»£مپ®ه¤‰éپ·م‚’見م‚‹مپ®م‚‚é¢ç™½مپ„م€‚ ن¸ه›½مپ§مپ¯م€پèچ‰مپŒè…گمپ£مپ¦è›چمپ«مپھم‚‹مپ¨è¨€م‚ڈم‚Œمپ¦مپٹم‚ٹم€پè…گèچ‰ï¼ˆمپڈمپ،مپڈمپ•ï¼‰مپ¨مپ¯مƒ›م‚؟مƒ«مپ®مپ“مپ¨مپ§مپ‚م‚‹م€‚و™‹مپ®و”؟و²»ه®¶مƒ»è»ٹ胤مپ¯م€پç”ںه®¶مپŒè²§مپ—مپڈم€پçپ¯çپ«مپ®و²¹مپŒè²·مپˆمپھمپ‹مپ£مپںمپ®مپ§م€پè›چمپ®ه…‰مپ§و›¸ç‰©م‚’èھم‚“مپ م€‚مپ“مپ®مپ“مپ¨مپ¯م€پé›ھوکژم‚ٹمپ§ه‹‰ه¼·مپ—مپںه«ه؛·مپ¨مپ¨م‚‚مپ«م€Œè›چé›ھمپ®هٹںم€چمپ®و•…ن؛‹مپ¨مپھم‚ٹم€پو—¥وœ¬مپ§مپ¯م€Œè›چمپ®ه…‰م€چمپ®ه”±وŒمپ«مپھمپ£مپںم€‚
ن¸ه›½مپ§مپ¯م€پèچ‰مپŒè…گمپ£مپ¦è›چمپ«مپھم‚‹مپ¨è¨€م‚ڈم‚Œمپ¦مپٹم‚ٹم€پè…گèچ‰ï¼ˆمپڈمپ،مپڈمپ•ï¼‰مپ¨مپ¯مƒ›م‚؟مƒ«مپ®مپ“مپ¨مپ§مپ‚م‚‹م€‚و™‹مپ®و”؟و²»ه®¶مƒ»è»ٹ胤مپ¯م€پç”ںه®¶مپŒè²§مپ—مپڈم€پçپ¯çپ«مپ®و²¹مپŒè²·مپˆمپھمپ‹مپ£مپںمپ®مپ§م€پè›چمپ®ه…‰مپ§و›¸ç‰©م‚’èھم‚“مپ م€‚مپ“مپ®مپ“مپ¨مپ¯م€پé›ھوکژم‚ٹمپ§ه‹‰ه¼·مپ—مپںه«ه؛·مپ¨مپ¨م‚‚مپ«م€Œè›چé›ھمپ®هٹںم€چمپ®و•…ن؛‹مپ¨مپھم‚ٹم€پو—¥وœ¬مپ§مپ¯م€Œè›چمپ®ه…‰م€چمپ®ه”±وŒمپ«مپھمپ£مپںم€‚ ه¯’مپ•مپ«مپ¯ه¼·مپ„é´‰مپ§مپ‚م‚‹مپŒم€په†¬ه ´مپ«مپ¯é›†ه›£مپ§و£®مپھمپ©مپ«مپمپگم‚‰م‚’ن½œم‚‹ç؟’و€§مپŒمپ‚م‚‹مپںم‚پمپ«م€پ群م‚Œمپ§è¦‹مپ‹مپ‘م‚‹مپ“مپ¨مپŒه¤ڑمپڈمپھم‚‹م€‚é´‰مپŒé›†ه›£مپ§ه¸°م‚‹ه¤•و™¯مپŒè¦‹م‚‰م‚Œم‚‹مپ®م‚‚م€پ秋مپ‹م‚‰ه†¬مپ«مپ‹مپ‘مپ¦مپ§مپ‚م‚‹م€‚
ه¯’مپ•مپ«مپ¯ه¼·مپ„é´‰مپ§مپ‚م‚‹مپŒم€په†¬ه ´مپ«مپ¯é›†ه›£مپ§و£®مپھمپ©مپ«مپمپگم‚‰م‚’ن½œم‚‹ç؟’و€§مپŒمپ‚م‚‹مپںم‚پمپ«م€پ群م‚Œمپ§è¦‹مپ‹مپ‘م‚‹مپ“مپ¨مپŒه¤ڑمپڈمپھم‚‹م€‚é´‰مپŒé›†ه›£مپ§ه¸°م‚‹ه¤•و™¯مپŒè¦‹م‚‰م‚Œم‚‹مپ®م‚‚م€پ秋مپ‹م‚‰ه†¬مپ«مپ‹مپ‘مپ¦مپ§مپ‚م‚‹م€‚















 秋مپ®ه†·و°—مپ¯ه¯‚مپ—مپ•م‚’ه¢—é•·مپ—م€پè؛«مپ«و·±مپڈمپ—مپ؟مپ¦مپڈم‚‹م€‚ه¾Œو‹¾éپ؛ه’ŒوŒé›†مپ«م€پم‚ˆمپ؟ن؛؛مپ—م‚‰مپڑمپ®وŒمپŒè¼‰م‚‹م€‚
秋مپ®ه†·و°—مپ¯ه¯‚مپ—مپ•م‚’ه¢—é•·مپ—م€پè؛«مپ«و·±مپڈمپ—مپ؟مپ¦مپڈم‚‹م€‚ه¾Œو‹¾éپ؛ه’ŒوŒé›†مپ«م€پم‚ˆمپ؟ن؛؛مپ—م‚‰مپڑمپ®وŒمپŒè¼‰م‚‹م€‚ ه†¬مپ®و—¥مپ®ه¤•و–¹مپ¯و—¥و²،م‚‚و—©مپ„مپŒم€په†¬è‡³مپŒن¸€ç•ھو—¥و²،و™‚é–“مپŒو—©مپ„مپ®مپ§مپ¯مپھمپ„م€‚12وœˆن¸ٹو—¬مپ‹م‚‰ن¸و—¬مپ«مپ‹مپ‘مپ¦م€پو±ن؛¬مپ§مپ¯16و™‚30هˆ†é ƒمپ«و—¥مپŒو²ˆم‚€م€‚ه¤§éکھمپ§مپ¯مپم‚Œم‚ˆم‚ٹç´„20هˆ†éپ…مپڈم€پç¦ڈه²،مپ§مپ¯و±ن؛¬م‚ˆم‚ٹç´„40هˆ†éپ…مپ„م€‚
ه†¬مپ®و—¥مپ®ه¤•و–¹مپ¯و—¥و²،م‚‚و—©مپ„مپŒم€په†¬è‡³مپŒن¸€ç•ھو—¥و²،و™‚é–“مپŒو—©مپ„مپ®مپ§مپ¯مپھمپ„م€‚12وœˆن¸ٹو—¬مپ‹م‚‰ن¸و—¬مپ«مپ‹مپ‘مپ¦م€پو±ن؛¬مپ§مپ¯16و™‚30هˆ†é ƒمپ«و—¥مپŒو²ˆم‚€م€‚ه¤§éکھمپ§مپ¯مپم‚Œم‚ˆم‚ٹç´„20هˆ†éپ…مپڈم€پç¦ڈه²،مپ§مپ¯و±ن؛¬م‚ˆم‚ٹç´„40هˆ†éپ…مپ„م€‚