投稿者: uranari
季語|紫雲英(げんげ)
仲春の季語 紫雲英
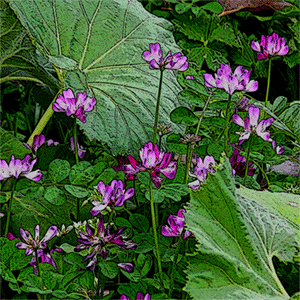 中国原産の、マメ科ゲンゲ属に分類される越年草で、日本へは17世紀ころ渡来してきたと考えられている。4月ころに花をつける。
中国原産の、マメ科ゲンゲ属に分類される越年草で、日本へは17世紀ころ渡来してきたと考えられている。4月ころに花をつける。
蓮に花が似ていることから、「れんげ」「れんげそう」とも呼ぶ。「紫雲英」は、一面に咲く花を、低くたなびく紫雲に見立てたところからきており、通常は「しうんえい」と読む。「げんげ」は「れんげ」の転訛。
紫雲英は、淡黄色のよい蜂蜜がとれることでも知られ、「はちみつの王様」とも呼ばれている。
化学肥料が自由に使えなかった頃は、8月から9月頃に種をまいて、翌春の田植え前にれんげ畑となったところを鋤き込んで、緑肥とした。戦後は、化学肥料の使用が自由になったことなどにより、れんげ畑は急速に減っている。
ギリシア神話には、紫雲英にまつわるドリュオペとイオレの姉妹の神話がある。祭壇の花にするため、ドリュオペが摘んだ紫雲英は、ニンフが変身したものだったというもの。イオレに、「女神が姿を変えたものだから、もう花は摘んではならない」と言いながら、ドリュオペは紫雲英に変わっていったという。
1966年(昭和41年)、運輸相に抜擢された政治家荒舩清十郎は、深谷駅問題などで辞任に追い込まれた。その時に、川島正次郎自民党副総裁が、「野におけレンゲ草だったよ」と荒舩清十郎を、表舞台に立つべきではない人物だったと評している。その言葉の元となったのは、滝野瓢水の「手に取るなやはり野に置け蓮華草」。遊女を身請しようとした友人を止めるために詠んだ句である。
【紫雲英の俳句】
げんげ田や故郷へつづく雲流れ 西村冬水
季語|蓬(よもぎ)
三春の季語 蓬
 中央アジア原産のキク科の多年草。日本では在来種として、本州以南に自生する。特有の香りを持ち、ハーブの女王の異名がある。
中央アジア原産のキク科の多年草。日本では在来種として、本州以南に自生する。特有の香りを持ち、ハーブの女王の異名がある。
繁殖力が強く、地下茎を伸ばして集団で生えている。早春に若芽を出し、8月から10月にかけて、淡褐色の小花を穂状につける。風媒花であり、秋の花粉症の原因ともなる。
食材に用いることが多い春の季語となるが、「夏蓬」という夏の季語にもなる。
別名を餅草(もちぐさ)といい、餅に入れて食すほか、新芽を汁物の具にしたり、天ぷらにしたりする。また、灸に使うもぐさにしたり、漢方薬にもなる。
語源説にはいくつかあるが、よく繁殖して四方に広がる様を「四方草(よもぎ)」と書いたという説が有力。万葉集の大伴家持の長歌には「余母疑(よもぎ)」と詠み込まれているが、古くは「さしも草」とも呼ばれ、小倉百人一首第51番には藤原実方朝臣の和歌(後拾遺集)で、
かくどだにえやは伊吹のさしも草 さしも知らじな燃ゆる思ひを
がある。
【蓬の俳句】
蓬つむ洗ひざらしの母の指 中尾寿美子
季語|薊(あざみ)
晩春の季語 薊
眉はき(まゆはき)
 キク科アザミ属で、日本では100種類ほどが知られており、春から秋にかけて花が咲く。「薊」だけでは春の季語であるが、夏の季語となる「夏薊」、秋の季語である「富士薊」などがある。
キク科アザミ属で、日本では100種類ほどが知られており、春から秋にかけて花が咲く。「薊」だけでは春の季語であるが、夏の季語となる「夏薊」、秋の季語である「富士薊」などがある。
日本での普通種はノアザミ。
紫だけでなく、黄色や赤色の花を咲かすアザミもある。多くの種類があるアザミは交雑しやすく、雑種を多く生じている。そのため、詳細な分類が難しい植物である。
葉や総苞にトゲがあるため、驚くという意味の「あざむ」が語源だと考えられている。古くは、婦人の眉払の形に似ていたため、「眉作(まゆつくり)の花」と呼んだ。「山ごぼう」として新芽や根を食す地方もある。
花言葉は「独立」「触れないで」「報復」「守護」。ノルウェー軍の侵攻を、薊のトゲを踏みしめる音で感知して勝利したことにちなみ、スコットランドでは国花となっている。
【薊の俳句】
この野道薊の外に花もなし 久保より江
季語|春休み(はるやすみ)
季語|子猫(こねこ)
晩春の季語 子猫
孕猫(はらみねこ)・猫の産(ねこのさん)・猫の子(ねこのこ)・親猫(おやねこ)
 猫の繁殖は1月から8月頃まで続き、妊娠期間は約65日。よって、冬場を除いて子猫は生まれるが、子猫が最も多くみられるのは春である。
猫の繁殖は1月から8月頃まで続き、妊娠期間は約65日。よって、冬場を除いて子猫は生まれるが、子猫が最も多くみられるのは春である。
猫は、一度の出産で2~6匹ほどが生まれる。生まれたてはオス・メスの区別が難しく、ひと月くらいしてはじめて判別できる。半年から一年たてば発情が始まるため、子猫の期間は1年ほどと短い。
▶ 関連季語 猫の恋(春)
▶ 俳句になった生物(猫)
季語|遍路(へんろ)
三春の季語 遍路
 順路に沿って霊場を巡回する巡礼の風習は、世界各地に広がっている。日本では、四国八十八箇所や、西国三十三所などがある。けれども、「遍路」と言うと、おのずと四国八十八箇所を指し、その巡礼や巡礼者のことを言う。それには、語源となった「辺土」が絡んでいると考えられる。
順路に沿って霊場を巡回する巡礼の風習は、世界各地に広がっている。日本では、四国八十八箇所や、西国三十三所などがある。けれども、「遍路」と言うと、おのずと四国八十八箇所を指し、その巡礼や巡礼者のことを言う。それには、語源となった「辺土」が絡んでいると考えられる。
四国では古くから、修行の地となるような辺境の地を「辺土」と言い表していた。それが、弘法大師信仰とともに、あまねく照らす道という意味の「遍路」に置き換えられた。
遍路は四季を通じて見られるものであるが、昭和初期より、春の季語として認識されるようになった。遍路が増える季節が春であり、この時期、菜の花や桜の花に、死装束を纏う遍路も映える。季語としての確立には、四国出身の高浜虚子の影響が大きかったとも。
四国遍路は、弘法大師ゆかりの寺院八十八箇所を順に巡るもの。空海42歳の厄年(815年)に開創したものとされているが、その巡礼の確立には諸説ある。有名なものに、衛門三郎伝説がある。
衛門三郎は、四国松山の強欲な豪農。托鉢僧の鉢を割って追い払った時から、8人の子どもが次々に亡くなり、その僧が弘法大師だったと気付くに至る。
弘法大師を探し求めて、霊場を20回も訪ね歩いた衛門三郎は、出会えなかったことから逆打ちするも、力尽きて阿波の焼山寺近くで倒れてしまう。その時はじめて弘法大師が現れ、その腕に抱かれた衛門三郎は非礼を詫び、「来世は河野家に生まれ、善を尽くしたい」と願いを述べて死ぬ。弘法大師が衛門三郎と書いた石を握らせ葬ると、翌年、伊予河野氏に子供が生まれた。その子は、左手に衛門三郎と書いた石を握っていたという。
その石を納めた安養寺は、このことをもって石手寺に改める。現在では霊場有数の規模を持つ寺院となっており、その石は一般公開されている。
因みに、石手寺近くの宝厳寺で生まれた一遍も河野氏一族であり、弘法大師を慕って四国巡礼を行っている。なお、四国遍路は死地へ赴くことであり、白い死装束をまとって巡るものとなっている。
現在のような遍路の整備は、室町時代から、庶民に巡礼の流行があった江戸時代にかけて行われたもので、1950年代より観光バスによる巡礼も行われるようになり、身近になることで遍路ブームを巻き起こした。
現在では、海外からの注目度も高く、世界遺産に推す声も高い。霊場中には、弘法大師の生地である善通寺、弘法大師開眼の地に近い最御崎寺、崇徳天皇陵がある白峰寺などがある。
四国遍路は総行程1400㎞。歩いて40日、自転車で20日、車で10日を要する。一番札所は徳島の霊山寺であるが、これは、上方に近い交通事情に因る。
弘法大師の和歌と伝わるものに、「土佐国室戸といふところにて」の前書きとともに、
法性のむろとといへどわがすめば うゐの浪風よせぬ日ぞなき
【遍路の俳句】
道のべに阿波の遍路の墓あはれ 高浜虚子
夕遍路雨もほつほつ急ぎ足 高野素十
季語|蛇穴を出づ(へびあなをいづ)
季語|風光る(かぜひかる)
三春の季語 風光る
 俳諧歳時記栞草に、初学記の引用で「春晴日出て風吹を光風といふと、云々。これによりていふか。此詞古抄にみえず。」
俳諧歳時記栞草に、初学記の引用で「春晴日出て風吹を光風といふと、云々。これによりていふか。此詞古抄にみえず。」
晴れ上がった春の日に吹く風は、爽やかで光り輝くように感じられる。
季語|春一番(はるいちばん)
仲春の季語 春一番
 立春から春分の間に、その年に初めて、南寄りの暖かい強い風(秒速8メートル以上)が吹くことをいう。日本海で低気圧が発達することにより発生し、海難事故や雪崩を誘発する。翌日は寒の戻りとなることが多い。
立春から春分の間に、その年に初めて、南寄りの暖かい強い風(秒速8メートル以上)が吹くことをいう。日本海で低気圧が発達することにより発生し、海難事故や雪崩を誘発する。翌日は寒の戻りとなることが多い。
春一番は、観測されない年もあり、春二番・春三番が確認される年もある。
「春一番」という言葉は、石川県能登地方などで昔から用いられていたものであり、「春一(はるいち)」と呼んだりもする。民俗学者の宮本常一が隠岐地方の調査を、俳句歳時記(1959年)に反映させたことで、一般的な言葉になったという。1963年2月15日の朝日新聞朝刊で取り上げられたことにより、2月15日は「春一番名付けの日」となっている。1976年には、キャンディーズが「春一番」を歌ってヒットさせている。
【春一番の俳句】
胸ぐらに母受けとむる春一番 岸田稚魚


 日本では、4月を年度初めとするため、春休みは、別れとスタートの期間ともなる。卒業生は、3月31日までは、学んできた学校に籍がある。
日本では、4月を年度初めとするため、春休みは、別れとスタートの期間ともなる。卒業生は、3月31日までは、学んできた学校に籍がある。