三春の季語 陽炎
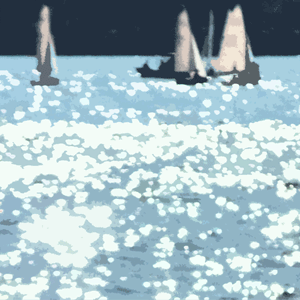 風が弱く日差しが強い日には、大地からの蒸気で、遠くのものが揺らいで見える。「陽炎」は、春に限られた現象ではないが、春の陽気を酌んで春の季語とする。また、「かぎろひの」は、「春」「あるかなきか」などに掛かる枕詞でもある。
風が弱く日差しが強い日には、大地からの蒸気で、遠くのものが揺らいで見える。「陽炎」は、春に限られた現象ではないが、春の陽気を酌んで春の季語とする。また、「かぎろひの」は、「春」「あるかなきか」などに掛かる枕詞でもある。
古くは、揺れながら輝くもの全てを「かぎろひ」と表現しており、「輝く火(陽)」の意であった。「陽炎」はそれが限定的になったものである。そのため、カゲロウやトンボのような光を反射する羽を持った昆虫を、「かげろう」と言うこともある。
俳諧歳時記栞草では、「篗纑輪」(1753年千梅)の引用で、「陽炎」と「糸遊」を同じものだとしながらも、「春気、地より昇るを陽炎或はかげろふもゆる」「空にちらつき、又降るをいとゆふ」と言っている。
万葉集には、柿本人麻呂の和歌
東の野に炎の立つ見えて かへり見すれば月傾きぬ
があるが、この炎(かぎろひ)は、東の空が赤くなって明けていく様を言っている。万葉集ではこの他にも
今さらに雪降らめやもかぎろひの 燃ゆる春へとなりにしものを
とも歌われている。
陽炎は、直進する光線が、空気の密度が異なる場所で、密度のより高い方へ傾くために起こる現象である。この揺らぎを「シュリーレン現象」と呼ぶ。同じメカニズムで発生するものに「蜃気楼」があり、こちらも春の季語となっている。
【陽炎の俳句】
入かゝる日も糸ゆふの名残かな 松尾芭蕉
陽炎や昔し戀せし道の草 夏目成美
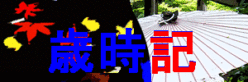

 二枚貝綱ニッコウガイ科に「サクラガイ」という種がある。よく似た貝に「ベニガイ」「カバザクラ」「モモノハナガイ」などもあり、これら数センチの大きさのピンク色の二枚貝を総称して「桜貝」という。
二枚貝綱ニッコウガイ科に「サクラガイ」という種がある。よく似た貝に「ベニガイ」「カバザクラ」「モモノハナガイ」などもあり、これら数センチの大きさのピンク色の二枚貝を総称して「桜貝」という。 藻類を食用として加工した海苔は、古くは「紫菜」とか「神仙菜」と呼ばれていた。「のり」の語源は、滑った様を表す「ぬら」だと言われ、かつては、岩場などに繁殖した藻類のことを指していた。
藻類を食用として加工した海苔は、古くは「紫菜」とか「神仙菜」と呼ばれていた。「のり」の語源は、滑った様を表す「ぬら」だと言われ、かつては、岩場などに繁殖した藻類のことを指していた。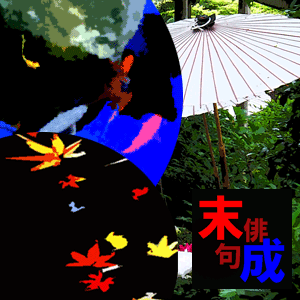 聖バレンタインデー・バレンタインの日ともいう、毎年2月14日に行われるカップルの愛の誓いの日。
聖バレンタインデー・バレンタインの日ともいう、毎年2月14日に行われるカップルの愛の誓いの日。 鳥綱カモ目カモ科オシドリ属の水鳥。東アジアに分布し、夏に北海道や東日本で繁殖する。冬になると西日本へも南下し越冬するため、冬の季語となる。
鳥綱カモ目カモ科オシドリ属の水鳥。東アジアに分布し、夏に北海道や東日本で繁殖する。冬になると西日本へも南下し越冬するため、冬の季語となる。 気温が氷点下(通常気圧で摂氏0度)まで下がると、氷ができる。一年で最も気温が下がるのは
気温が氷点下(通常気圧で摂氏0度)まで下がると、氷ができる。一年で最も気温が下がるのは 戸外で暖をとるために、落葉などを集めて火を焚くことをいうが、その火を指すこともある。歴史は古く、40万年以上前から焚火は行われていたと考えられており、日本では長崎県佐世保市の洞窟内で、旧石器時代の焚火跡がみつかっている。
戸外で暖をとるために、落葉などを集めて火を焚くことをいうが、その火を指すこともある。歴史は古く、40万年以上前から焚火は行われていたと考えられており、日本では長崎県佐世保市の洞窟内で、旧石器時代の焚火跡がみつかっている。 雪上を移動するために、靴に板をつけていたものが、現代ではスポーツになった。競技は、クロスカントリーやジャンプなどがあるノルディックスキーと、ノルディックスキーから分かれて滑降に特化したアルペンスキーがある。
雪上を移動するために、靴に板をつけていたものが、現代ではスポーツになった。競技は、クロスカントリーやジャンプなどがあるノルディックスキーと、ノルディックスキーから分かれて滑降に特化したアルペンスキーがある。 雪を2つ丸めて、それぞれ頭と胴としたものを、重ねてダルマ型とする。木の枝などを使って目鼻もつける。海外にも同様のものがあり、日本語訳では「雪人」「雪男」「雪人形」などとされるが、日本のものと違って3段になっているものが普通である。
雪を2つ丸めて、それぞれ頭と胴としたものを、重ねてダルマ型とする。木の枝などを使って目鼻もつける。海外にも同様のものがあり、日本語訳では「雪人」「雪男」「雪人形」などとされるが、日本のものと違って3段になっているものが普通である。