初春の季語 片栗の花
 ユリ科カタクリ属に属する50年ほど生きる多年草で、万葉集に大伴家持が歌った
ユリ科カタクリ属に属する50年ほど生きる多年草で、万葉集に大伴家持が歌った
もののふの八十娘子らが汲み乱ふ 寺井の上の堅香子の花
の「堅香子(かたかご)」は片栗のことだと言われている。この「かたかご」が「かたかごゆり」となり、「かたくり」に転訛したと考えられている。
旧正月の頃に花をつけるため、初百合とも呼ばれる。ただし、山地では6月頃まで花は残っている。花は普通は紫であるが、シロバナカタクリと呼ばれる白色のものもある。ニリンソウなどとともに群生をつくり、「スプリング・エフェメラル(春の妖精)」と呼ばれている。
カタクリは、春先から初夏の2か月ほどしか地上に現れず、一年の大半を土中の鱗茎として休眠する。そのため、花を咲かせるための栄養を蓄積するまでに時間がかかり、種子の発芽から花を咲かせるまでに10年近くの歳月を要する。
良く知られている片栗粉は、もともとはこの片栗の鱗茎を日干して抽出したもので、滋養など様々な薬効が知られていた。しかし採れる量が少ないため、現在ではそのほとんどがジャガイモなどから精製されており、薬効も認められない。
【片栗の花の俳句】
日をかけて咲く片栗の蔭の花 馬場移公子

 ハタ科の海水魚にサクラダイがあるが、季語となるのは、真鯛。
ハタ科の海水魚にサクラダイがあるが、季語となるのは、真鯛。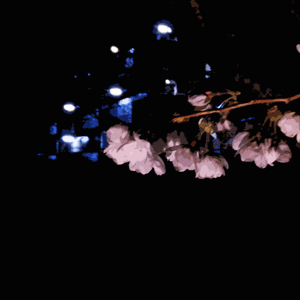 日が伸びゆく中に明りを灯せば、明るく艶やかなイメージが広がる。和歌では、玉葉和歌集の藤原定家に
日が伸びゆく中に明りを灯せば、明るく艶やかなイメージが広がる。和歌では、玉葉和歌集の藤原定家に 陰暦三月のことであるが、新暦3月の別名としても用いる。
陰暦三月のことであるが、新暦3月の別名としても用いる。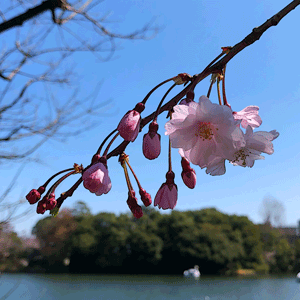 陰暦二月。啓蟄から春分まで。七十二候では、蟄虫啓戸・桃始笑・菜虫化蝶・雀始巣・桜始開・雷乃発声。
陰暦二月。啓蟄から春分まで。七十二候では、蟄虫啓戸・桃始笑・菜虫化蝶・雀始巣・桜始開・雷乃発声。 春一番も春風であり、春風は時に恐ろしいものであるが、季語で「春風」を用いる時には、「春風駘蕩」の言葉もあるように、のどかなあたたかさが強調される。また、
春一番も春風であり、春風は時に恐ろしいものであるが、季語で「春風」を用いる時には、「春風駘蕩」の言葉もあるように、のどかなあたたかさが強調される。また、 春の日中は、日脚がのびて長く感じる。因みに、「
春の日中は、日脚がのびて長く感じる。因みに、「 春先、暖かくなり始めた頃に急に寒さが戻ることがある。「寒の戻り」と言ったり「凍返る」と言ったりもする。関連季語に「
春先、暖かくなり始めた頃に急に寒さが戻ることがある。「寒の戻り」と言ったり「凍返る」と言ったりもする。関連季語に「 冬鳥として渡ってきたマガモなどの鴨が、春になってロシア東部から極東にかけての北方へ帰っていく様を引鴨という。地域によって違いはあるが、3月頃が渡りのピークである。
冬鳥として渡ってきたマガモなどの鴨が、春になってロシア東部から極東にかけての北方へ帰っていく様を引鴨という。地域によって違いはあるが、3月頃が渡りのピークである。 俳句での「風車」は、玩具の風車であり、「かざぐるま」として春の季語となる。ただし、キンポウゲ科に「風車」の名を持つ花があり、「風車の花」で夏の季語となる。
俳句での「風車」は、玩具の風車であり、「かざぐるま」として春の季語となる。ただし、キンポウゲ科に「風車」の名を持つ花があり、「風車の花」で夏の季語となる。