晩春の季語 桜
花(はな)・花見(はなみ)・桜狩(さくらがり)・花盛り(はなざかり)・花吹雪(はなふぶき)・夕桜(ゆうざくら)
 バラ科サクラ属の落葉高木。現在では「花」と言えば、一般的には「桜」を指す。エドヒガンやヤマザクラは、古くから日本に自生していた。桜から派生した季語も非常に多く、桜の散り際に見られる「花吹雪」「花筏」、桜の咲くころの空を表現した「花曇」「養花天」、花見衣装の「花衣」など、枚挙に遑がない。
バラ科サクラ属の落葉高木。現在では「花」と言えば、一般的には「桜」を指す。エドヒガンやヤマザクラは、古くから日本に自生していた。桜から派生した季語も非常に多く、桜の散り際に見られる「花吹雪」「花筏」、桜の咲くころの空を表現した「花曇」「養花天」、花見衣装の「花衣」など、枚挙に遑がない。
また、古くから歌にうたわれ、万葉集にも約40首の歌が載せられているが、梅の119首に比べると少ないことから、古代人が愛でた花は主に梅だったと言われる。紀貫之が古今集で「安積山の歌」とともに歌の父母とした王仁の
難波津に咲くやこの花冬ごもり今は春べと咲くやこの花
の「この花」は、その季節感から梅とされるが、これは「此の花」であり、高所に花をつける「木の花」とは異なるという考えもある。
皇祖の母神コノハナサクヤビメは、「サクヤ」から「サクラ」の語源にもなったとされる神で、富士山を祀る浅間大社に鎮座する。太宰治の「富嶽百景」で、「富士には月見草がよく似合う」と謳われるが、これは、富士でかぐや姫の遺した不死の薬を焼いたとされる竹取物語を参考にしたもので、本来の富士の姿は桜である。
また、太古より日本にはサガミ信仰という、稲の神霊「サガミ」が桜の木に宿るという信仰があり、山に入って花見を行いその年の豊穣を祈っていたという説がある。これを基に、「サ神」が宿る神座(クラ)を「サクラ」とする語源説もある。いずれにせよ、桜は太古より特別な花だったことから、多くの名歌が生まれている。
世の中にたえてさくらのなかりせば春の心はのどけからまし 在原業平「古今和歌集」
ひさかたの光のどけき春の日に静心なく花の散るらむ 紀友則「古今和歌集」
花の色はうつりにけりないたづらに我が身世にふるながめせしまに 小野小町「古今和歌集」
願はくは花の下にて春死なんそのきさらぎの望月のころ 西行法師「続古今和歌集」
なお、弘仁2年(811年)に地主神社を訪れた嵯峨天皇は、「御車返しの桜」とも呼ばれるようになった桜に惚れ、これを機に、「梅」と「桜」の地位が逆転し、梅よりも桜が愛でられるようになったともいう。
▶ 関連季語 八重桜(春)
▶ 関連季語 枝垂桜(春)
▶ 関連季語 山桜(春)
▶ 関連季語 初桜(春)
▶ 関連季語 寒桜(冬)
 イネ科ススキ属の植物。「茅(かや)」と呼ばれ、茅葺屋根の材料となる。万葉集には44首歌われていると言われ、「すすき」「をばな」「草(かや)」「み草」として出てくる。「すすき」として歌われる場合、しばしば「ハダススキ」として現れるが、この「ハダ」は「旗」のことだと言われ、「穂に出ず」の枕詞となる。
イネ科ススキ属の植物。「茅(かや)」と呼ばれ、茅葺屋根の材料となる。万葉集には44首歌われていると言われ、「すすき」「をばな」「草(かや)」「み草」として出てくる。「すすき」として歌われる場合、しばしば「ハダススキ」として現れるが、この「ハダ」は「旗」のことだと言われ、「穂に出ず」の枕詞となる。
 エドヒガンの枝垂れ品種で、ソメイヨシノより1週間ほど早く咲く。京都府の府花。
エドヒガンの枝垂れ品種で、ソメイヨシノより1週間ほど早く咲く。京都府の府花。 その年に初めて咲いた桜、あるいは、咲いて間もない桜をいう。「初花」とも呼び、18歳くらいの女性のことをも指す。
その年に初めて咲いた桜、あるいは、咲いて間もない桜をいう。「初花」とも呼び、18歳くらいの女性のことをも指す。











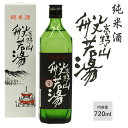


 ヤマザクラとマメザクラを交配したフユザクラは、11月から1月頃に花を咲かす。緋寒桜とも呼ばれるカンヒザクラは、これとは別種で、1月から3月頃に花を咲かせる。
ヤマザクラとマメザクラを交配したフユザクラは、11月から1月頃に花を咲かす。緋寒桜とも呼ばれるカンヒザクラは、これとは別種で、1月から3月頃に花を咲かせる。 バラ科サクラ属の落葉高木。現在では「花」と言えば、一般的には「桜」を指す。エドヒガンやヤマザクラは、古くから日本に自生していた。桜から派生した季語も非常に多く、桜の散り際に見られる「花吹雪」「花筏」、桜の咲くころの空を表現した「花曇」「養花天」、花見衣装の「花衣」など、枚挙に遑がない。
バラ科サクラ属の落葉高木。現在では「花」と言えば、一般的には「桜」を指す。エドヒガンやヤマザクラは、古くから日本に自生していた。桜から派生した季語も非常に多く、桜の散り際に見られる「花吹雪」「花筏」、桜の咲くころの空を表現した「花曇」「養花天」、花見衣装の「花衣」など、枚挙に遑がない。 バラ科サクラ属の落葉高木。
バラ科サクラ属の落葉高木。 単に「祭」といった場合は夏の季語となる。神を「祀る」ことからきており、「奉る」と同源だと考えられている。また、「まつらう」に語源があるという説もあり、こちらは、神に順い奉仕することを指す。
単に「祭」といった場合は夏の季語となる。神を「祀る」ことからきており、「奉る」と同源だと考えられている。また、「まつらう」に語源があるという説もあり、こちらは、神に順い奉仕することを指す。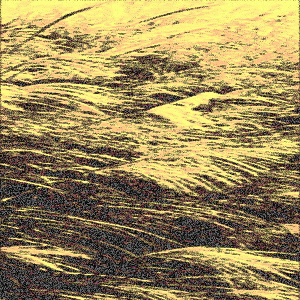 東経100°から180°までの北半球に発生する、最大風速17.2m/s以上の強い低気圧を台風という。その中心は「台風の目」と言われるが、下降気流となり、晴れ渡っている。
東経100°から180°までの北半球に発生する、最大風速17.2m/s以上の強い低気圧を台風という。その中心は「台風の目」と言われるが、下降気流となり、晴れ渡っている。 アジサイ科アジサイ属。日本に自生するガクアジサイが、アジサイの原種。梅雨時に最も映える植物であり、夏の季語となる。
アジサイ科アジサイ属。日本に自生するガクアジサイが、アジサイの原種。梅雨時に最も映える植物であり、夏の季語となる。 秋に渡って来る羽の色の美しい小鳥。また、秋に渡ってくる「色々な鳥」の意ともいう。
秋に渡って来る羽の色の美しい小鳥。また、秋に渡ってくる「色々な鳥」の意ともいう。