三夏の季語 夏草
 夏に繁茂する草。日射しの強い日中は、叢の中が高温多湿になって、息が詰まるほどの熱気を発する。これを「草いきれ」と言い、夏の季語となっている。
夏に繁茂する草。日射しの強い日中は、叢の中が高温多湿になって、息が詰まるほどの熱気を発する。これを「草いきれ」と言い、夏の季語となっている。
夏の草として代表的なものは、クズ・メヒシバ・オヒシバ・ブタクサなどである。
古くは、「草」と言えば夏のイメージが強かったようで、古今和歌集仮名序にも「秋萩夏草を見て妻を恋ひ」とある。
古事記(允恭記)では、悲恋の物語で知られる「木梨の軽の太子」の項で、自分との仲を問われて、伊予の湯に島流しにあった軽の太子に向けて、衣通の王(軽の大郎女)が歌う。
夏草のあひねの浜の蠣貝に 足踏ますな明かしてとほれ
この歌の後に恋人を追い、心中したとか。
松尾芭蕉の「夏草や」の句は、旧暦5月13日に平泉で詠まれたもので、毛越寺境内の句碑に真蹟のものがある。
【夏草の俳句】
夏草や兵どもが夢のあと 松尾芭蕉

 夏は、夏風邪ウイルスの感染によって体調を崩すことも多い。冬の風邪とは違うウィルスなどによって引き起こされ、長引くことが多い。手足口病やプール熱が、その代表的なもの。
夏は、夏風邪ウイルスの感染によって体調を崩すことも多い。冬の風邪とは違うウィルスなどによって引き起こされ、長引くことが多い。手足口病やプール熱が、その代表的なもの。




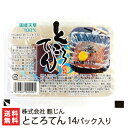





 ブナ科クリ属の栗。雌雄異花で、5月から6月に、雄花は穂状、雌花は毬状の白い花をつける。花は地味であるが、雄花は独特の臭いが印象的で、男女の交わりに掛けて詠まれる俳句もある。
ブナ科クリ属の栗。雌雄異花で、5月から6月に、雄花は穂状、雌花は毬状の白い花をつける。花は地味であるが、雄花は独特の臭いが印象的で、男女の交わりに掛けて詠まれる俳句もある。 ヒキガエル科に属す蛙の内、在来種はニホンヒキガエル・ナガレヒキガエル・アジアヒキガエルの3種。これに外来種のオオヒキガエルを加えた4種が、日本に分布している。ガマガエル・イボガエルの異名を持つ。
ヒキガエル科に属す蛙の内、在来種はニホンヒキガエル・ナガレヒキガエル・アジアヒキガエルの3種。これに外来種のオオヒキガエルを加えた4種が、日本に分布している。ガマガエル・イボガエルの異名を持つ。 ユリ目ユリ科ユリ属の多年草で、その花季から夏の季語となる。日本ではヤマユリ・ササユリ・テッポウユリなど、7種ほど特産種がある。園芸種も含め、5月から8月頃に開花し、球根は食用や薬用として活用される。
ユリ目ユリ科ユリ属の多年草で、その花季から夏の季語となる。日本ではヤマユリ・ササユリ・テッポウユリなど、7種ほど特産種がある。園芸種も含め、5月から8月頃に開花し、球根は食用や薬用として活用される。 後漢の蔡邕「月令章句」に、「百穀各以其初生為春 熟為秋 故麥以孟夏為秋」とある。つまり、穀類にとって、芽が出る時が春で、熟す時が秋となる。よって、麦にとっては初夏が秋であり、「麦秋」は夏の季語になる。
後漢の蔡邕「月令章句」に、「百穀各以其初生為春 熟為秋 故麥以孟夏為秋」とある。つまり、穀類にとって、芽が出る時が春で、熟す時が秋となる。よって、麦にとっては初夏が秋であり、「麦秋」は夏の季語になる。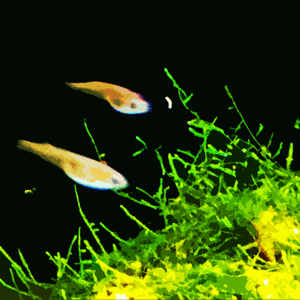 「湧泉」「湧水」とも呼ぶ、水が湧き出る所。「出づ水」が語源。その涼感をもって、夏の季語とする。俳諧歳時記栞草には6月に分類されている。
「湧泉」「湧水」とも呼ぶ、水が湧き出る所。「出づ水」が語源。その涼感をもって、夏の季語とする。俳諧歳時記栞草には6月に分類されている。 バラ科バラ属。園芸種は、世界中で最も親しまれている花のひとつで、6月の誕生花ともなっている。「いばら」の転訛から「ばら」と呼ぶ。
バラ科バラ属。園芸種は、世界中で最も親しまれている花のひとつで、6月の誕生花ともなっている。「いばら」の転訛から「ばら」と呼ぶ。













