晩秋の季語 雁
かりがね・初雁(はつかり)・雁渡る(かりわたる)・雁行(がんこう)
 カモ目カモ科ガン亜科の水鳥の中でも、カモより大きくハクチョウよりも小さい一群をいう。マガン、カリガネ、コクガン、ハクガン、ヒシクイなどがこれに当たり、首が長く、雌雄同色の特徴を持つ。冬鳥として日本に渡ってくるが、渡りの季節に目立つため、秋の季語となる。
カモ目カモ科ガン亜科の水鳥の中でも、カモより大きくハクチョウよりも小さい一群をいう。マガン、カリガネ、コクガン、ハクガン、ヒシクイなどがこれに当たり、首が長く、雌雄同色の特徴を持つ。冬鳥として日本に渡ってくるが、渡りの季節に目立つため、秋の季語となる。
V字になったりなどの編隊飛行で10月頃に北方から渡って来て、沿岸部の湖沼などで生活し、3月頃まで留まる。千葉県の印旛沼などが飛来地として知られていたが、現在では温暖化や開発の影響で、太平洋側では宮城県がマガンの飛来の南限となっている。その宮城県には、国内の8割に当たる10万羽が飛来するという、ラムサール条約にも登録されている伊豆沼・内沼がある。
現在では漢語を元にした「がん」が正式名だが、室町時代以前は「かり」と呼ばれており、現代俳句でも「かり」として詠むのが一般的。なお「かり」の名は、その鳴き声を元にしていると言われる。
古くから狩猟の対象として生活に溶け込んでいた雁は、文学上にも多く登場する。漢書の蘇武伝には、捕らえられた蘇武が、手紙を雁の足に結びつけて放ったという故事があり、そこから「雁の使い」「雁の玉章」という言葉が生まれた。60首あまりの雁の歌が載る万葉集にも、遣新羅使の和歌
天飛ぶや雁を使に得てしかも 奈良の都に言告げ遣らむ
のように「雁の使い」が詠み込まれている。
また「かりがね」という種類の雁が存在するが、もとは「雁が音」で、雁の鳴き声を言い表す言葉だったことが知られており、それが次第に「雁」全般を指す言葉に変化していき、現在では特定種を指す言葉になった。万葉集にも
我が宿に鳴きし雁がね雲の上に 今夜鳴くなり国へかも行く
という詠み人知らずの和歌をはじめ、多数が歌いこまれている。
紛らわしい季語に雁渡しがあるが、これは、雁が渡ってくる9月から10月頃に吹く北風のことである。
雁は遠くから渡ってくるため、「遠つ人」が枕詞となる。万葉集に大伴家持の和歌で、
今朝の朝明秋風寒し遠つ人 雁が来鳴かむ時近みかも
がある。
「雁字」は、雁が飛ぶ様子をいう言葉であり、「雁の使い」にも通じ「手紙」のことも指す。
【雁の俳句】
風の香の身につきそめし雁のころ 岸田稚魚
雲とへだつ友かや雁のいきわかれ 松尾芭蕉
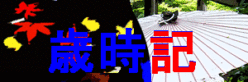
 中国あるいは東南アジア原産のバショウ科の多年草で、英名は、シーボルトによりジャパニーズ・バナナと名付けられた。冬に葉を枯らすが、春には再び葉をつけ、稀に大きな黄色い花をつける。それは「
中国あるいは東南アジア原産のバショウ科の多年草で、英名は、シーボルトによりジャパニーズ・バナナと名付けられた。冬に葉を枯らすが、春には再び葉をつけ、稀に大きな黄色い花をつける。それは「 モクセイ科モクセイ属の常緑小高木に、金木犀・銀木犀・薄黄木犀などがある。中国原産。単に「木犀」と言った場合には「銀木犀」を指す。
モクセイ科モクセイ属の常緑小高木に、金木犀・銀木犀・薄黄木犀などがある。中国原産。単に「木犀」と言った場合には「銀木犀」を指す。 春に渡ってきた燕は、子作りをした後、9月から10月頃、集団を作って南へ帰っていく。七十二候にも玄鳥去があり、9月の中旬から下旬に当たる。
春に渡ってきた燕は、子作りをした後、9月から10月頃、集団を作って南へ帰っていく。七十二候にも玄鳥去があり、9月の中旬から下旬に当たる。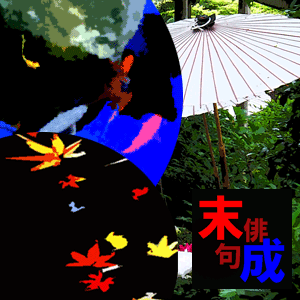 バラ科ナシ属。
バラ科ナシ属。
 湯煎で温めた酒を燗酒と言う。燗酒全般を熱燗とも呼ぶが、現在ではその温度帯に応じて、様々な呼び名がつけられている。55℃付近を「飛び切り燗」、50℃付近を「熱燗」、50℃付近を「上燗」、45℃付近を「ぬる燗」、37℃付近を「人肌燗」、それ以下を「日向燗」などと呼ぶ。
湯煎で温めた酒を燗酒と言う。燗酒全般を熱燗とも呼ぶが、現在ではその温度帯に応じて、様々な呼び名がつけられている。55℃付近を「飛び切り燗」、50℃付近を「熱燗」、50℃付近を「上燗」、45℃付近を「ぬる燗」、37℃付近を「人肌燗」、それ以下を「日向燗」などと呼ぶ。 中国では、重陽の日(陰暦9月9日・菊の節句)に酒を温めて飲むと病気にかからないと言われていた。日本にも、平安時代以前にそれが伝わっていたと見られ、酒を温める習慣がある。
中国では、重陽の日(陰暦9月9日・菊の節句)に酒を温めて飲むと病気にかからないと言われていた。日本にも、平安時代以前にそれが伝わっていたと見られ、酒を温める習慣がある。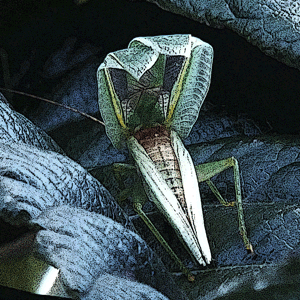 単に「虫」と言えば、蟋蟀を中心とした秋に鳴く虫を指すため、秋の季語となる。万葉集の時代、秋に鳴く虫は全て「こほろぎ」と呼ばれている(長歌に出てくる「虫」もあるが、「火に入る夏虫」である)。
単に「虫」と言えば、蟋蟀を中心とした秋に鳴く虫を指すため、秋の季語となる。万葉集の時代、秋に鳴く虫は全て「こほろぎ」と呼ばれている(長歌に出てくる「虫」もあるが、「火に入る夏虫」である)。 直翅目バッタ目コオロギ科の代表種「こおろぎ」。日本に生息するのは、最も普通に見られるエンマコオロギのほか、ミツカドコオロギ、オカメコオロギ、ツヅレサセコオロギなど。
直翅目バッタ目コオロギ科の代表種「こおろぎ」。日本に生息するのは、最も普通に見られるエンマコオロギのほか、ミツカドコオロギ、オカメコオロギ、ツヅレサセコオロギなど。